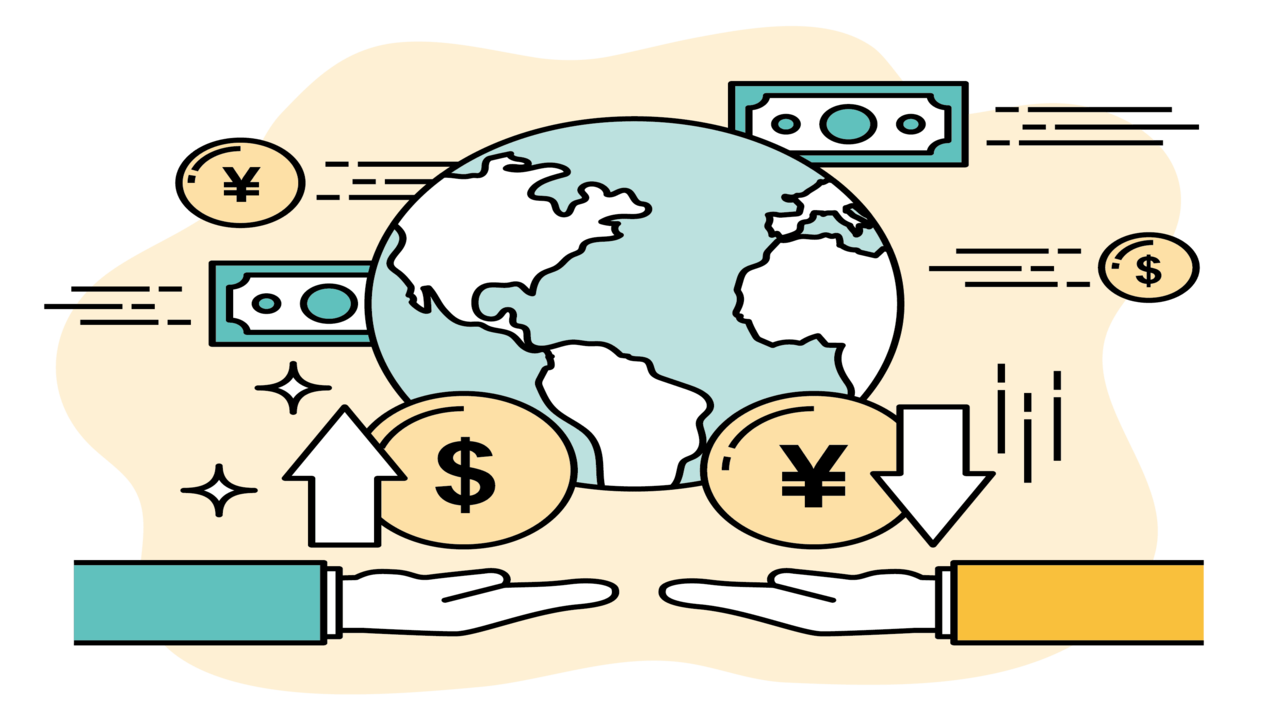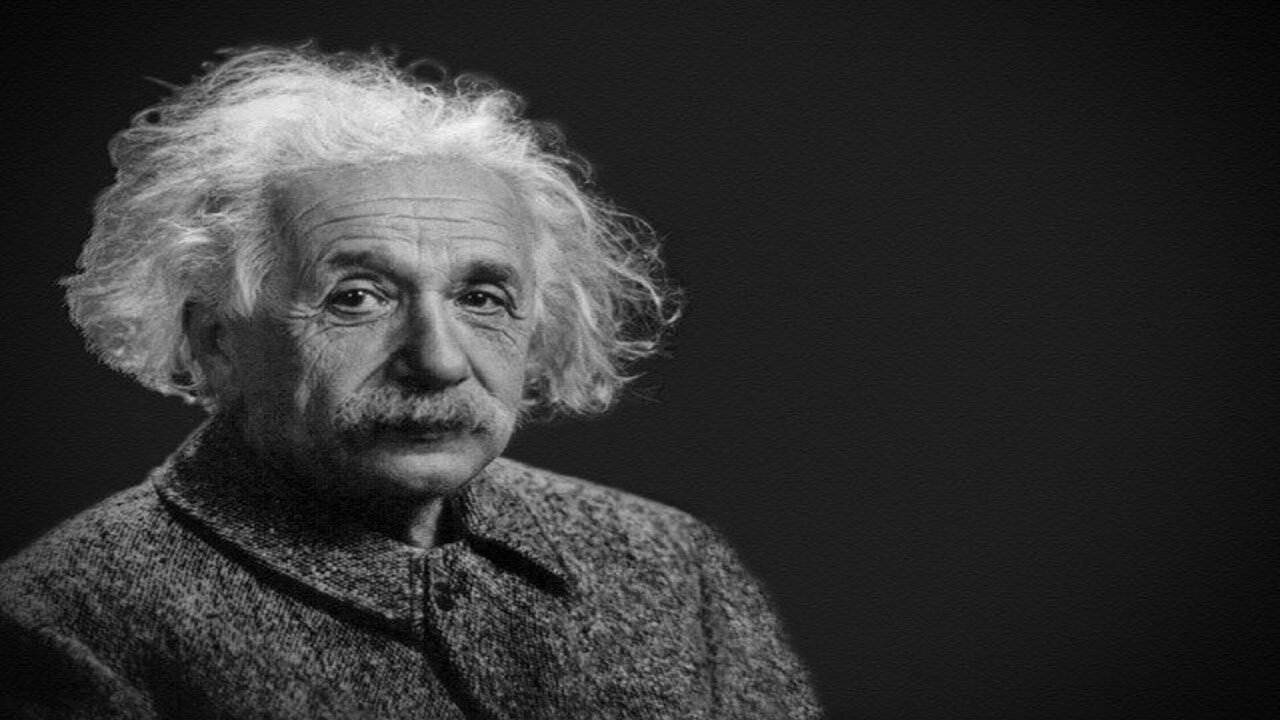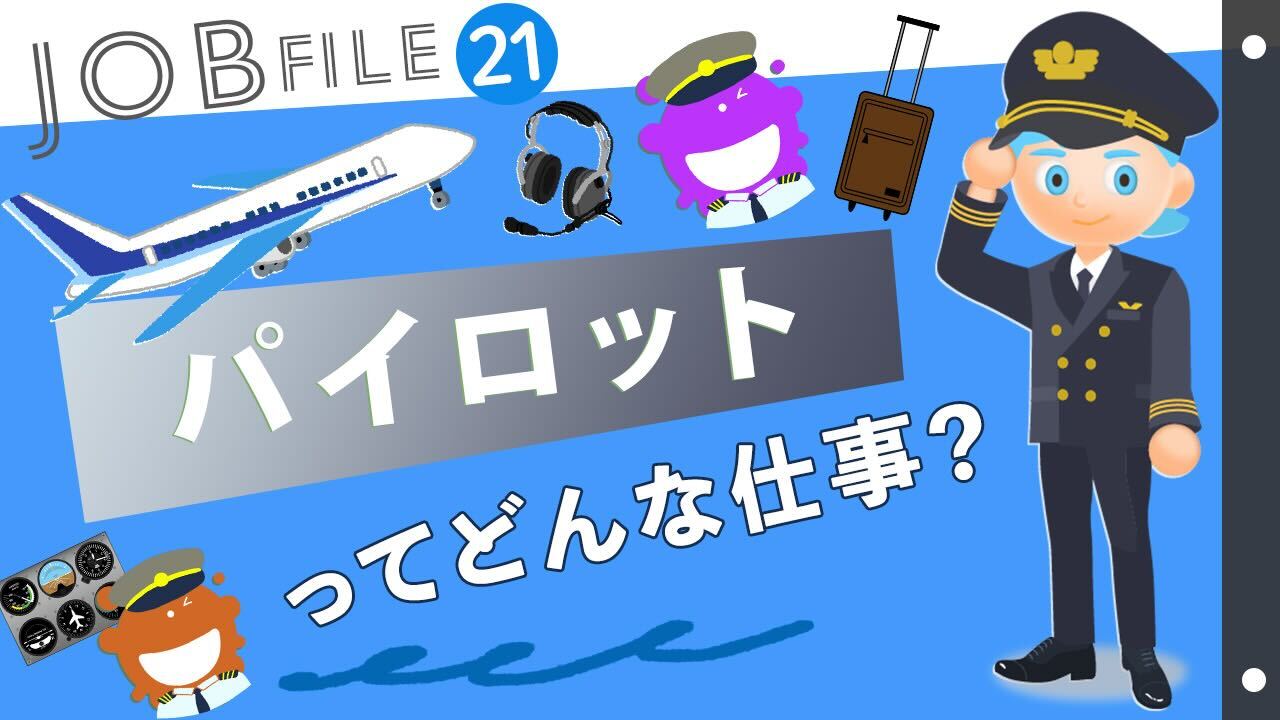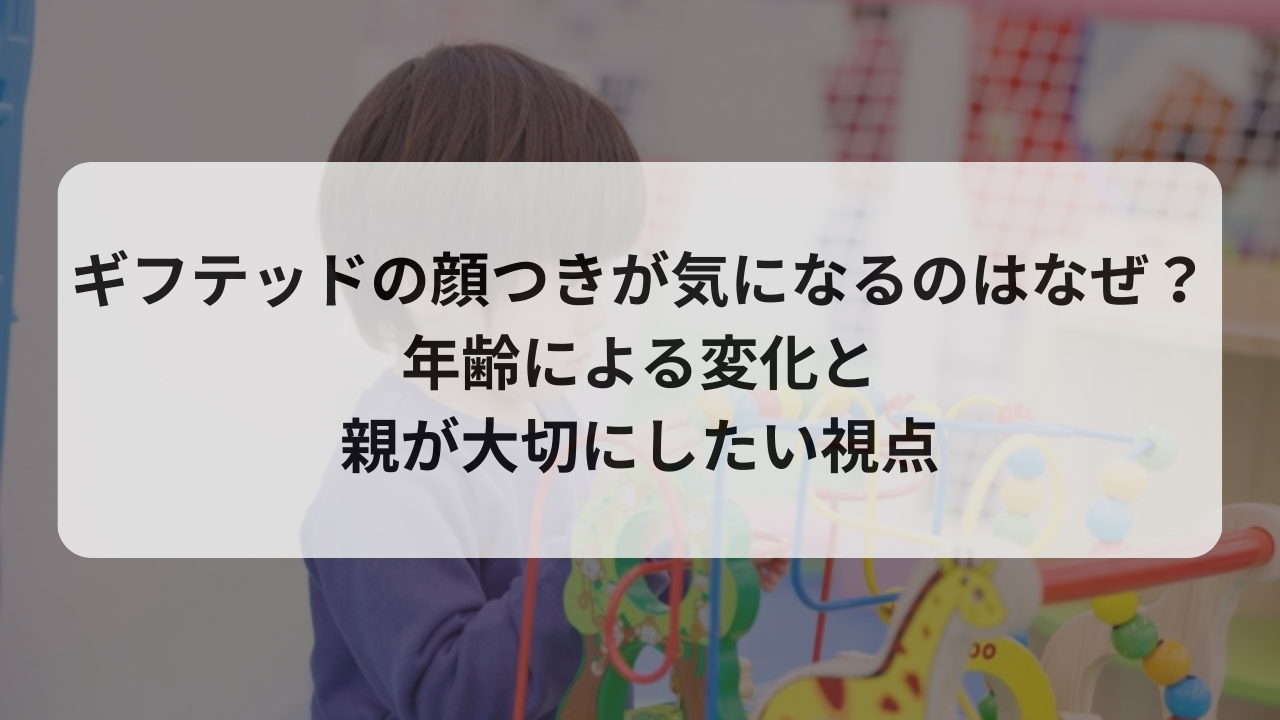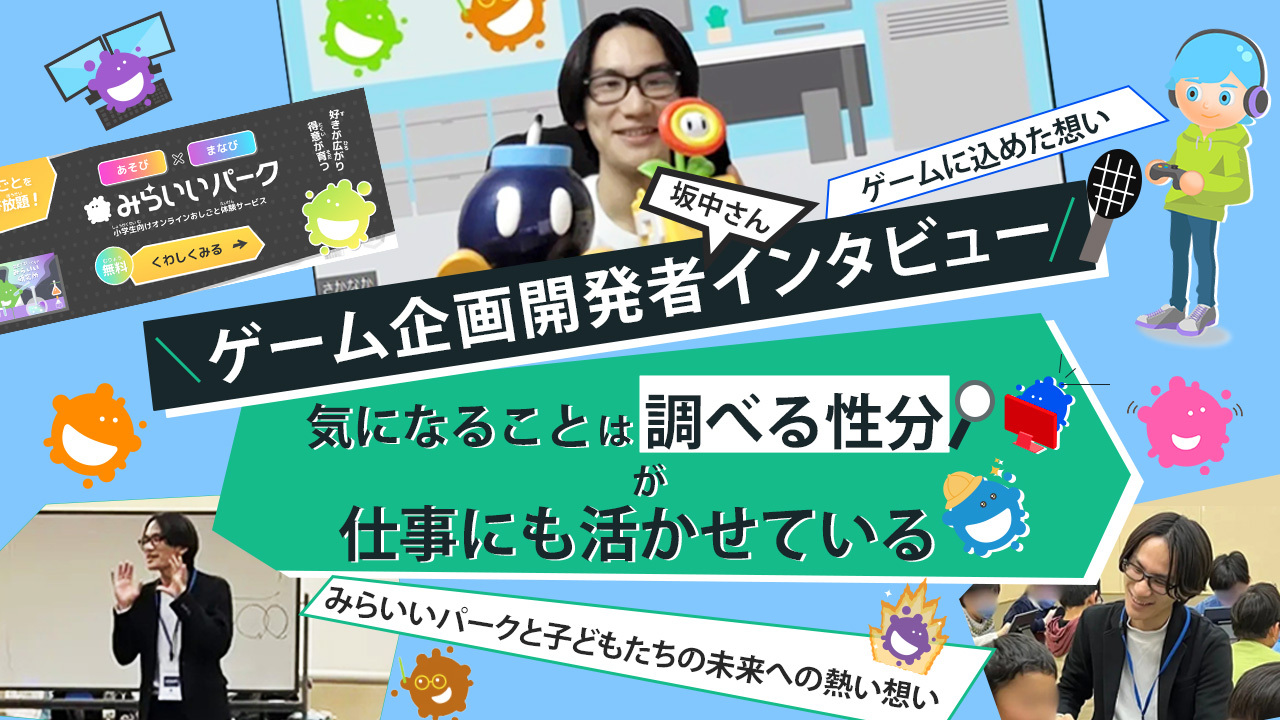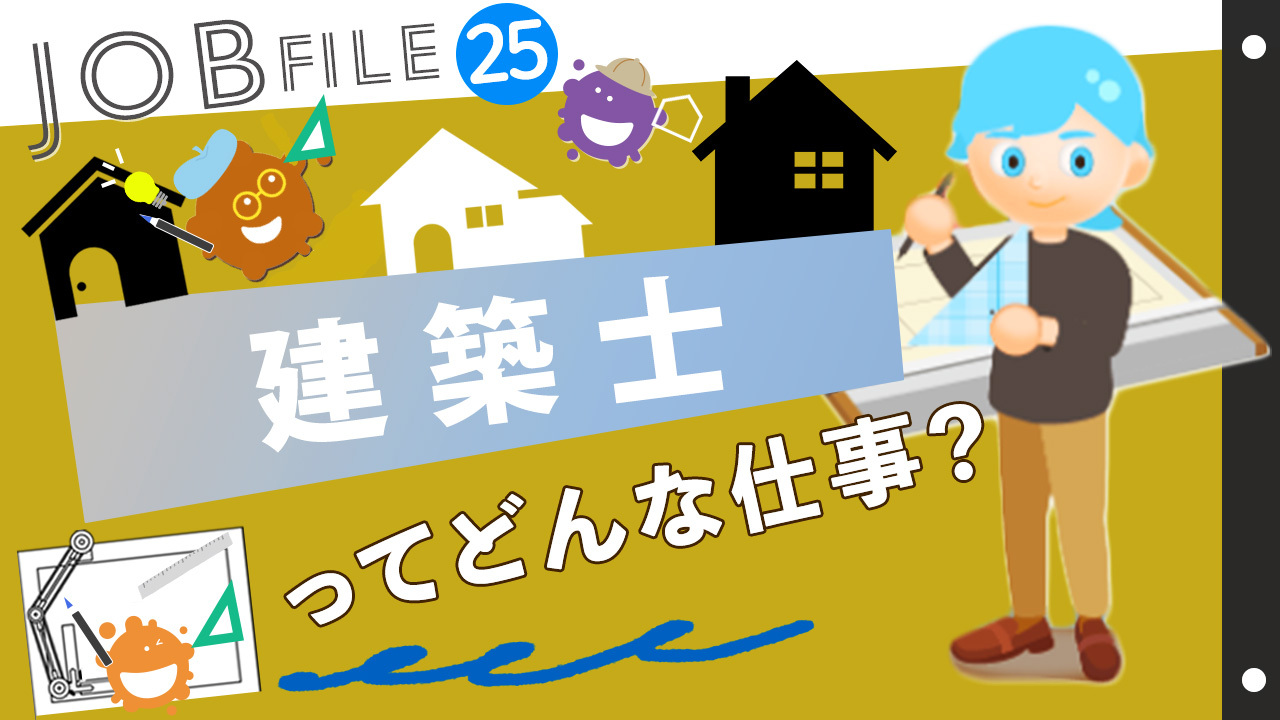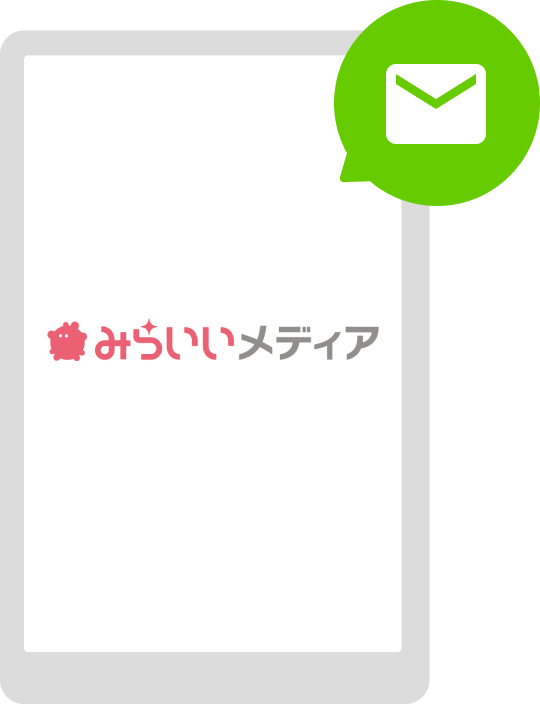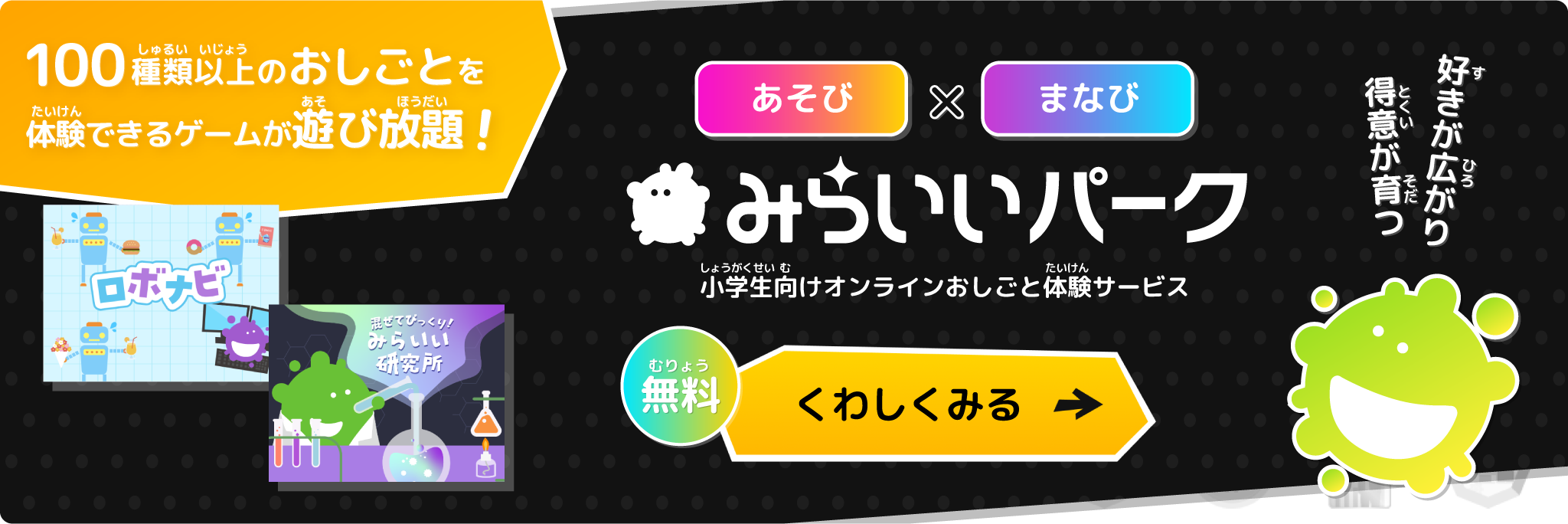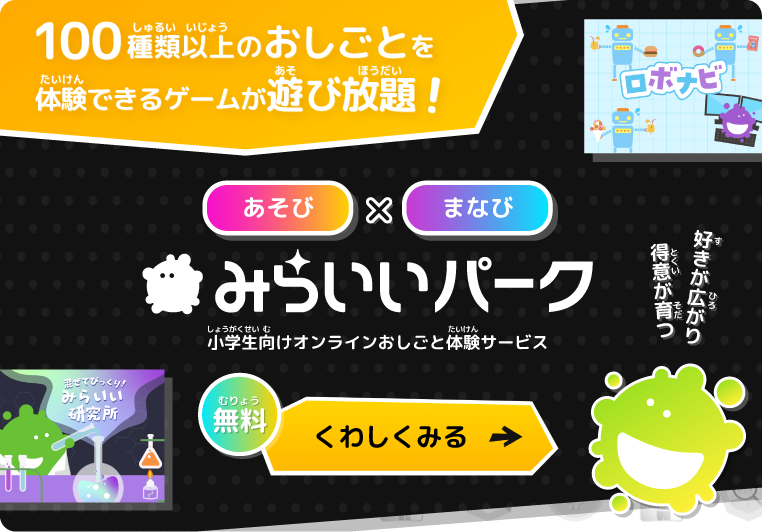SDGs6「安全な水とトイレを世界中に」とは?世界の現状と私たちにできること

毎日当たり前に使っている水道。蛇口をひねれば、きれいで安全な水がいつでも出てきます。実は、世界には安全な水を飲めない人たちがたくさんいるのを知っていますか?
SDGsの6番目の目標「安全な水とトイレを世界中に」は、そんな世界の水の問題を解決するために作られました。この記事では、水の大切さや世界の現状、私たちにできることをわかりやすく解説していきます。
動画でも3分で解説しておりますので、ぜひご覧ください!
SDGs6ってなに?目標の意味をわかりやすく解説

SDGs6は「安全な水とトイレを世界中に」という目標です。日本では、安全な水を飲み、綺麗なトイレが使える人の割合が99.9%(2022年時点)という結果が出ています。一見達成されていると思えるような、この目標がなぜ必要なのでしょうか?世界と比べた日本の現状や課題も解説します。詳しく見ていきましょう。
どうして「水とトイレ」が世界の問題なの?
私たち日本人にとって、きれいな水を飲んだり、清潔なトイレを使ったりすることは当たり前のことです。しかし、世界を見回すと、そうではない人たちがたくさんいます。世界では、
- 約22億人の人が、家で安全な水を飲めません
- 約34億人の人が、安全で清潔なトイレを使えません
- 毎日800人以上の子どもたちが、汚れた水が原因で病気になって亡くなっています
出典:https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_act01_03_water.html
https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_act01_03_sanitation.html
http://www.unic.or.jp/files/54c38330d412f4b7ccafd086511476f8-1.pdf
これは、世界中の人口の約3分の1にあたる大きな数字です。安全な水がないと、私たち人間は生きられません。だからこそ「水とトイレ」は世界みんなで解決しなければならない大切な問題なのです。
「安全な水」ってどんな水?「安全ではない水」って?
「安全な水」とは、
- 病気の原因になる細菌やウイルスが入っていない水
- 有害な化学物質が混じっていない水
- いつでも必要な時に手に入る水
を指します。日本の水道水は、厳しい基準をクリアした安全な水です。
「安全ではない水」とは、
- 汚れた川や池からそのまま使う水
- 動物のふんや生活排水が混じった水
- 工場から出た有害な物質が流れ込んだ水
を指します。このような水を飲むと、お腹を壊したり、重い病気になったりしてしまいます。特に体の小さい子どもたちは、命に関わる場合もあるのです。
SDGs6が目指すゴール
SDGs6では、2030年までに達成したい具体的な目標を決めています。「6-1」のように数字で示されるものは、それぞれの項目の達成目標を示しており、「6-a」のようにアルファベットで示されるものは、実現のための方法を示しています。
- 6.1すべての人が安全で安い水を平等に使えるようにする
- 6.2すべての人が清潔なトイレを平等に使えるようにし、外での排泄をなくす
- 6.3汚染を減らし、有害な物質の放出を最小限に抑える
- 6.4水を効率的に使い、水不足を解決する
- 6.5国を越えて協力し、水資源を総合的に管理する
- 6.6山、森、湿地、川、帯水層、湖などの水に関係する生態系を保護・回復する
- 6.a途上国の水と衛生の活動やプログラムへの国際協力を拡大する
- 6.b水と衛生の管理の改善において地域コミュニティの参加を支援・強化する
世界の現状|いまだに安全な水が飲めない人たち

世界には、今でも安全な水が飲めない人たちがたくさんいます。どれくらいの人が困っているのか、なぜそんなことが起きているのかを見てみましょう。
世界ではどれくらいの人が困っている?
世界の水の問題は、想像以上に深刻です。
- 安心して飲める水がない人:約22億人
- 家にトイレがない人:約34億人
- 自宅に手を洗う設備がない人:約20億人
- 汚れた水が原因で病気になる人:年間約140万人
出典:https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_act01_03_water.html
https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_act01_03_sanitation.html
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/wash-documents/jmp-2023_layout_v3launch_5july_low-reswhowebsite.pdf?sfvrsn=c52136f5_3&download=true
https://www.unicef.or.jp/news/2023/0112.html
これは、世界の人口が80億人と考えると、4人に1人は安全な水を飲めず、2人に1人は安全なトイレを使えずに生活していることになります。
水道やトイレが使えないとどうなるの?
安全な水やきれいなトイレが使えないと、どんなことが起きるのでしょうか?汚れた水を飲んでしまうと、下痢や感染症にかかってしまったり、手を洗えないため、病気が広がりやすかったりします。下痢が改善しなければ、栄養失調になりやすく、最悪の場合、命を失うこともあるのです。
また、上下水道が整備されていない場所では、水を汲みに行くのは子どもの仕事です。毎日何時間もかけて水を汲みに行くことで、子どもたちが学校に行けなくなるという問題もあります。
どうして水が足りない国があるの?
日本は水に恵まれている国ですが、世界的には水不足が起きている国が多く存在しています。その原因も一つではなく、いくつかの要因が複雑に絡まっていることがほとんどです。
まず、水不足に大きく関係するのが地域や気候です。雨がほとんど降らない地域(サハラ砂漠周辺など)があったり、干ばつ(1年以上雨が降らないこと)が続く国もあったりします。温暖化の気候変動による降水パターンの変化も水不足の要因として挙げられます。
また、お金や技術の問題もあります。水道管や浄水場を作るお金が足りない、設備を作ってもそれを動かす電力がない、機械を修理できる技術者やそれを受け継ぐ人がいないなどさまざまなものが足りないのです。
戦争や政治が要因となっている地域もあります。戦争で設備が壊されてしまったり、政治的に不安定なため、大きな設備を作る長期的な計画が立てられなかったり。他にも、汚職により水道工事のお金が別のことに使われてしまう場合もあります。特にアフリカやアジアの一部では、これらの問題が重なって、水不足がより深刻になっています。
日本の水事情|世界から見てどう違う?

日本は世界から見ると、とても水に恵まれた国です。でも、それが当たり前だと思っていませんか?世界視点で見た日本の立ち位置も確認していきましょう。
日本は水に恵まれている国
日本の年間降水量は世界平均の約2倍(日本の平均:約1,700mm、世界の平均:約880mm)です。また、山が多く、雨水が川に流れやすい地形であることや、四季があり、雪解け水も豊富なことも安全な水の確保につながっています。
また、設備面では、高い技術で水をきれいにする浄水場が全国にたくさんあり、水道普及率が99.9%以上で、ほぼ全ての家に水道が通っています。蛇口をひねれば安全な水がすぐに出るだけでなく、下水道も整備されていて、使った水もきちんと処理されるのです。何十億人という人が水を使えない中、これだけ安全な水の循環が確立されているのは、とても恵まれた状況といえるでしょう。
日本の課題「バーチャルウォーター」とは?
このように安全な水の循環が確立されているにも関わらず、日本にも課題があるとされています。それは「バーチャルウォーター」と呼ばれるものです。バーチャルウォーターとは、農産物や工業製品を生産する際に使用された水の総量を指します。日本は食料や衣類、工業製品など多くを海外から輸入しており、その生産地が水不足地域である場合、間接的に他国の貴重な水資源を消費していることになります。
特に畜産物や穀物など水を多く必要とする商品は影響が大きく、日本は1人当たり年間約1,800m³のバーチャルウォーターを輸入しています。これは国内の水問題だけでなく、国際的な水資源の持続性にも関わるため、輸入先の多様化や消費行動の見直しが求められています。
世界では「安全な水」を使えない人もいる

水に関する問題において、日本では当たり前のことが、世界では当たり前ではありません。このギャップを知って自分には何ができるかを考えて行動に繋げましょう。
水があるからこそ見落としがちな“当たり前❞
世界とのギャップを知るために、私たちの普段の行動を振り返ってみましょう
- 朝起きて顔を洗う:顔を洗うきれいな水がない人が世界の全人口の25%います
- 歯磨きをする: 歯磨きに使える安全な水がない人は世界の全人口の25%です
- お風呂に入る: お風呂に入れるほどの安全な水を大量に毎日使える地域はとても限られています
- トイレを使う:水洗トイレを使えない人が世界には23億人います
日本で何気なくしている水に関する行動の多くが、世界の人にとっては当たり前ではないのです。また、生活排水がどこに行くかも大切です。私たちが使った水は下水処理場できれいになってから川に戻されますが、そのような設備がない国では、汚れた水がそのまま川や海に流れてしまいます。地震や台風で断水になったとき、水の大切さを実感した人も多いでしょう。世界には、毎日がその「断水状態」で生活している人がいるのです。
日本にも水問題はある?
明治時代後期から昭和初期にかけては、日本の農村地域で水をめぐる争いが起きたこともありました。しかし、上下水道を整備したり、ダム建設を進めたりするなど、水問題を解決するために多くの人が行動してきました。
そして現在も、全く問題がないわけではありません。災害時は多くの人が水不足に陥る可能性は残されています。たとえば、豪雨で浄水場が壊れ、水が使えなくなることがあります。地震で水道管が破裂し、復旧に時間がかかった事例もあります。
また、気候変動による問題も挙げられます。異常気象で夏の暑さが厳しくなり、水の需要が増えたり、雨の降り方が変わって渇水になる地域もあったりします。普段から限りある資源として水を大切に使うことで、将来起こりうる水不足の予防につながるのです。
SDGs6の取り組み事例【国内・海外】

SDGs6の目標達成のために、世界中でいろいろな取り組みが行われています。どんな活動があるのか見てみましょう。
日本企業・自治体の水資源保護プロジェクト
日本コカ・コーラでは、「い・ろ・は・す」を通じて水の循環を大切にする取り組みを続けています。製品の売上の一部を使って、全国各地の水源を守る森林保護活動を支援しています。現在は終了していますが、2024年には「もり森そだつ」という新しいキャンペーンを始め、ゲームを楽しみながら森林保護について学べる仕組みを作りました。
LIXIL株式会社では、途上国向けの簡易式トイレシステム「SATO」を開発し、現在までに約860万台を45カ国に出荷、約6,800万人の衛生環境改善に貢献しています(2024年3月31日時点)。2024年には新たにフィリピンとインドネシアでも事業を開始し、現地での生産・雇用も生み出しています。
横浜市では、雨水タンクを設置する家庭に助成金を出しています。100リットル以上のタンクを設置すると、購入費の半額(最大2万円)がもらえます。この取り組みにより、各家庭で雨水を有効活用できたり、災害時の備蓄水としても役立てることが可能です。 また、川への雨水流出を減らし、豪雨時などの洪水防止にも貢献できます。
熊本市は水道水を100%地下水でまかなう「日本一の地下水都市」です。くまもと地下水財団を中心に、市民が参加できる地下水保全活動を実施しています。SNSを使った水の大切さを伝えるキャンペーンや企業と連携した地下水涵養(水を地下に浸透させる)事業を展開し、貴重な地下水を次世代に引き継いでいます。
海外のNPO・国際機関の活動(例:UNICEFやWaterAidなど)
UNICEF(ユニセフ)は、世界中の子どもたちのために安全な水とトイレを届ける活動をしています。緊急時に給水車を派遣したり、学校でのトイレ建設、手洗い設備の設置と衛生教育などを進めています。
WaterAid(ウォーターエイド)とは、アフリカやアジアで活動している、イギリスを拠点とする国際NGOです。井戸や給水設備の建設、地域住民への技術指導だけでなく、政策提言活動など国の中核にも助言をしながら水不足に取り組んでいます。
子どもたちも参加できる水を守るキャンペーン
子どもたちが参加でき、多くの学校や地域で行われている取り組みが、ペットボトルキャップ回収活動です。キャップを集めてリサイクル業者に売り、その利益でワクチンを購入します。この活動は、間接的に途上国の子どもたちの健康を支援することができます。
また、毎年8月1日は「水の日」というのを知っていますか?この日に合わせて、全国で様々なイベントが開催されます。浄水場見学会や、水の大切さを学ぶワークショップ、節水グッズの配布などがあるので、地域で取り組んでいる活動がないか調べてみましょう。
SDGs6で私たちにできること【小学生・家庭向け】

水が身近な日本に住む私たちだからこそできることがあります。世界の水問題を解決するために、まずは、小さな取り組みから始めてみましょう。
水道の出しっぱなしをやめる/節水シャワーを使用する
水の出しっぱなしをしないように注意するだけで、たくさんの水の節水ができます。たとえば、シャワーの出しっぱなしをやめると、1分間で約12リットルの節約になります。湯船に使ったお湯は、洗濯や庭の水やりに再利用可能です。また、食器などの洗い物をするときは、水を溜めるようにしてみましょう。桶にためた水と洗剤で洗えば水道からの水で流すのはすすぐときだけでよくなります。野菜も桶に溜めて洗い、使った水は植物の水やりに使うと無駄なくお水を使えます。
シャワーヘッドを変えると約30〜50%の節水が可能です。シャワーヘッドは、空気混合などで水圧を感じやすくし、水の勢いを保ちながら使用量を減らせます。水の使用量を減らすことは、水道代やガス代の節約にもつながります。
油をシンクに流さない/排水をきれいに保つ
調理で使った油をそのまま流すと、排水溝が詰まったり、下水処理の際に負担がかかったりします。油をなるべく流さないようにするためには、揚げ油を捨てずに炒め物に使ってみましょう。捨てる場合は、固める粉を使ったり、新聞紙に油を吸収させたりしてから燃えるゴミに出します。炒め物をしたときの少量の油も、キッチンペーパーで油を拭き取ってから洗うとよりよいですね。
環境配慮型の洗剤やせっけんを選ぶ
環境にやさしい洗剤の使用も家庭でできることです。環境に配慮した洗剤の特徴は、
- 生分解性が高い(自然の中で分解されやすい)
- リンや蛍光増白剤を使っていない
- 植物由来の成分でできている
です。
また、掃除に重曹やクエン酸を使う、せっけんを基本にした製品を選ぶ、洗剤の使用量を守るなども環境に配慮した行動です。
洗剤やせっけんを買う時にも、水への問題に向けた取り組みが可能です。環境への負荷が少ないと認められた商品につけられるエコマークのついた商品を選んだり、詰め替え用を使ってプラスチック削減に参加したりしましょう。洗剤は適量を使い、泡を使いすぎないようにすると排水を綺麗に保てます。
NPO団体に寄付したり募金キャンペーンを知る
世界では、安全な水を利用できない人が総人口の約25%、適切なトイレを使えない人が約50%います。こうした状況を改善するため、多くのNPOや国際機関が井戸の設置や水質改善プロジェクトを行っています。私たちができることの一つは、寄付や募金を通じてこうした活動を支援することです。少額でも継続すれば大きな力となり、現地での井戸建設や衛生教育に役立ちます。まずは信頼できる団体を調べ、どのような活動に使われるのかを知ることから始めましょう。
世界100か国以上で、安全な水や衛生教育(WASH)を提供しています。学校や地域に手洗い設備を設置したり、災害時の水供給を支援しています。
清潔な水を世界中のコミュニティに届ける活動をしている非営利団体です。寄付金の100%が現地のプロジェクトに使われ、GPSや写真で成果を確認できます。
家庭や地域に水道や衛生設備を整備できるよう、お金を借りやすくする仕組みを提供している。現在までに7,900万人以上が恩恵を受けています。
自由研究・クイズで“水問題”を学ぼう!
数字やニュースを読むだけでは、水不足を実感するのはなかなか難しいものです。そこで、夏休みの自由研究で取り上げたり、クイズ形式で学んだりすることもおすすめです。たとえば、自分の家で1日に使う水の量を計測する、世界各国の水事情を地図にまとめるなどすると理解が深まります。また、家族や友達と水問題クイズを出し合えば、楽しく知識を共有できます。
水を大切にすることは、命を守ること

水は私たちの命を支える大切な資源です。その大切な資源をみんなで守っていくために、今日から実践できることを確認しましょう。
家庭でできることを1つ行動に移そう
まずは無理をせず、何か1つ始めてみましょう。今日からできる簡単なことは、
- 歯磨きの時に水を止める
- お風呂の残り湯で洗濯する
- 食器を洗う前に油汚れを拭き取る
などです。これらに慣れてきたら、もう少し長い期間取り組めないか考えてみましょう。
- 家族で節水目標を決めて振り返る
- 環境にやさしい洗剤に変えてみる
- 家庭の水使用量をチェックする
- 地域の水に関するイベントに参加する
など、私たちができることはたくさんあります。
「きれいな水があるのが当たり前」ではない世界を知る
私たちにとって当たり前の「安全な水」は、実は世界では当たり前ではありませんでしたね。世界では、安全な水を利用できない人が約25%いるという現状を忘れないようにしましょう。。
これからも私たちが心がけていきたいのは、水を使うときに「ありがたい」という気持ちを持つことです。SDGs6「安全な水とトイレを世界中に」の達成には、まだ時間がかかります。しかし、私たち一人ひとりの意識と行動が、必ず世界を変える力になります。今日の学びを家族や友だちにも伝えて、みんなで水を大切にする輪を広げていきましょう。

%20(1).jpg)










%20(1).jpg)