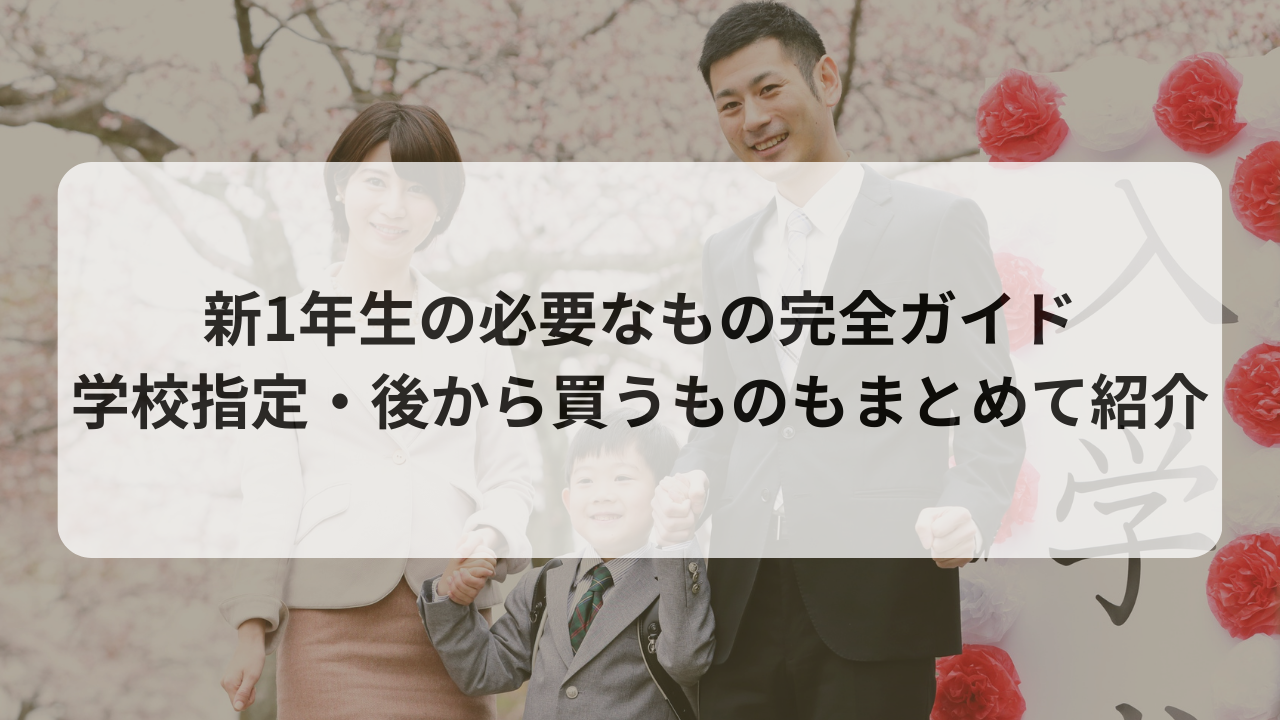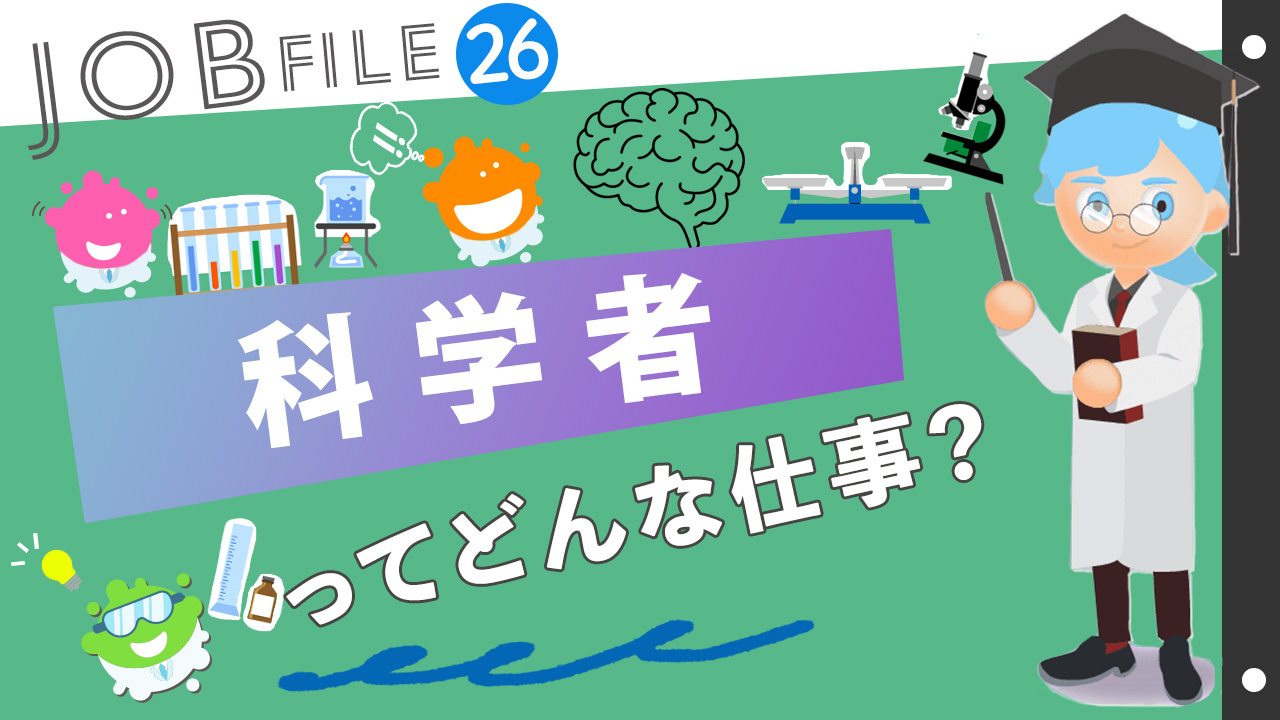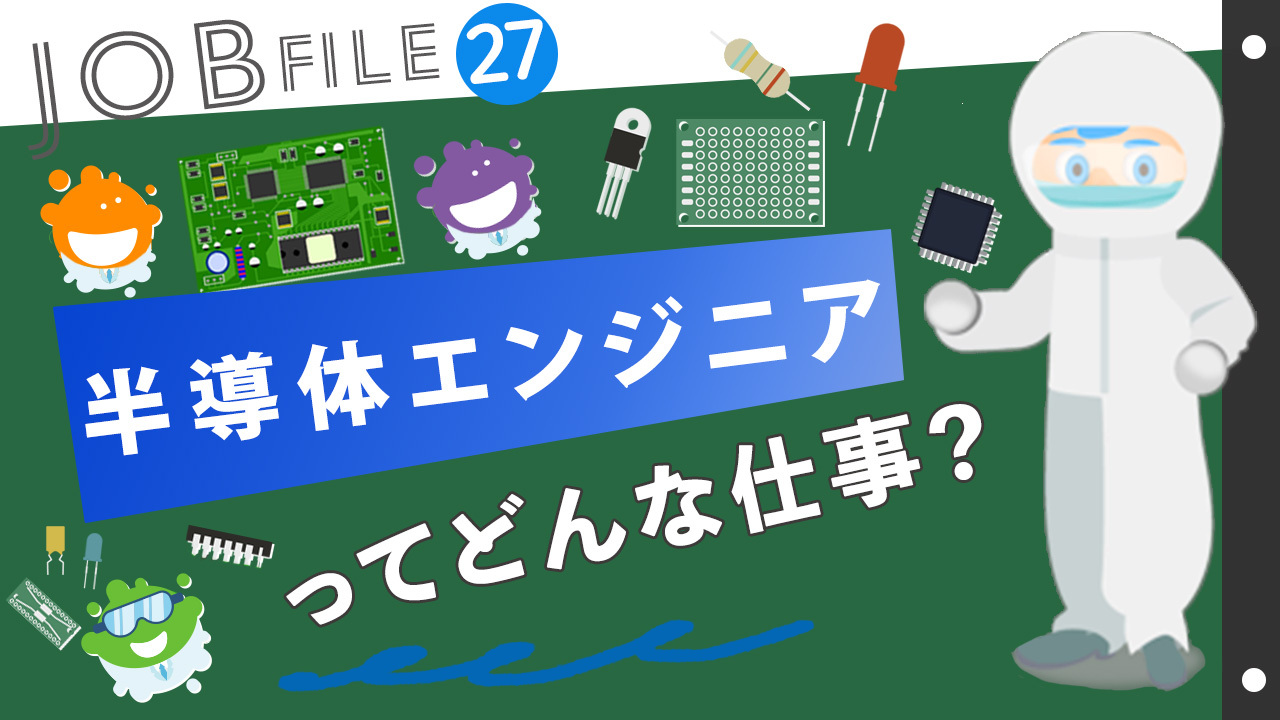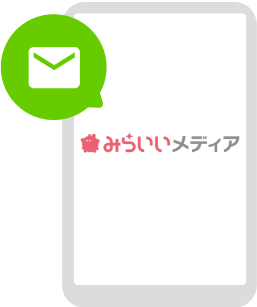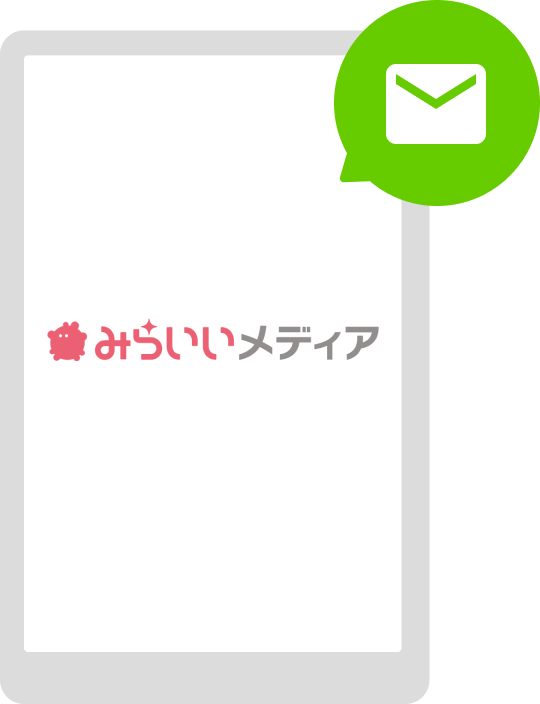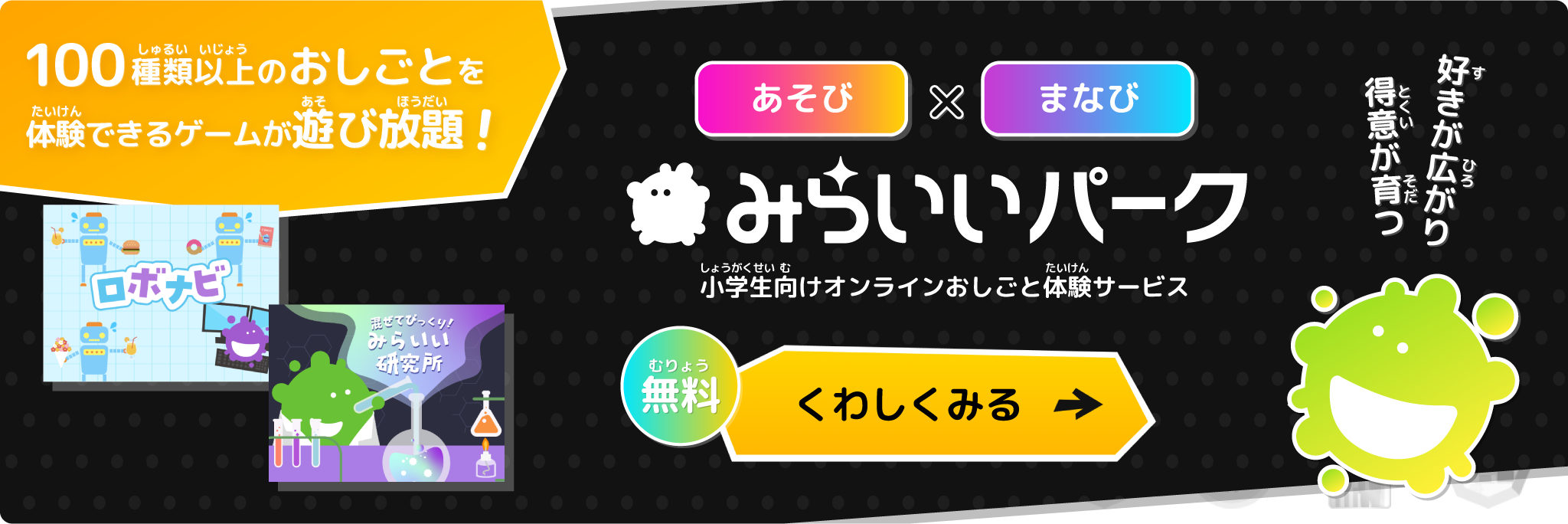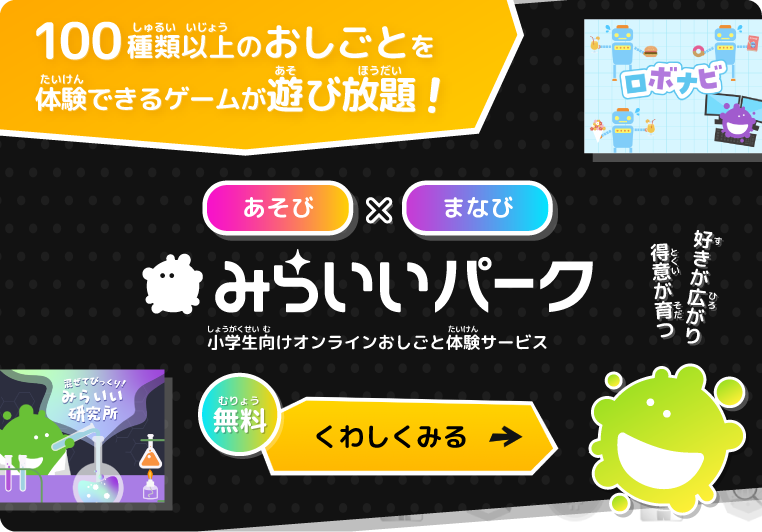【小学生のためのSDGs解説】それぞれの目標を親子で学ぼう

今の時代、SDGsという言葉を耳にしたことがあるという人も多くいるでしょう。
しかし、いざ小学生の子どもと一緒に取り組んでみたいと思っていても、何だか難しそうと感じてしまいますよね。
ここでは、SDGsについての基礎知識や取り組み事例などに加え、目標ごとに簡単な解説も設けました。ぜひ親子で一緒に、それぞれの目標について学んでいきましょう!
SDGs(エスディージーズ)とは何?

SDGsの基礎知識をまとめました。まずは、正確な知識を身に付けていきましょう。
SDGsってどんな言葉?正式な意味と読み方
SDGs(エスディージーズ)は、「Sustainable Development Goals」(サステナブル・ディベロップメント・ゴールズ)の呼称。日本語に訳すると、「持続可能な開発目標」という意味です。
世界中の人が誰一人取り残されることなく安全に生活できるよう、環境問題の解決・改善策も含め、17の目標とターゲットが設定されています。
どうしてSDGsが注目されているの?
SDGsが注目されている理由として、地球温暖化や海洋汚染、プラスチックごみの増加などの環境問題、貧富や教育の格差拡大、ジェンダー差別などの社会問題に対し、国の危機感が高まっていることが挙げられるでしょう。
こういった問題が進めば、地球環境は悪化の一途をたどり、いずれは生物が生存できなくなる恐れがあります。解決できないことには、地球上の生物の生命が守られることはありません。
さらに、多様性のある平和な社会を実現するため、ジェンダー差別や貧困・教育の格差拡大をなくす必要もあります。
そのほか、日本経済団体連合会(経団連)によって企業行動憲章が改定されたことも、SDGsが注目されるようになった理由と言えるでしょう。
ーー企業行動憲章とは、企業が社会の一員として守るべきルールや取り組み方針をまとめたもの。
つまり、大手企業をはじめとする多くの会社が「自分たちの事業を通してSDGsの目標達成に貢献する」という方針を正式に掲げたのです。この動きにより、企業だけでなくメディアや学校、家庭でもSDGsへの関心が広がっていきました。
誰がSDGsを決めたの?国連の動き
SDGsは、2015年9月、ニューヨークで193の加盟国が参加する国連サミットで採択され、17の目標とターゲットが決められました。それらが決定するまで、1,500以上の企業や団体、世界の1,000万人の人などの意見が取り入れられたようです。
したがって、SDGsは国連サミットに参加した加盟国が決めたものと言えるでしょう。
参照元:さすてらす公式、東京保健生活協同組合公式
SDGsの17の目標をわかりやすく解説!【子ども向け】

先述したように、SDGsには17の目標が設けられました。
17の目標は5つのカテゴリーに分けられ、その頭文字をとり、「5つのP」と呼ばれています。
- People(人間):人が人らしく生きていくため、確実に保証されなければならない項目
- Prosperity(豊かさ):経済的な豊かさや、技術産業、インフラなどについての項目
- Planet(地球):自然環境についての項目
- Peace(平和):戦争や暴力や不正のない世界を実現するための項目
- Partnership(パートナーシップ):目標を実現させるために、みんなが協力していくための項目
目標1:貧困を終わらせる
【世界の子どもの6人に1人が極度の貧困で暮らしています】
貧困とは、食料や飲料水、住居、教育、仕事といった基本的な物やサービスを、お金がなくて手に入れられない状態を指します。極度の貧困状態ですと、最低限の食糧が手に入らず、生きることが難しくなってきます。
全世界の6人に1人(約3億5,600万人)が、極度の貧困状態におかれている状態です。
こうした原因の一つが、教育を受けられないこと。たとえば、文字が読めない、計算ができない。適切な知識がないと仕事に就くことも難しくなってしまい、子ども世代へと貧困の連鎖が生まれてしまうでしょう。
参照元:ユニセフ
目標2:飢餓をゼロにする
【飢餓って何だろう?】
世界では、7人に1人(約9億2,500万人)が飢餓状態です。飢餓状態が長期間続くと、体や脳の働きが弱くなってしまうため、活動することが困難な状態になってしまいます。
飢餓により免疫力が弱ってしまった子どもは、下痢やはしかなどで命を落としてしまう危険があります。飢餓の原因は、自然災害や紛争、経済危機、慢性的な貧困などさまざま。簡単に解決できる問題ではないと言われています。
参照元:WFP
目標3:すべての人が健康的な生活を送れるように
【病気になっても安心して治療が受けられるように】
新型コロナウイルスによる世界の死者数は、500万人を超えてしまいました。特に、医療機関は大きな影響を受けましたが、医療機関や福祉は目標3に大きく関わっています。
目標3の中には、妊娠出産に関わる死亡率を下げる、マラリア・結核・エイズといった伝染病を根絶させる、新生児と5歳未満の死亡をなくすなど、早期に解決が必要な問題が多く含まれています。
目標4:すべての子どもが質の高い教育を受けられる
【大人の都合で学校に行けない子どもがいます】
その理由は、国や地域によってもさまざまです。
たとえば、戦争や教員不足という理由が挙げられるでしょう。学費が払えない、働かなければならないという理由もあります。
開発途上国においては、識字率(読み書きできる人の割合)が50%を下回っている国も多くあります。
いずれにしても、社会や大人の事情によって、子どもが教育を受けられない状況は避けるべき課題です。
目標5:ジェンダーの平等を実現させよう
【「ジェンダー」って何?】
たとえば、「男性」は電車が好き、ズボンをはく、家事はできなくてもいい、戦いが好き。「女性」はピンク色が好き、子どもを育てる、ご飯を作る、おしゃべりが好き。このように、「男女はこうあるのが自然」と、社会の中で作られた性別に対する考え方を指します。
世界には、「女性だから」という理由で学校に行かせてもらえなかったり、無理矢理結婚させられたりという状況に苦しんでいる子どもがいます。「男性だから、女性だから」という考え方を断ち切り、変えていく時代に差し掛かっていると言えるでしょう。
目標6:すべての人が安全な水を使い続けることができる
【家にトイレがない人は世界で6億人以上】
日本では当たり前に使える水道。しかし、世界にはまだ水道設備が整っていない地域が多くあります。飲み水やトイレ、お風呂、料理などに水を使えないうえ、手を洗えないため、感染症のリスクが高まってしまう可能性も。また、外で排せつせざるを得ない人もいます。
健康を守るためにも、すべての人がきれいな水を必要な時に使えることを目標としています。
目標7:地球に優しいエネルギーをみんなが使えるように
【世界では8億人以上が自宅で電気を使えない!】
世界には、電気やガスなどのエネルギーを使えず、不便な生活を送っている人々が多くいます。
快適な暮らしができず、必要な情報も得られず、灯りがなく夜は暗い。
健康を損ねる可能性もあるため、どの地域でも、安くて地球に優しいエネルギーが使えるよう設備を整える必要があるのです。
目標8:経済が成長していけるように 働きがいのある仕事ができるように
【世界には大人の都合で働かされている子どもがいます】
家計を助けなければいけない、災害や紛争が起こっている、などの理由で、教育を受けられずに働かされている子どもたち。
解決は容易ではありませんが、どんな理由であれ、子どもに悪影響のある労働はなくす必要があります。また、男女問わず働きたいと望んでいる人が、しっかり仕事をして稼げることも保証されていなければいけません。
目標9:どの国も産業・技術革新を進めていけるように
【産業が発展していくためにはインフラを整える必要があります】
インフラとは、道路や学校、病院、発電所、水道など、日常生活に必要な施設や設備を指します。世界にはまだまだインフラが整っていない地域があり、不便な生活を強いられている人が多くいます。
産業や経済の発展を実現させるには、インフラを整えることが大前提と言えるでしょう。
目標10:人や国の不平等をなくそう
【差別って何だろう?】
国、地域、人種、宗教、性別、肌の色。人間同士、さまざまな違いがあるのは当たり前です。しかし、「違うから」という理由だけで、個人や集団に対して攻撃したり、傷つけたりなど、人間の尊厳を踏みにじるような行為をすることは差別です。今でも、世界各地で差別によって苦しむ人々がいることを覚えておかなければいけません。
誰しもが安心して暮らしていける世の中になるよう、法律や政策などを通して不平等をなくしていくことが必要です。
目標11:安全で安心して住み続けられる都市づくり
【住み続けたい都市の条件とは何でしょうか?】
交通、自然環境、教育施設、医療施設、公共施設など。これらが整っていることが、住み続けたい都市の条件であると言えるでしょう。
しかし、今でも10億人以上がスラム街に暮らしていたり、大気汚染がひどかったりと、安全や安心が保障されていない環境に暮らす人々がたくさん存在しています。また、災害による死者や被災者数も減らさなければいけません。
目標12:環境にも人にも優しい生産・消費が続けられるように
【つくる人の責任とは? つかう人の責任とは?】
供給されている食料品は、世界中の人々に届いているわけではありません。地球上には食べ物を残す生活ができる人もいれば、ずっと飢えている状態の人もいます。
食べ残しをしない、ものを大切に使うなどを意識し、ごみを削減することが大切です。
目標13:気候変動の影響を減らせるように行動しよう
【地球温暖化はどんどん進行しています】
地球上では、さまざまな要因で発生した二酸化炭素が地球の温度を上げてしまう、いわゆる地球温暖化が起こっています。
気温が上がると、海の温度が上がる。海水の酸性化や異常気象、干ばつ、生き物の生態系の変化など、地球のあらゆる箇所に影響が出てしまいます。
各国が協力しながら、引き続き対策をしていくことが重要と言えるでしょう。
目標14:海の豊かさを守っていこう
【海の生き物を苦しめるプラスチック】
大量のプラスチックごみが海に流れてしまうと、ウミガメや魚がエサと間違えて食べてしまうリスクがあります。また、漁業で使う大きなネットに絡まって死んでしまう生き物も少なくありません。
そのほか、海の二酸化炭素の濃度が高くなる海洋酸性化問題も生じており、プランクトンやサンゴ、貝、エビなどへの悪影響が懸念されます。
目標15:陸に住むすべての生きものを守ろう
【陸地に住む生き物の生態系を守ろう】
地球上の砂漠ではなかった乾燥地帯で、植物が育たなくなったり、農業に適さない土地になってしまったりと、いわゆる砂漠化が進行しています。その原因は、人間活動の影響や気候の変動です。
また、陸地では過剰な森林伐採も深刻になっています。環境が変化したことで、生き物は住みかを奪われてしまうこともあります。最悪の場合、絶滅の恐れが生じるかもしれません。
目標16:みんなが平和に暮らせるようにする
【世界中から犯罪や暴力が無くなるように】
世界では、多くの子どもたちが安心して日々の生活を送れない状況にあります。
日常的に紛争が起こっていたり、暴力の危険にさらされていたり、大人のために働かされていたりと、その理由も実にさまざま。子どもが平和に生きられないということは、決してあってはなりません。
目標16には、子どもへの虐待や暴力を撲滅させることも掲げられています。
目標17:SDGsの目標を達成するために協力しあおう
【みんなで結束して目標を達成させよう】
開発途上国が発展していくためには、多くの資金が必要です。ただ、社会情勢が不安定だったり、貧困層が多かったりと国内で資金を集めることが難しいケースがあります。そのため、先進国からの支援を通じて国の仕組みを構築し、国を発展させなければいけません。
SDGsの目標を実現するには、各国の政府や学者、有識者、企業、個人などが協力する必要があります。私たちも、一人ひとりができることから始めましょう。
身のまわりのSDGs!私たちにできること

では、SDGsを実現するために、私たちにできることは何でしょうか?
ここでは、無理なく生活に取り入れられそうな取り組みをまとめました。できることから少しずつ取り組んでいきましょう。
学校や家庭でできるSDGsアクション
学校では、周りにいる友だちに優しくして、その存在を大切にしましょう。
そんなことがSDGsに繋がるの?と思うかもしれませんが、周りの人を大切にすることも立派な取り組みです。
人間一人ひとりが周りを大切にすることを心がければ、みんなが仲良く暮らせる世の中の実現にぐんと近づきます。地球は、さらに平和な場所になっていくでしょう。
そのほかのアクションとしては、給食を残さず食べて食品ロスを減らす、節水に気を付ける、ペットボトルの蓋を集める、などが挙げられます。また、飲み終わったペットボトルや缶、びんをごみとして捨てるのではなく、リサイクルするように心がけましょう。
お買い物や食事で「エコ」を考える
日々の食事や買い物においても、SDGsを意識して取り組むことが可能です。
たとえば、食べ残しのないようにし、食品ロスを避ける。買い物に行くときはエコバッグを持つ。エコラベルが貼ってある商品を購入する、見切り品を買うなど、さまざまな取り組みが挙げられます。
SDGsを意識した自由研究やポスターづくり
SDGsを意識した自由研究も、SDGsについて楽しく学べるアクションです。
たとえば、家の食品ロスを調べてみる、海に住んでいる生き物やプラスチックごみについて調べる、周りにあるユニバーサルデザインを調べてみる、などのテーマが挙げられるでしょう。自分で調べて研究して、まとめる。このアクションを経て知識が深まり、自分事としてとらえられるようになりますよ。
また、「水を大切に」「電気はこまめに消そう」「食材を無駄なく使おう」などのポスターを作って、家や学校に貼っておくのもよいですね。具体的に視覚化することで、SDGsを常に意識しながら取り組めるはずです。
家庭でできるSDGsへの取り組みは、以下の記事も参考にしてください。
家庭における身近なSDGs事例!
世界や日本のSDGsの取り組み事例【小学生向け】

引用元:WENDY ASIA
ここでは、日本や世界で行われている取り組み事例を紹介します。
日本の町や学校で行われているSDGsの活動
SDGsに対して日本で行われている取り組みは、決して難しいことではありません。
たとえば、地域密着型のお店やスーパーを利用することも、SDGsを実現するための立派な取り組みです。
地元のスーパーでは、地元で採れた野菜を売っています。それを購入すれば、スーパーの売上が伸び、働く人の雇用、農家として働く人の雇用を守ることに繋がるでしょう。
『未来を変える目標SDGsアイデアブック』を活用し、授業でSDGSについて話し合う機会を設けている学校もあります。
授業では、水資源や環境問題、貧困、世界の平和、暮らしやすい社会などについて調べ、自分たちには何ができるかを話し合ったりしているようです。SDGsを自分事としてとらえることができますね。
参照元:『未来を変える目標SDGsアイデアブック』授業での活用事例 小学校編
地域や小学校での取り組み事例については、以下の記事を参考にしてください。
小学校教育でのSDGsの取り組み事例と身につく力
地域におけるSDGsの取り組み事例
世界の子どもたちも取り組んでいる!事例を紹介
インドネシアのバリ島には、The Green School(グリーンスクール)と呼ばれる、竹で造られた学校があり、ここではSDGsに関連した教育を展開しています。ここに通う子どもたちは、環境問題に積極的に取り組み、自らプロジェクトを企画しているそう。
代表的な事例としては、「Bye Bye Plastic Bags(バイバイ・レジ袋)」プロジェクトが挙げられるでしょう。これは、当時10歳と12歳のメラティ、イザベラ姉妹が立ち上げたプロジェクトです。
彼女たちは、グリーンスクールの学びを活かし、何か行動を起こさなければと、バリ島で問題となっていたプラスチックごみについて取り組みました。その結果、プラスチック袋とストローの使用が禁止されることになりました。地域の条例を動かした一例です。
参照元: WENDY ASIA
親子でできる取り組み事例は、以下の記事を参考にしてください。
【最新】SDGs取り組み世界ランキングや親子でできる取り組み事例
企業や団体がどんな取り組みをしているか見てみよう
一例として、石川県金沢市にある会宝産業株式会社の取り組みを見ていきましょう。
会宝産業は自転車のリサイクル事業を展開しており、発展途上国にその技術や知識を提供しています。また、国にリサイクル工場を建設したり、解体ノウハウなども伝えたりして、積極的に雇用を促進しているそうです。
会宝産業の活動は、目標8「働きがいも経済成長も」、目標12「つくる責任・つかう責任」などに貢献。相手国の発展を支えています。
他の企業のSDGsに関する取り組みは、以下の記事を参考にしてください。
【企業の面白いSDGs取り組みレポート】土になるプラスチックに迫る!
SDGsをもっと知って、未来の地球を守ろう

自分にできることを1つずつ実行しよう
SDGs実現のため、私たちにできることは多くあります。
周りの人を大切にする、地域密着型の店舗を利用する、電気はこまめに消すなどのアクションが挙げられるでしょう。SDGsを意識してみると、探せばできることは数多くあるのです。
小さなことでも、たくさんの人が行えば大きな成果につながっていくはずです。まずは、自分にできることを探してみましょう。
おうちの人と一緒に話してみよう
おうちの人と、SDGsについて一緒に話してみるのもおすすめです。
世界には教育を満足に受けられない子どもがいる、戦争が起きている地域があるなど、自分事には何となくとらえられない場合でも、本や動画などを一緒に見て、具体的にイメージすることができるでしょう。
家族でSDGsを共有することで、一緒に取り組むこともできますね。
SDGsについてさらに知識を深め、未来の地球を守っていきましょう。












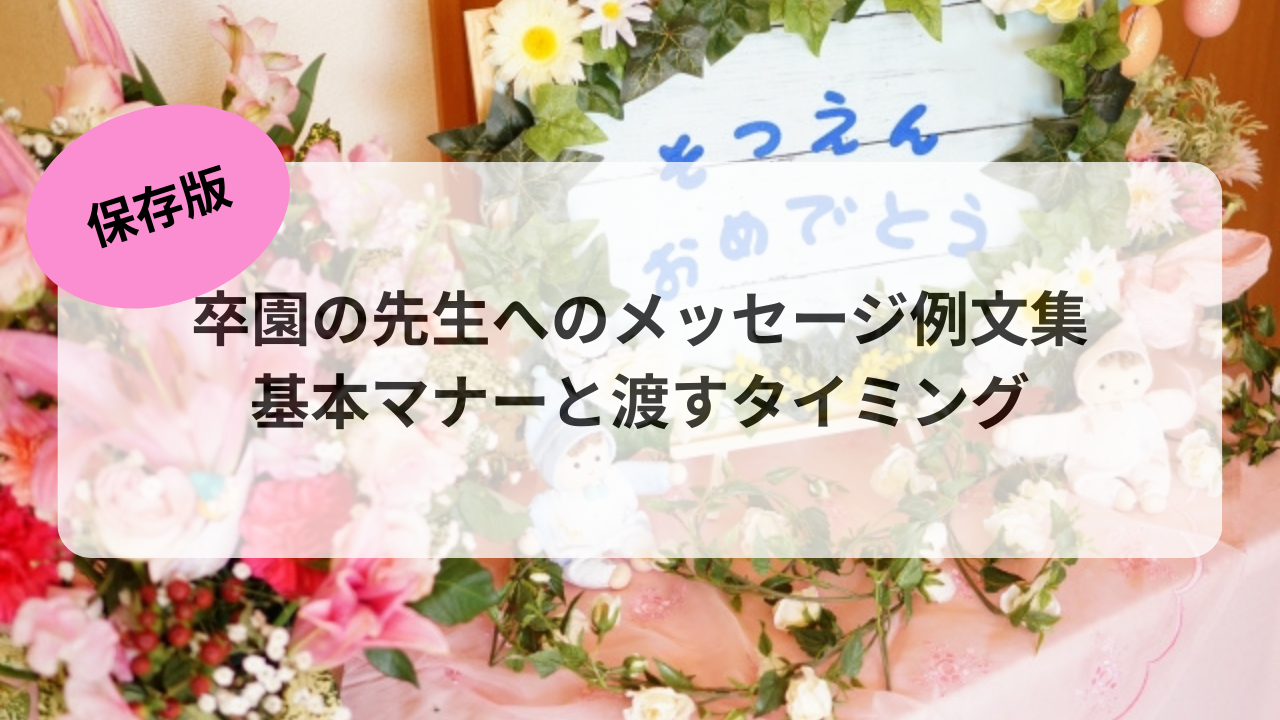
%20(1).jpg)

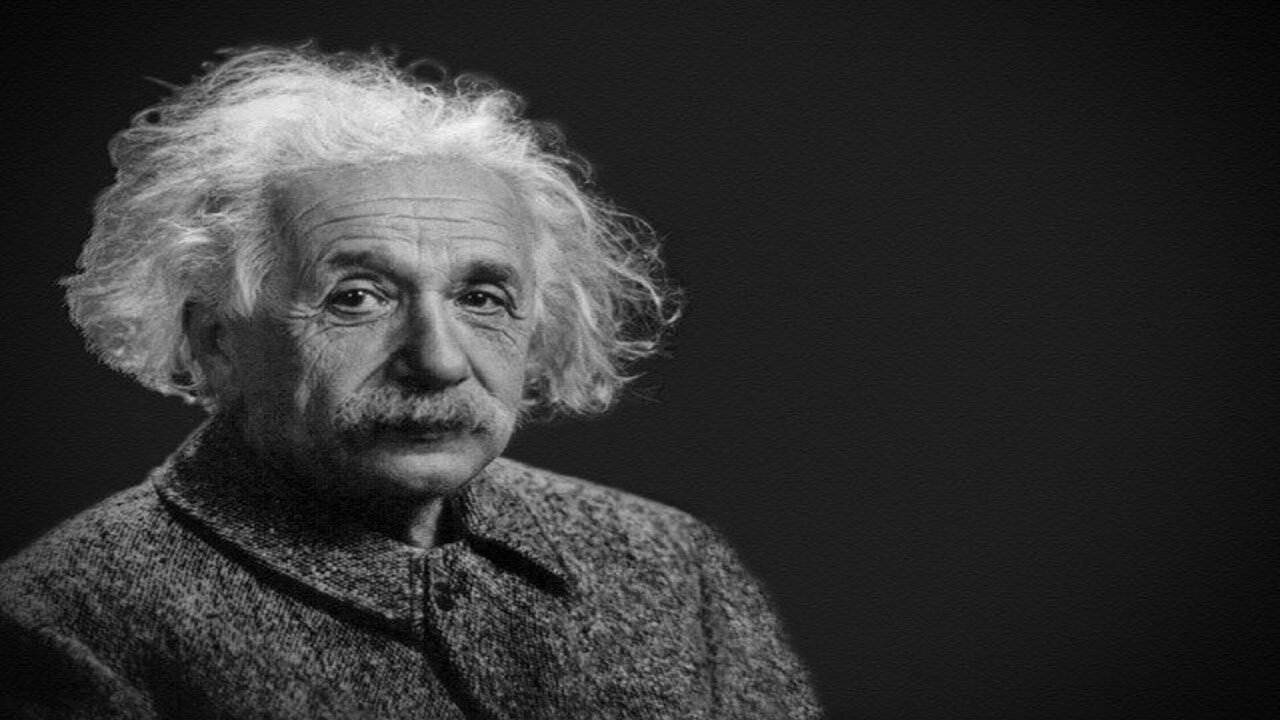
.png)