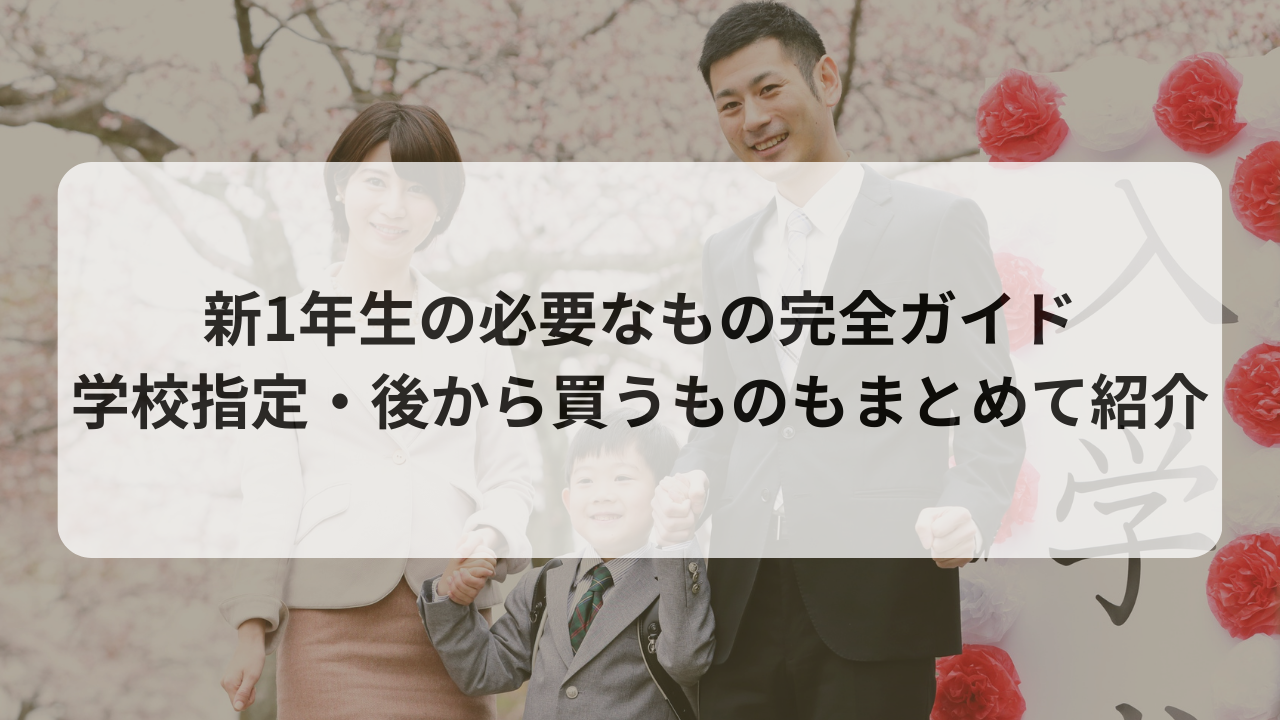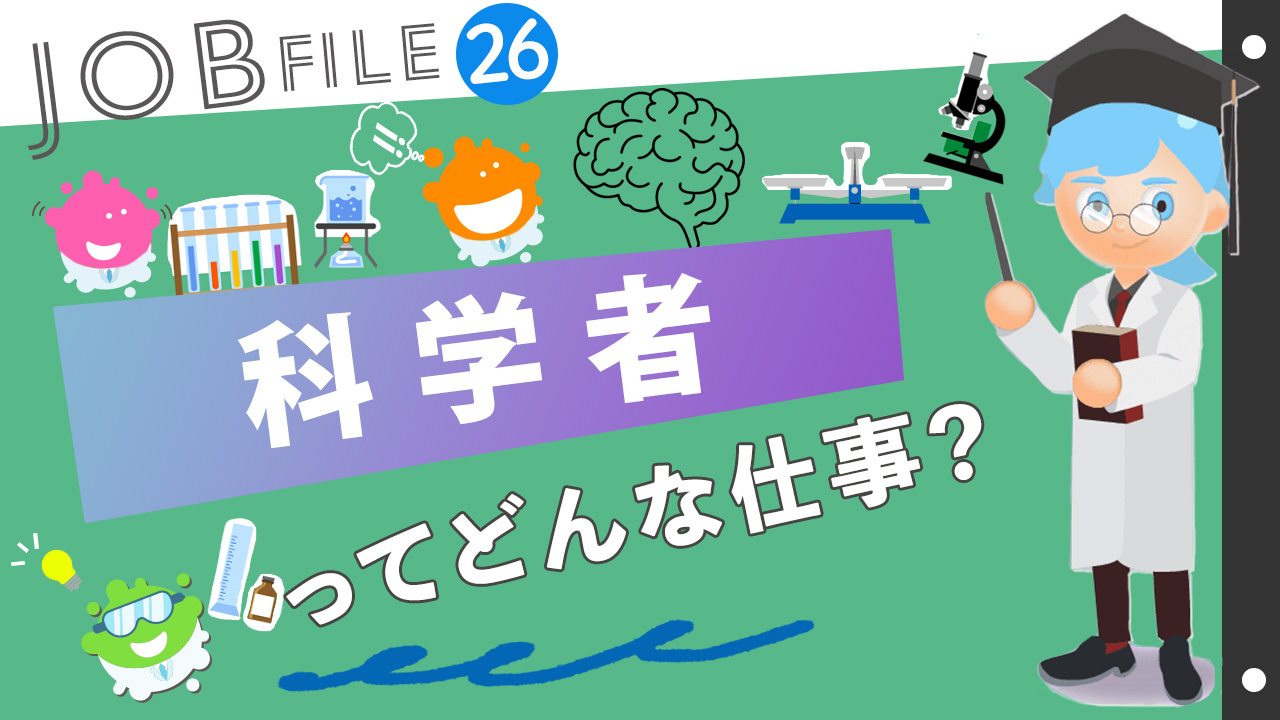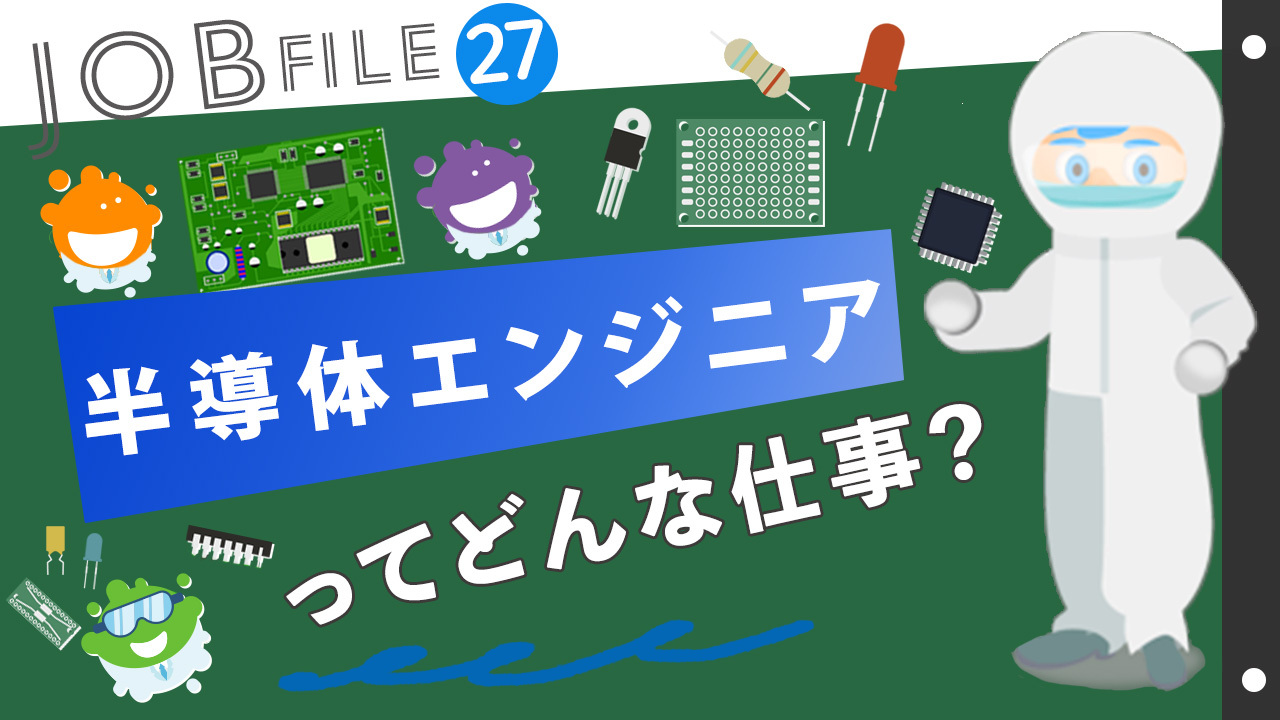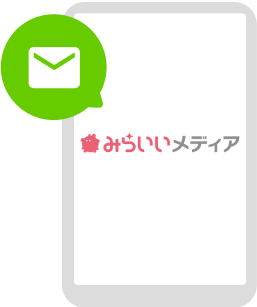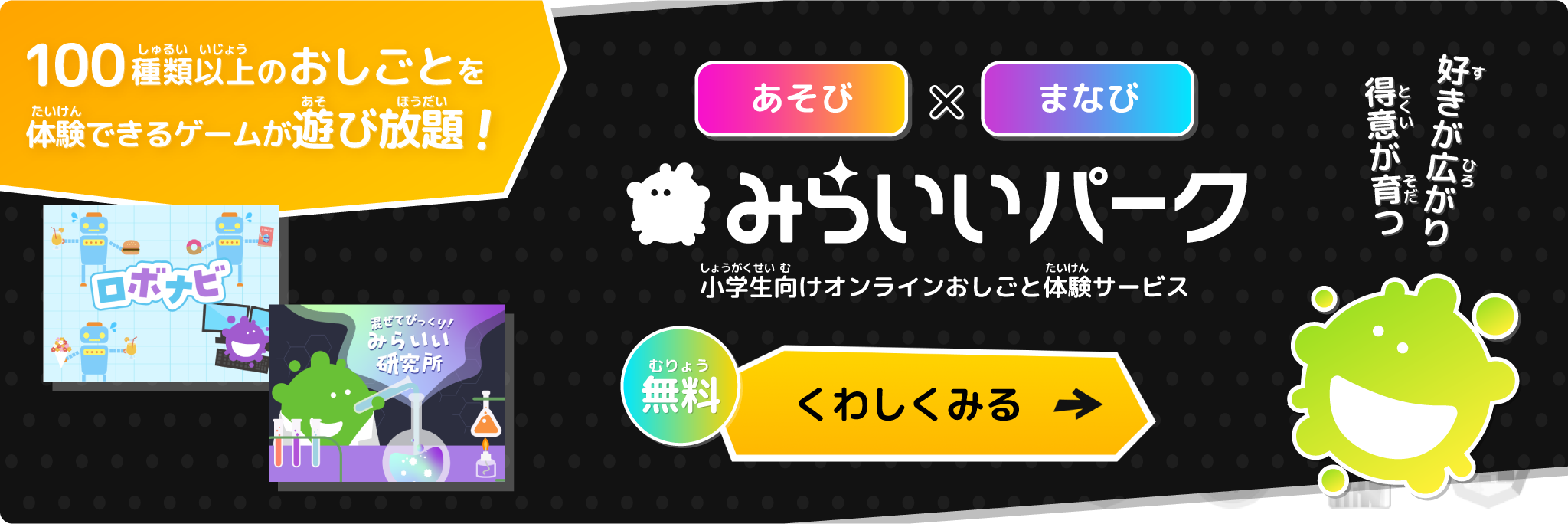SDGs14「海の豊かさを守ろう」とは?現状・課題と家庭でできる取り組み
.png)
SDGs14「海の豊かさを守ろう」は、私たちの暮らしと深く関わる“海”を守るための開発目標です。
現在、海洋汚染や生態系の破壊など、海はさまざまな深刻な問題を抱えています。
私たちが豊かで幸せに暮らせる未来を持続させるためには、課題に向き合うことが必要です。
この記事では、「SDGs14 海の豊かさを守ろう」について、基本的な意味や必要とされている理由、日本や世界の取り組み、さらにお子さまと一緒にできる身近な行動まで、分かりやすくまとめています。
あわせて、3分で分かる解説動画も掲載していますので、ぜひご覧ください。
SDGs14とは?「海の豊かさを守ろう」が目指していること

ここでは、海が人々の暮らしにとってなぜ大切なのか、「SDGs14 海の豊かさを守ろう」がなぜ必要とされているのかを解説します。
日本は、海から食や産業、文化など、さまざまな面で大きな恩恵を受けてきました。
その一方で、海を取り巻く問題も増えています。
SDGs14が掲げられた背景を知り、目標達成に向けて私たちに何ができるのかを、一緒に考えていきましょう。
なぜ海は大切なの?私たちのくらしとのつながり
海が大切な理由は、私たちの暮らしや地球環境を支える多くの役割を担っているからと言えるでしょう。
地球の約7割を占める海は、魚介類や海藻、プランクトンから大型の海洋生物まで、非常に多様な生き物を育む巨大な生態系。
これらの生き物は私たちの食料となるだけでなく、医薬品の原料などにも利用されており、人間の健康や産業を支えています。
また、海は海流によって熱や栄養を運び、世界の気温や気候を調整している働きも。
蒸発した海水は雲となって雨をもたらし、農業用水や飲み水の源にもなっています。
さらに、海は二酸化炭素を吸収する「巨大な炭素の貯蔵庫」として、地球温暖化の進行を緩和する重要な役割も果たしています。
漁業や物流、観光などの経済活動を通じて、世界中の人々の暮らしを支える存在でもあるのです。
SDGs14の10個のターゲットを分かりやすく紹介
「SDGs 14.海の豊かさを守ろう」には10個のターゲットが設定されており、目標達成を実現するために取り組むべきことを細かく説明しています。
10個のターゲットを分かりやすく紹介すると、
- プラスチックごみなど、陸から流れ出る海の汚染を減らすこと
- 壊れてしまった海や沿岸の生態系を回復させ、守ること
- 海の酸性化を防ぐため、科学的な対策を進めること
- 魚を獲りすぎず、資源を回復させる漁業を行うこと
- 海の一部を守る区域として保全すること
- 魚を獲りすぎてしまう原因となる補助金を見直すこと
- 海の資源を活かしながら、地域の経済を支えること
- 海を守るための研究や技術を世界で共有すること
- 小規模な漁業者が公平に働ける環境を整えること
- 国際的なルールに基づいて海を守ること
と、海の環境汚染や生態系を回復させる仕組み作りはもちろん、漁業に携わっている人々のために持続的に働ける環境を整えることも重要だと提唱しています。
SDGs14では、海の豊かさを守り、海洋や海洋資源を持続可能な形で利用していくため、国際的なルールに基づき、世界全体で協力して取り組むことが大切だと考えられているのです。
出典元:SDGs(持続可能な開発目標)17の目標と169のターゲット(外務省仮訳)
SDGs14が必要とされる理由
SDGs14が必要とされる理由は、海洋汚染や乱獲、気候変動などによって、海の生態系が深刻な影響を受けているからです。
これらの問題が進むと、多くの海の生き物がすみかを失い、絶滅してしまうおそれがあります。
海の環境悪化は、生物多様性がなくなるだけでなく、漁業者の収入減少や観光業の衰退、さらには気候変動の加速など、私たちの暮らしにも大きな影響を及ぼすでしょう。
SDGs14は、海洋汚染の削減や乱獲の防止、生態系の保全に取り組むことで、海を「将来にわたって使い続けられる状態」で次世代へ引き継ぐことを目指した国際的な目標なのです。
SDGs14から見る海の現状|起きている問題と将来の不安

ここでは、SDGs14の視点から、世界と日本の海の現状を見ていきます。
海では今、さまざまな問題が起きています。
これからの未来に向けて、どのような課題があるのかを確認していきましょう。
世界と日本の海の今|SDGs14の現状データ
世界の海に目を向けると、サンゴ礁の衰退や海洋汚染、水産資源の減少といった課題が見られます。
サンゴ礁の衰退の原因は、水質が酸性になる海洋酸性化や温暖化による白化など。
サンゴ礁が失われると、海の生態系全体に加え、私たちの食や生活にも悪影響を及ぼしかねません。
また、船から流出した油による汚染や、魚や貝の獲りすぎによる水産資源の減少も、世界的な問題と言えるでしょう。
日本の海でも、水産資源の減少や海洋プラスチックごみが、生態系に影響を与えています。
海洋プラスチックごみについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひこちらもチェックしてみてください!
【SDGs14.海の豊かさを守るために…】海洋プラスチックについて考えてみよう!
魚が減っている?生き物と海の環境の変化
海が抱える課題のひとつとして、魚の減少も挙げられるでしょう。
世界的に魚介類の需要が高まる中、獲りすぎが続くことで水産資源は減少傾向に。
魚が減ると、クジラや海鳥などの生き物も十分な餌を得られなくなり、海の生態系全体に影響が広がります。
こうした変化は生物多様性の低下につながり、海の環境を不安定にしてしまいます。
生物多様性は、食料の供給や気候の調整など、私たちの暮らしを支える大切な基盤です。
魚が減り続ければ、漁業をはじめとした仕事にも影響が及び、人の生活そのものが成り立たなくなるおそれがあります。
海の汚れと水の問題|ごみ・水質・酸性化
海がさまざまな原因で汚染され、水質が悪化している点も課題でしょう。
たとえば、海に流れ込むプラスチックごみ。
存在するだけで海を汚す原因の一つではありますが、それは細かく砕けて、プランクトン→小魚→中型の魚…というように、食物連鎖を通じて生き物の体内に蓄積されていきます。
マイクロプラスチックはダイオキシンなどの有害物質を吸着しやすく、それが体内にたまることで、生き物の成長や繁殖を妨げてしまいます。その結果、生物の数やバランスが崩れ、海の生態系全体や海洋環境に悪影響を及ぼすおそれもあるのです。
また、生活排水や農業由来の窒素・リンが海に流れ込むことで、水質が悪化するケースも。
さらに、水温の上昇や海の酸性化が進むと、プランクトンや小魚のすみかが失われるだけでなく、サンゴ礁の白化によって、海の回復力が弱まってしまいます。
これらの問題は互いに影響し合い、海の生態系全体を弱らせているのが現状です。
SDGs14を進めるために|日本や世界の取り組み

SDGs14の達成に向けて、日本や世界ではさまざまな取り組みが行われています。
ここでは、海を守るために進められている日本および世界の代表的な取り組みを紹介します。
日本の取り組み
日本では、SDGs14の達成に向けて、海洋環境を守るための政策が国レベルで進められています。
特に問題となっている海洋プラスチックごみへの対策として、国は関連法の整備や海岸漂着物の回収を進めてきました。
2020年7月にはレジ袋の有料化が義務付けられ、使い捨てプラスチックを減らそうとする動きが、私たちの身近な行動にも広がっています。
こうした制度を通じて、国全体で海を守る意識と行動を後押ししている点が、日本のSDGs14の取り組みといえるでしょう。
SDGs14を実現するための企業の取り組みについては、以下の記事で紹介しています。
「SDGs 14.海の豊かさを守ろう」の取り組み事例を解説!
コンタクトレンズの空ケースをリサイクル!シードのSDGsとは!
岐阜県の「長良川システム」も、SDGs14の実現を目指す取り組みです。
以下の記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
【SDGs.14 海の豊かさを守ろう】「長良川システム」について知ろう!
世界の国々の動き
世界でも、SDGs14の達成に向けた政策が進められています。
ノルウェーでは1999年から「デポジット制度」を導入し、飲料容器を回収・再利用する仕組みを整えてきました。
商品購入時に預り金を上乗せし、容器返却時に返金する制度により、高い回収率を実現しています。
その結果、ノルウェーではペットボトルのリサイクル率が97%に達しました。
そのほか、EUでは「EUプラスチック戦略」を打ち出しています。
- プラスチックリサイクルの経済性と品質の向上
- プラスチック廃棄物と海洋ごみ量の削減
などを軸として精力的に取り組み、大きな成果を上げています。
また、EU全域に使い捨てプラスチックに関する規制案も提案し、プラスチックごみの削減に尽力しています。
参照元:環境庁「EUの政策概要」
国連が進めていること
国連では、海洋保全とブルーエコノミーを支えるための新たな国際金融プラットフォームとして、「One Ocean Finance Facility」の設計を進めています。
これは、海洋分野への投資が不足している現状を改善し、海洋保護や持続可能な海洋経済への資金を拡大することを目的とした取り組みです。
SDGs14の達成には多額の資金が必要ですが、これまでの投資額は十分とはいえません。
国連は、革新的な資金調達の仕組みを通じて投資を拡大し、2030年に向けて海を守る取り組みを加速させようとしています。
SDGs14を家庭で実践!子どもとできる海を守る方法

引用元:MEL協議会公式
ここからは、SDGs14の達成に向けて、お子さまと一緒にできる身近な取り組みを紹介します。
難しく考えず、できることから親子で楽しく始めてみましょう。
サステナブル・シーフードを選ぶ
サステナブル・シーフードとは、MSC(Marine Stewardship Council:海洋管理協議会)認証やASC認証(Aquaculture Stewardship Council:水産養殖管理協議会)のラベルが貼られた水産物です。
MSC認証は、海洋環境に配慮した魚の獲り方を守っている水産物に与えられる認証ラベルで、「海のエコラベル」と呼ばれています。
一方、ASC認証は、環境や地域社会に配慮した養殖で生産された水産物に与えられる認証ラベルです。
いずれの水産物も、現場から加工流通のプロセスまで厳しい審査をクリアしており、海や環境への影響が少ない製品であることを示しています。
そのため、サステナブル・シーフードを選ぶことは、SDGs14を実現させるために有効な方法だと言えるでしょう。
食品ラベルを親子でチェックする
親子で一緒に買い物に行く際、先ほど紹介した認証ラベルがある食品をチェックしてみましょう。
MSC認証やASC認証のラベルのほか、MEL(Marine Eco-Label Japan)ラベルと呼ばれるものもありますが、こちらは日本の「一般社団法人マリン・エコラベル・ジャパン協議会」によって作られています。
MELラベルも、環境や生態系の保全に配慮し、適切に管理された漁業の生産者、加工業者、流通業者を認証するラベル。
魚が「e」のように見える可愛らしいデザインのラベルです。

引用元:日本水産資源保護協会
スーパーで買い物をする際に、MSC認証やASC認証のエコラベルなど、海のエコラベル探しゲームをしてみても、楽しくエコラベルを覚えられそうです。
ぜひ、親子でエコラベルの商品をチェックしてみてください。。
自由研究で海のごみや生き物を調べる
夏休みの自由研究で、海のごみや生き物を調べて発表してみるのもおすすめです。
本やインターネットなどで、海にどのようなごみがあるのか、ごみによって海の生き物にどのような影響があるのかを調べるのも面白いですよ。
- プラスチックごみにはどのようなものがあるのか?
- プラスチックごみは、なぜ海に集まるのか?
- プラスチックごみによって、どのような被害や影響があるのか?
- プラスチックごみを減らすにはどうすればよいか?
これらの情報を調査して自分なりにまとめてみることで、おのずとSDGs14についての知識が深まっていきます。
自分が何をすべきなのかがはっきりと掴めてくるでしょう。
海岸のごみ拾い+SNS「ピリカ」に投稿する
海岸のごみ拾いなどボランティア活動に積極的に参加してみることも、SDGs14の実現に貢献していることになります。
ボランティア活動は、自治体や団体などが開催しています。
ネットで調べてみると、近くで「ごみ拾いのボランティア募集」といった情報が見つかるかもしれません。
ぜひ、家族や友人を誘って参加してみてください。
さらに、その活動をSNSサービス「ピリカ」に投稿してみましょう。
ピリカとは、誰でもいつでも、気軽にごみ拾いの様子を発信できる完全無料のSNSサービス。
ごみ拾い活動を投稿することで、世界中へ活動状況を発信することが可能です。
拾ったごみの写真を撮って、共有してみましょう。
ピリカを利用している人から「ありがとう」が届くので、ちょっと嬉しい気持ちになりますね。
ピリカを活用すれば、楽しくごみ拾いが続けられるでしょう。
App Store
Google Play
プラスチック削減に取り組む
家庭でできることからプラスチック削減に取り組んでみましょう。
たとえば、飲み物をマイボトルに入れて持ち歩けば、ペットボトルの使用を減らすことが可能。
また、エコバッグを使うことで、レジ袋の削減にもつながります。
プラスチック容器を使わない固形シャンプーや詰め替え用の商品を選び、ボトルを長く使う方法も効果的。
普段より少しだけ意識してプラスチック削減に取り組むことで、親子でできる海を守る一歩になりますよ。
子どもと一緒に楽しく学ぶSDGs14|絵本・動画・クイズ

ここでは、お子さまと一緒にSDGs14について楽しく学べる絵本や動画、クイズを紹介。
ぜひ親子で取り組んでみてください。
おすすめ絵本3選
『ウミガメものがたり』
鈴木 まもる(作・絵)
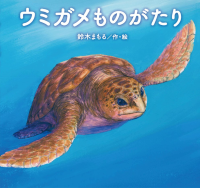
あまり知られていないウミガメの生態を、排卵から子ガメが海へ旅立ち、再び生まれた海に戻るまでの物語として描いた一冊です。
子ガメが成長するまでには、エサと間違えてプラスチックごみを食べてしまったり、漂流するロープや網に絡まったりと、さまざまな試練が待ち受けています。
その多くが、人間の出すごみによって引き起こされているもの。
ウミガメが懸命に生きる姿を通して、なぜ海の豊かさを守らなければならないのかを自然と理解できる絵本です。
ウミガメものがたり
『プラスチックのうみ』
ミシェル・ロード (著)、ジュリア・ブラットマン (イラスト)、川上 拓土 (翻訳)
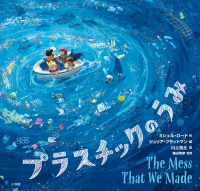
一見すると、青く輝く海にカラフルで美しいものが浮かんでいるように見える表紙ですが、その正体はすべてプラスチックごみ。
美しく見える海がゴミだらけというギャップのあるイラストが強く印象に残ります。
人間が出したプラスチックごみが海にどのような影響を与えているのかを、美しいイラストとわかりやすい言葉で伝えてくれる一冊です。
本書はアメリカで刊行された絵本ですが、日本語版の翻訳を担当したのは、環境問題に関心をもつ小学生の男の子。
豊かな海を守るために私たちに何ができるのか、親子で考えるきっかけを与えてくれます。
プラスチックのうみ
『海がどんどんこわれていく』
保坂 直紀(著)、こどもくらぶ(編集)
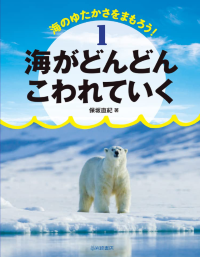
海岸に捨てられたごみやプラスチックごみが、海にどのような影響を与えているのかを、写真や図を使ってわかりやすく解説した一冊です。
ごみ問題を身近な出来事として捉えながら、海の環境を世界規模で考える大切さにも気づかせてくれます。
本書は「SDGs14 海の豊かさを守ろう」をテーマにしたシリーズの1冊。
ほかにも関連書籍が刊行されているので、興味があればあわせてチェックしてみてください。
海がどんどんこわれていく
子ども向けSDGs14動画
海が抱えている課題、プラスチックごみが海に与える影響などを、アニメでやさしく、分かりやすく教えてくれています。
自分ができることを具体的に知ることができるため、さっそく今日から実践してみようと思えるはず。
10分ほどの動画なので、すき間時間に気軽に見ることができます。
楽しく学べる海の生き物クイズ
みんなで楽しく学ぶSDGsクイズ
海洋プラスチックごみクイズ | プログラミングでSDGs!
楽しくSDGs14について学べる選択式のクイズ。
解説付きなので、+αの知識が身につきますよ。
ぜひ親子でチャレンジしてみてください!
親子で考えるにあたり、以下の記事も参考にしてみてください。
親子で考えよう!目標14 海を守る
SDGs14に関するよくある質問

SDGs14にはどんな目標があるの?
将来にわたって、持続可能な開発のために海の豊かさを保全し、海洋や海の資源を持続可能な形で利用することが目標です。
たとえば、「海洋汚染を減らす」「生態系を回復する」といった目標が定められています。
プラスチック以外に、海のどんな問題があるの?
プラスチックのほかにも、「海洋汚染」「乱獲による海洋資源の減少」「サンゴ礁の白化」などの問題があります。
家庭でできることは、何から始めればいい?
「マイバッグ・マイボトルを使う」「ゴミを分別する」「プラスチックをリサイクルする」「エコラベルの魚を選ぶ」など、まずは身近なことから少しずつ始めましょう。
SDGs14を親子で学び、できることから始めてみよう

私たちは「海の恵み」に支えられて生活しています。
地球の7割は海であり、生物の命も海なしでは成り立ちません。
美しい海を守るため、SDGs14「海の豊かさを守ろう」では、世界各国がさまざまな取り組みを行っています。
しかし、私たち一人ひとりにもできることが確実にあります。
周りのごみを拾う、ペットボトルをリサイクルに出す、マイボトルやマイバッグを持つ。
小さな行動からで大丈夫。できることから、親子で海を守る取り組みを始めてみましょう。
SDGsについてさらに詳しく学びたいなら、以下の記事で紹介している本がおすすめです!
【SDGs本】子どもと一緒に読むならこれ!おすすめ9選
みらいいおすすめ!「こどもSDGs なぜSDGsが必要なのかがわかる本」をご紹介!












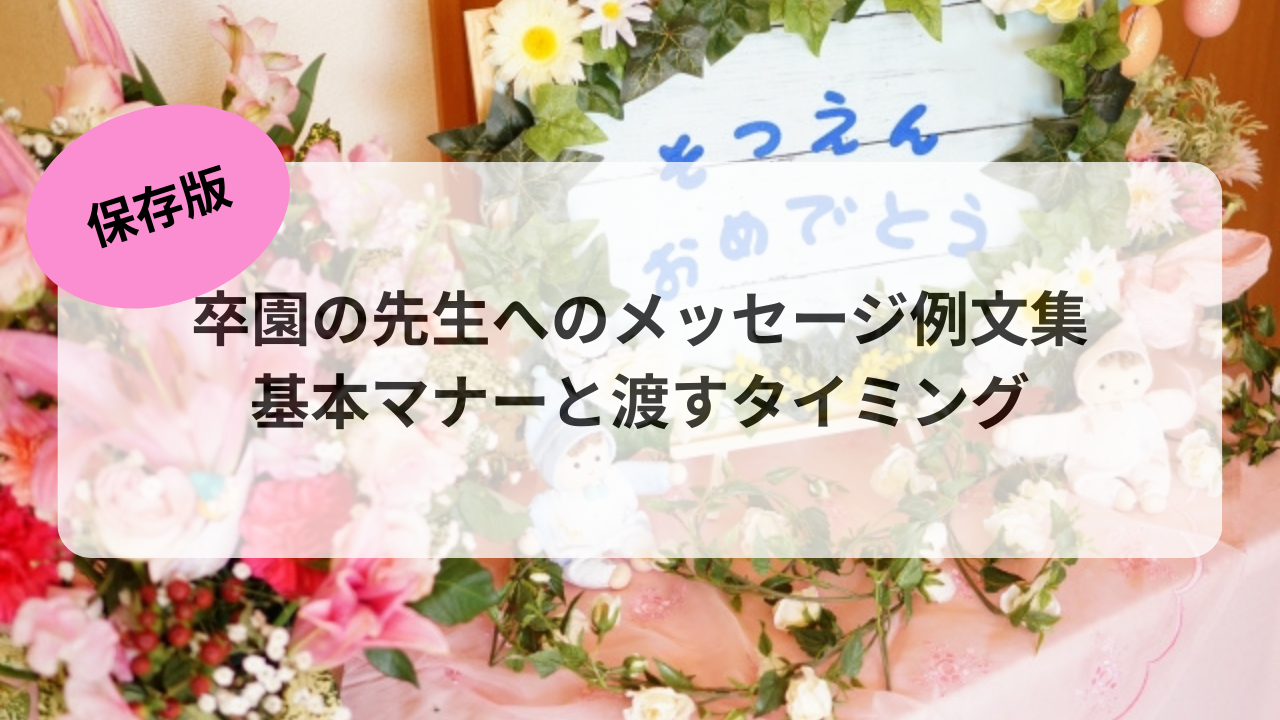
%20(1).jpg)