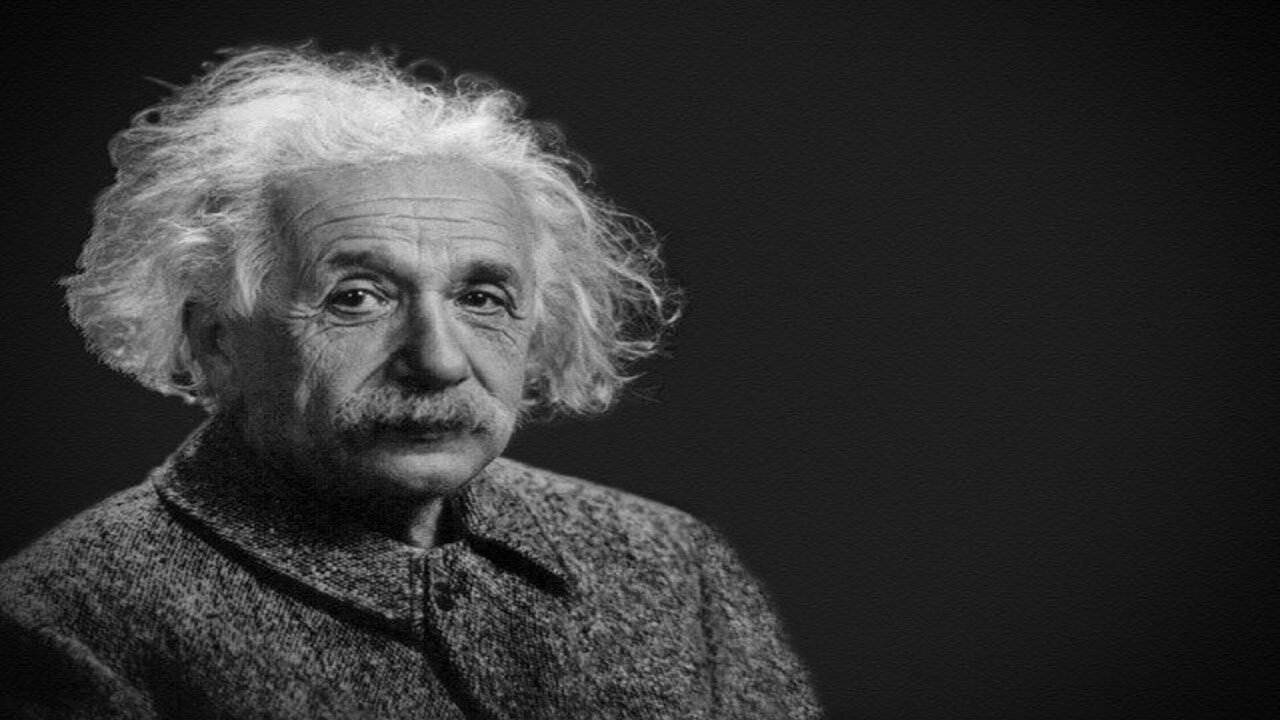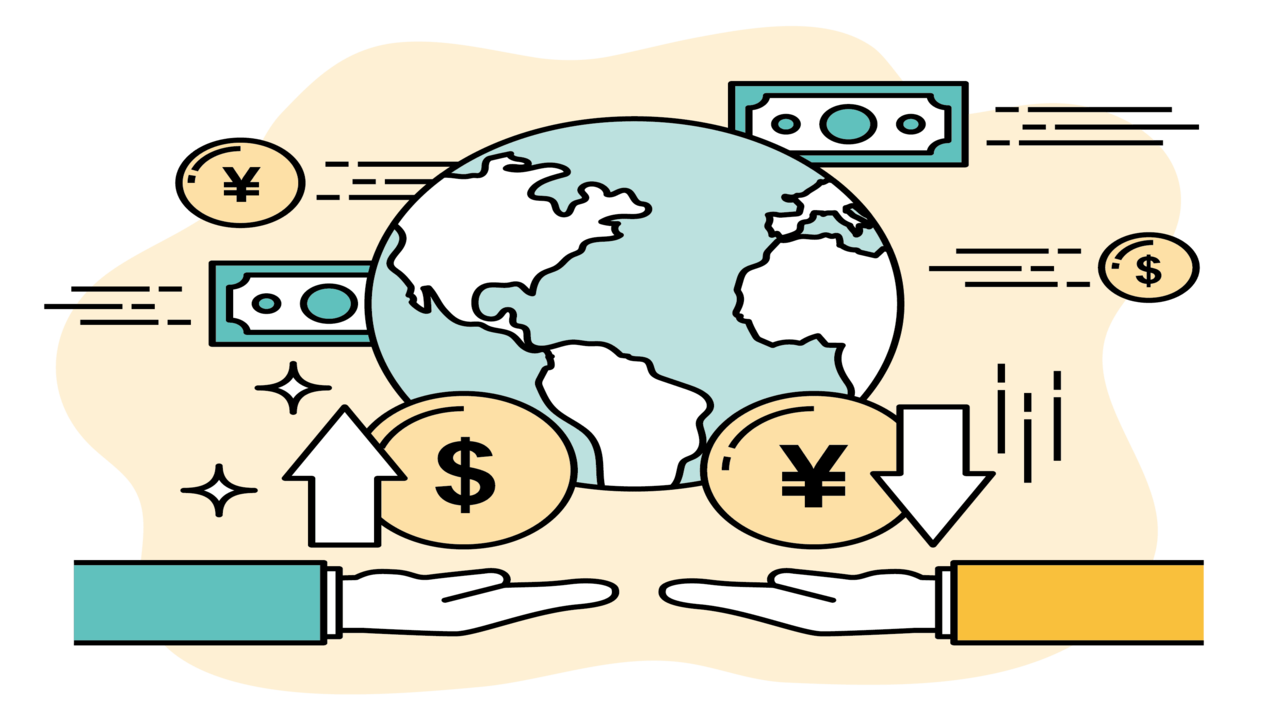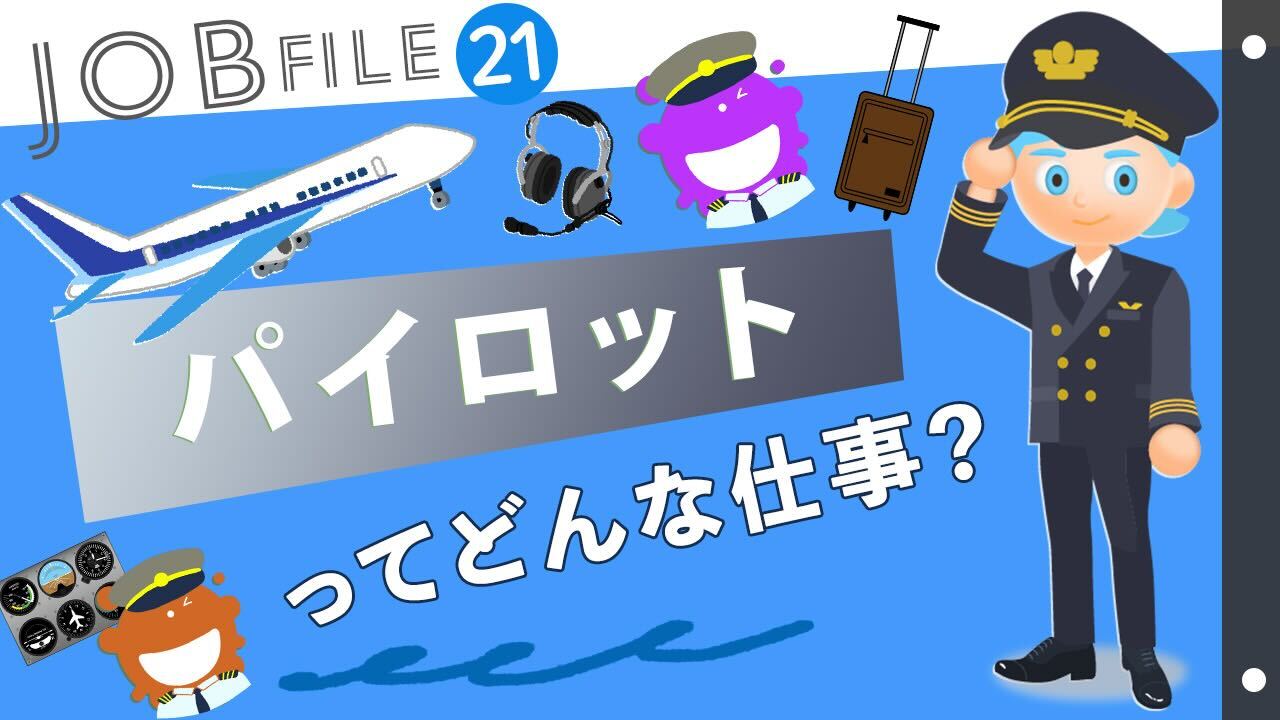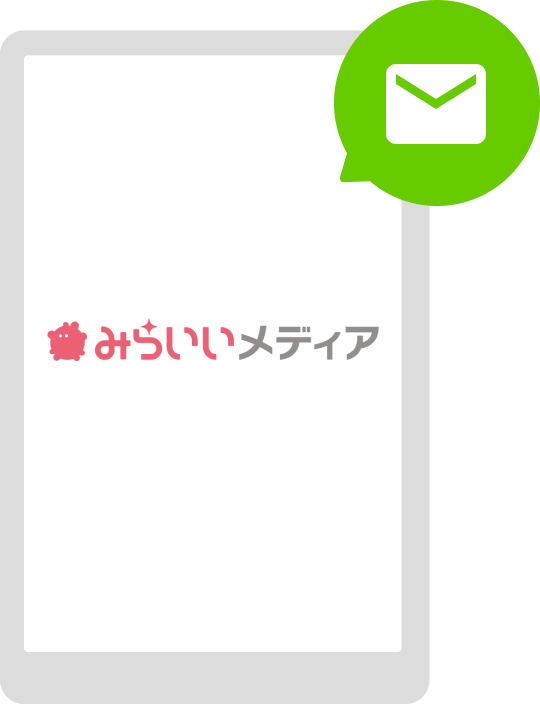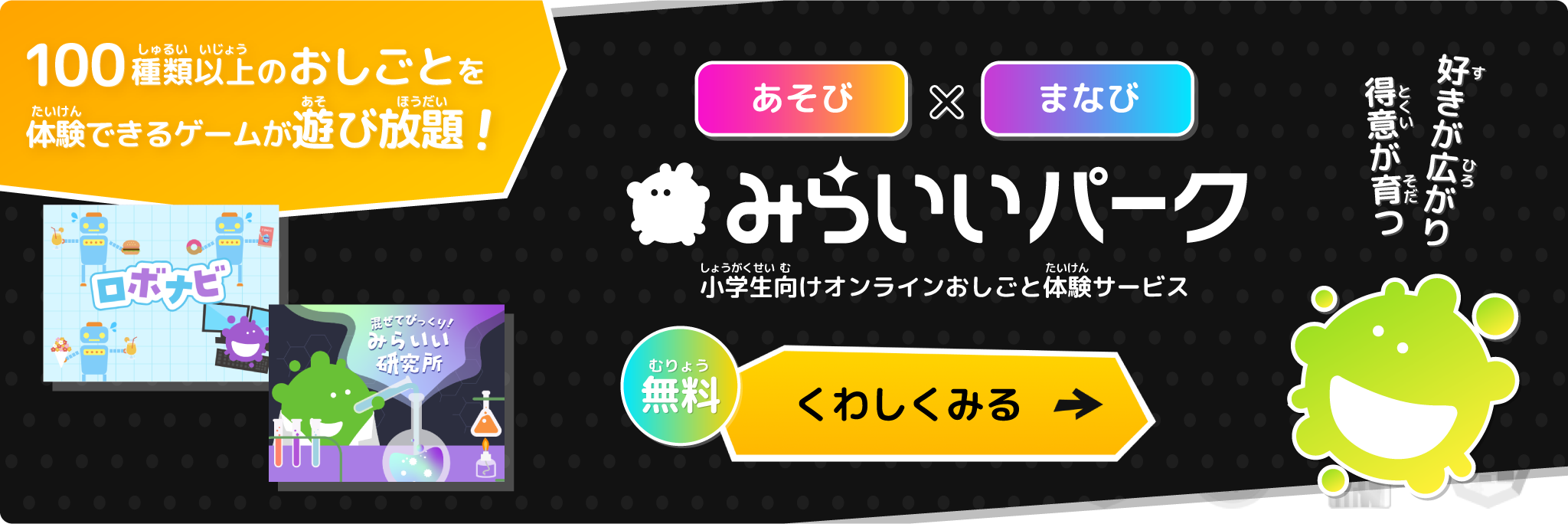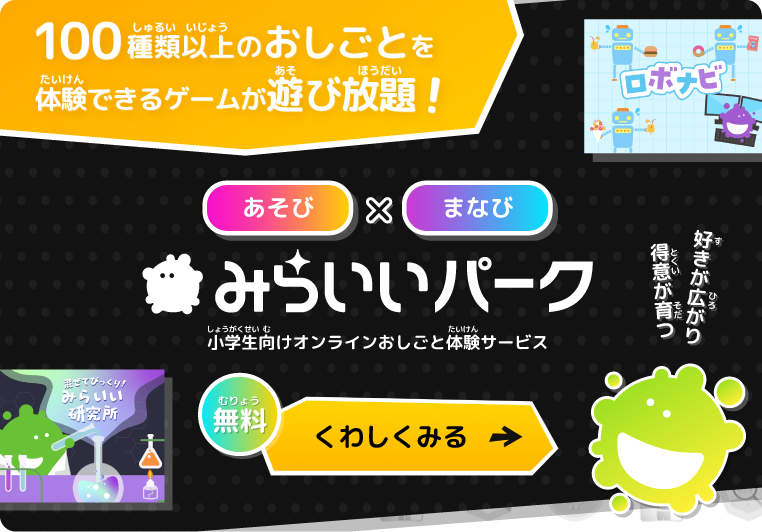【STEAM教育】日本と世界の取り組みをわかりやすく解説

時代の変化とともに「活躍できる人材像」が変わり、教育制度は変化しています。
変化の一つである「STEAM教育」。「耳にしたことはあるけど、よくわからない」と疑問に思う方が多いのではないでしょうか。
実際に、学研教育総合研究所の調査によると、日本ではSTEAM教育の認知度は20%と低いのが現状です。
しかし、実はアメリカでは国家戦略としているほど、将来生きていくために非常に重要視されている教育手法でもあります。
そこで今回は、子ども達の未来に向けて、日本の教育や世界の教育はどのような状況になっているのか。STEAM教育の意味と背景、日本や世界の先進事例を紹介します!
STEAM(スティーム)教育って何?国家戦略に置くアメリカの事例とは

STEAM(スティーム)教育とは?
まず、STEAM教育とは何なのか?についてです。
STEAM教育とは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Art(芸術と教養)、Mathematics(数学)の頭文字をとったもので「スティーム」教育というふうに呼びます。
この教育手法の前進に、「STEM(ステム)教育」がありました。これは理数系の教育分野を指すことが多かったのですが、ものづくりには科学知識や技術の他にデザイン性や人間が生きていくうえでの根本的な考え方や知識が必要だという考えが高まり、Art(芸術と教養)が加わり現在のSTEAM教育という名前になりました。
STEM教育についてはこちらをご覧ください。
なお、他には、Sports(体育)を加えた「STEAMS」など、概念を派生させたものもあります。
さらにSTEAM教育とはについて詳しくはこちらをご覧ください。
なぜSTEAM教育が必要なの?
ではなぜ、STEAM教育が必要と言われているのでしょうか?
それはずばり、社会変化にあります。
ロボット化が進んでいく中でロボットに使われるのはなく、「新たな変化を生み出せる能力を持つ人材」が必要とされているからです。しかし、変化を生み出すことができるデザイナーやエンジニアは全世界で不足しているので育てる必要があるというのが、STEAM教育が必要な理由になります。
STEAM教育を「国家戦略」と宣言したアメリカの教育事例とは
最初にSTEAM教育の重要性を訴えたのは、アメリカだと言われています。
アメリカの前大統領のオバマ大統領が2011年に演説で述べたことで、世界へ広まり始めました。
「コンピューター・サイエンスは国の未来のために必要。スマートフォンやゲームで遊ぶだけでなく、実際にプログラミングをしてみよう」というメッセージとともに、STEAM教育をアメリカの国家戦略とし、教育省が実証プロジェクトを推進しています。
アメリカでの教育実例は、以下のようなものがあります。
・ある惑星からサンプルを持ち帰るミッションを、NASAのチームに協力してもらいながら設計する
・一定の地域で風力発電量を調べ、3Dプリンターを使って風車を作成する
・ハッカーに破られないように、自分のみが開け方を知っている箱を作る
だいぶ実践的な内容と思われた方が多いのではないでしょうか。
日本のSTEAM教育の方針や事例はどのようなものなの?

文部科学省の方針は?
では、日本のSTEAM教育の方針や事例はどのようなものなのでしょうか?
日本でも同様に、AIやロボットなどのデータ駆動型社会の到来によって、数理・データサイエンス・AIの知識や素養が、社会生活の基本「読み書きそろばん」と同様に重要になってきていると考えられています。そして、これからの社会で生きていくのに必要な力をつけるために、2020年台は次のような「教室」が必要だとされています。
・「教科」を勉強する場
・地域社会課題を解決するための取り組み「マイ・プロジェクト」を遂行する場
・学習環境の改善などの身近な活動への取り組みや、特別活動として他校生や研究者、企業人達と連 携を取る「ルール形成能力」育成の場
3つに共通するポイントは、EdTech(個別最適化)×生徒同士の協業による学び合いです。EdTech(エドテック)とは、学習教材として用いられるパソコンやタブレット、授業動画を見たり、ドリルを解いたりできるような技術を指します。
EdTechを活用した教科学習のメリットは、個別最適化ができるので一人ひとりの学習効果が高まることが期待できることです。
新しい教育手法を取り入れる際は、既存の学習への影響を考慮する必要がでてきますが、EdTechにより教科学習の生産性向上をめざし、捻出した時間でSTEAM系のワークショップを実施したいと考えているようです。
日本の教育事例(1)STEM教育研究センターの設置
では、日本では具体的にどのような取り組みが行われているのでしょうか?ここでは2つ紹介します。
1つは「STEM教育研究センター」です。
埼玉大学にある、ロボットやプログラミングを子ども達と行う研究センターです。地域における子ども達の居場所づくりと、ものづくりの活動を通した教育研究や、学校などの教育機関と連携して小学校の授業づくりや出張講義を行っています。
例えば、「ロボットと未来研究会」やロボカップジュニアなどのコンテストを開催しているそうです。外部連携については、小中学校の総合学習の時間の企画や運営支援をしているそうです。
日本の教育事例(2)聖徳学園中学・高等学校での取り組み
もう1つは私立の中高一貫校での取り組み例です。
東京都にある聖徳学園では「Global Thinking」「ICT&Innovation」をキーワードに、海外でも活躍できる人材育成に注力しています。生徒1人1台iPadを導入し、STEAM教育を実践しています。2017年に「STEAM棟」を竣工し、そこでは、生徒達がプログラミンを学んでいるそうですが、それだけでなく「課題解決力」を育むことに力をいれています。例えば、世界や地元・武蔵野市が抱える実際の課題を見つけ、科学や技術を用いて解決するといった実践を行っているそうです。
日本でのSTEAM教育推進にあたっての課題や世界の導入事例は?

日本は他の国にかなり遅れをとっている
日本での導入は2020年からになりますが、世界では遅れているのが現状です。実際、IT先進国であるインドは2015年から導入しています。
また、日本のSTEAM教育をするにあたって、課題もあると言われています。例えば、STEAM教育の一翼を担うプログラミング教育があります。プログラミングを使って教科学習の理解を深めることを目的としたもので、2020年から小学校で必修化されることが決定しています。しかし、指導力の不安や、パソコンやタブレット配備状況などのICT環境が自治体により差があるのが現状となっています。
文部科学省の調査によると、指導力については、日本全体でみると年々向上している一方で、都道府県別にみるとばらつきがあり、平均値を下回る県が過半数を超えるという結果でした。つまり、指導力が高い県とそうでない県の差が大きいのが現状です。
また、ICT環境の整備状況については、教育用コンピュータ1台当たりの児童生徒数は、ここ5年で6.4人から5.4人と改善されていますが、都道府県別に見ると1台あたり1.8人~7.5人と県により開きがあることが分かっています。
世界でも遅れをとっている日本。教育研修はあるようなので、教員へのスキルインプットを促しながら、外部講師の活用などで指導力のばらつきがないようにしながら、ICT環境の整備も足りないところは推進していってもらいたいところですね。
イスラエルの事例
では、世界の教育事情はどのようになっているのでしょうか?
1つ目はイスラエルです。
実は、イスラエルはITやサイバーセキュリティの先進国でありスタートアップ文化が根付いている国なだけに、IT人材の教育にも力をいれています。例えば、次のような教育を行っています。
・幼少期から高校卒業後までのSTEAM教育を一貫して実施し、能力開発の機会を作っている
・小学校からプログラミングを必修。高校卒業後の兵役時に、能力に合った部隊へ配属、IQ、リーダーシップ、ハッキング、プログラミング能力等で評価・配属。任務で能力開発を行う
・幼稚園に関しては、より高度な科学技術幼稚園を設置し、科学やロボット工学を学ぶ
いかがでしょうか。「こんなにも日本とは教育環境が違うのか!」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
イスラエルでは18~19際から、男女ともに徴兵制度があるのですが、そこで生活をすることで、能力開発だけでなく、チームワークやリーダーシップなどの力も身につき、結果的にスタートアップ養成所のような役割を果たすようになってきているとも言われています。
アメリカの事例
2つ目の事例はアメリカでの取り組みです。
サンディエゴのHigh Tech Highという学校では、カリキュラムが自由なSTEAM学習を実践しています。教科書はなく、1日中、頭と手を使います。プログラミング教育はもちろんですが、ライフスキル(非認知能力)の重要性を前提にした教育を行っています。
非認知能力というのは、学力などの認知能力の対極にある概念で、意欲、創造性などの個人の特性による能力で、集団行動の中で養われるものが多いと言われています。
子ども達は、観察、考察、記録、結果発表といった段階を経ることで、目的とするものを作り出しています。その課程で、知識を活用して何かを創る創造性、批判的思考力、課題解決能力、協業する姿勢、失敗から学ぼうという姿勢を身に着けているそうです。
よく、「社会に出たら学歴は大概関係なくなる」という言葉を聞きますが、非認知能力は人生に大きな影響があると考えられそうですね。
まとめ
以上、STEAM教育の意味と背景、日本や世界の先進事例の紹介でした。うすうす感じられているかもしれませんが、今そしてこれからの教育は、かつてお父さんお母さんが受けた教育とはかなり違ってくるということ。
自分が受けなかった教育を我が子が受ける時代になった今、「読み書きそろばんの大切さは分かるけど、STEAM教育は受けてないからいまいちピンと来ない」という人も多いのではないでしょうか。
大切なのはこれからくる未来をできるだけ具体的に想像することと、子ども達が大人になったときに幸せな人生を送れているかということだと考えられます。教育は根本的には「子どもが幸せに生きるためのスキルセット」なので、お父さんお母さんも、引き続き日本や世界の教育の動向をみながら、子ども達にしてあげられることを、考えていけるとよいですね!
お子さまの個性に合わせた体験ができるオンラインのプログラミングワークショップはこちらから!
【オンライン開催】子どもの"やってみたい”からはじめる!小学生のプログラミング無料体験!






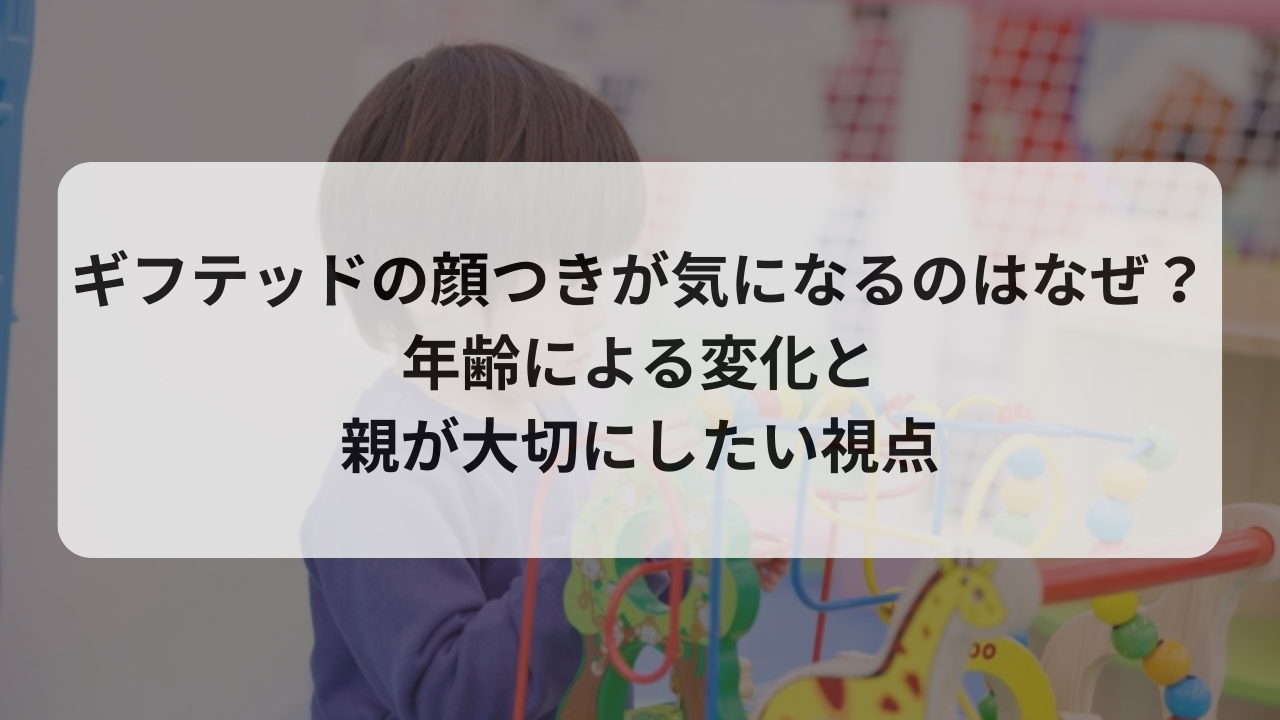
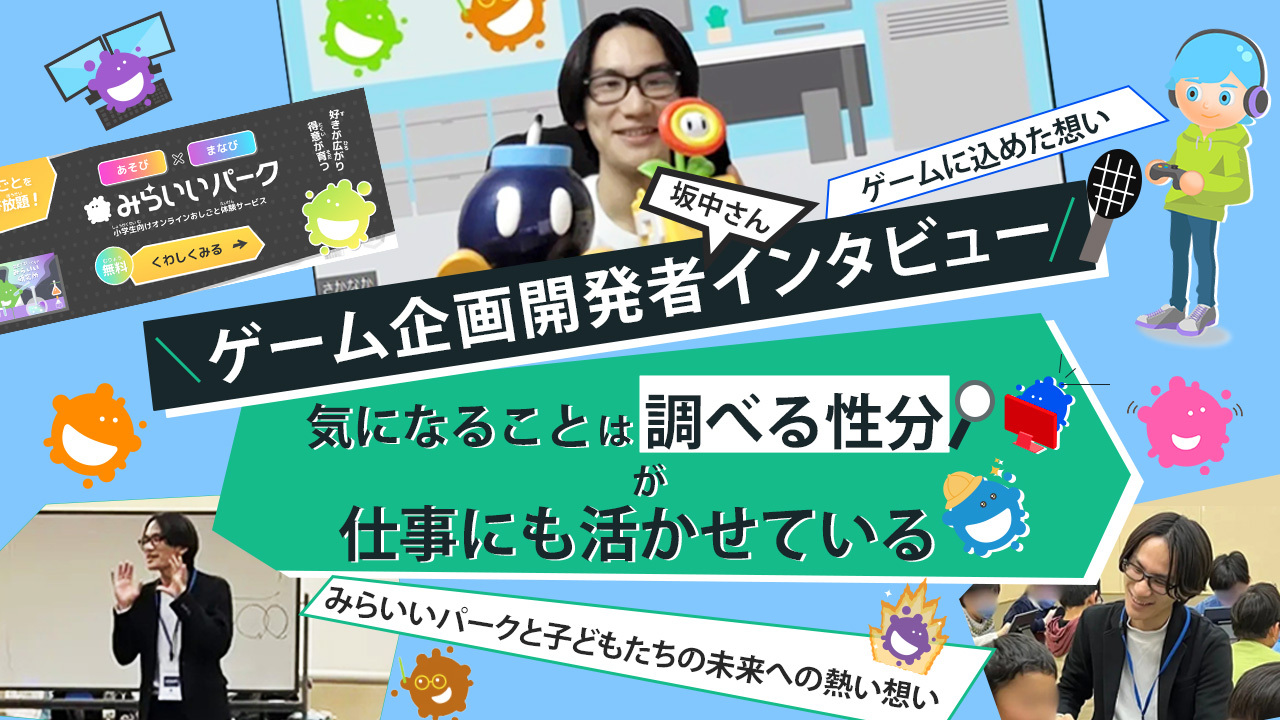

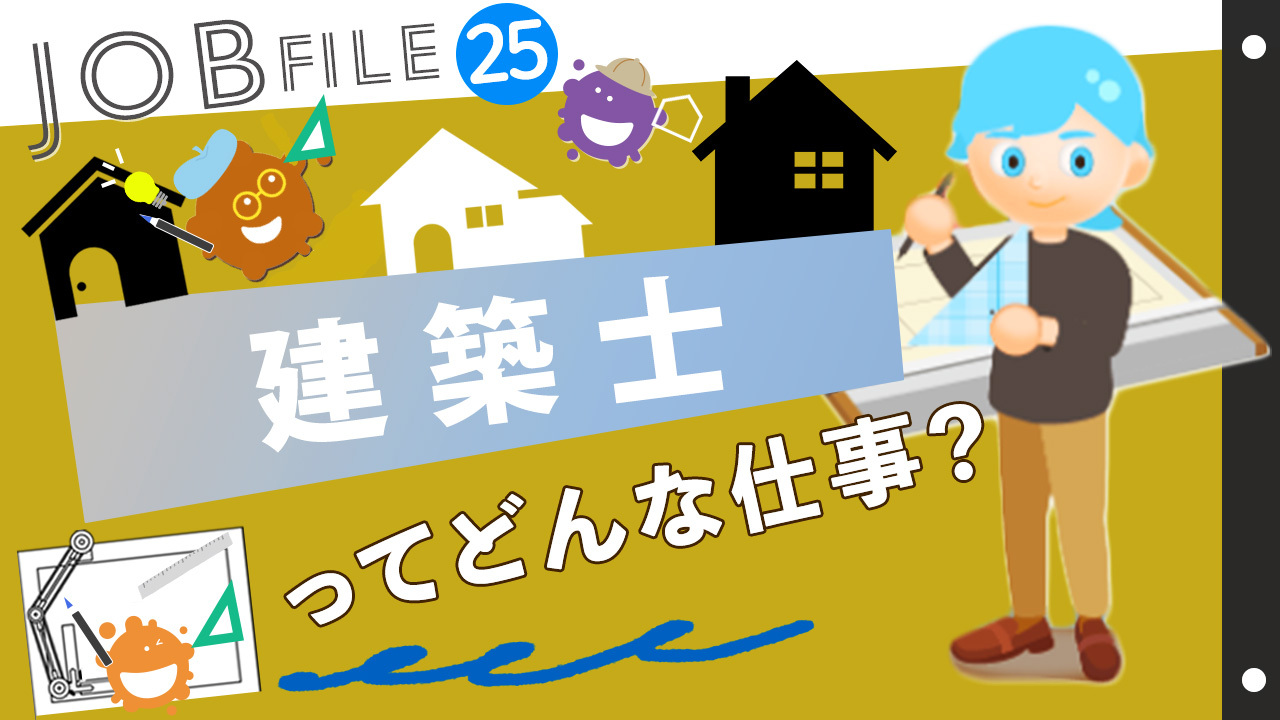

%20(1).jpg)