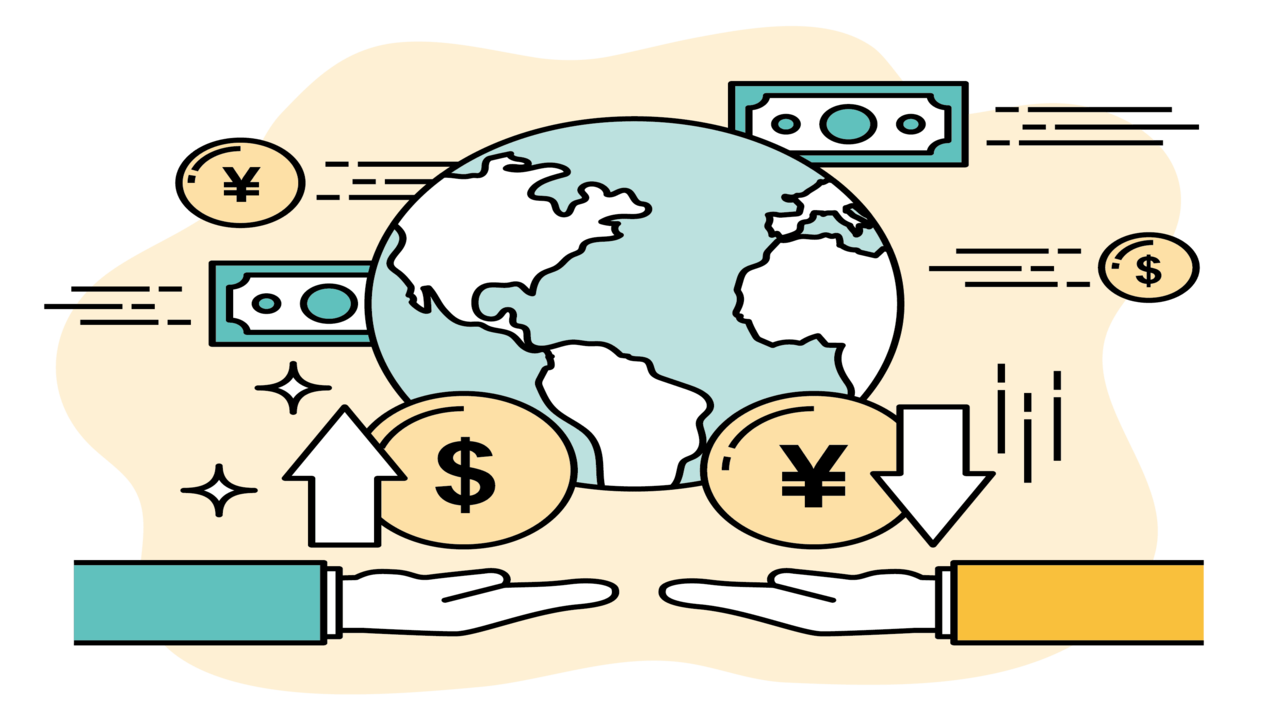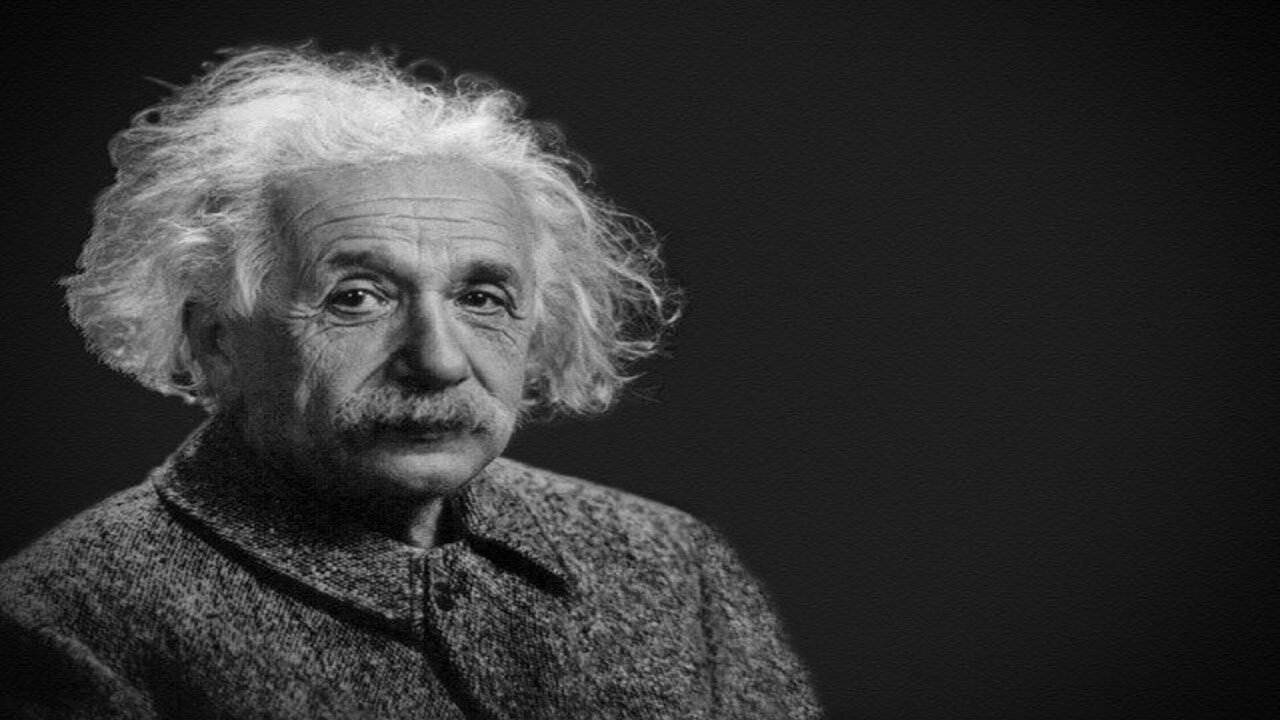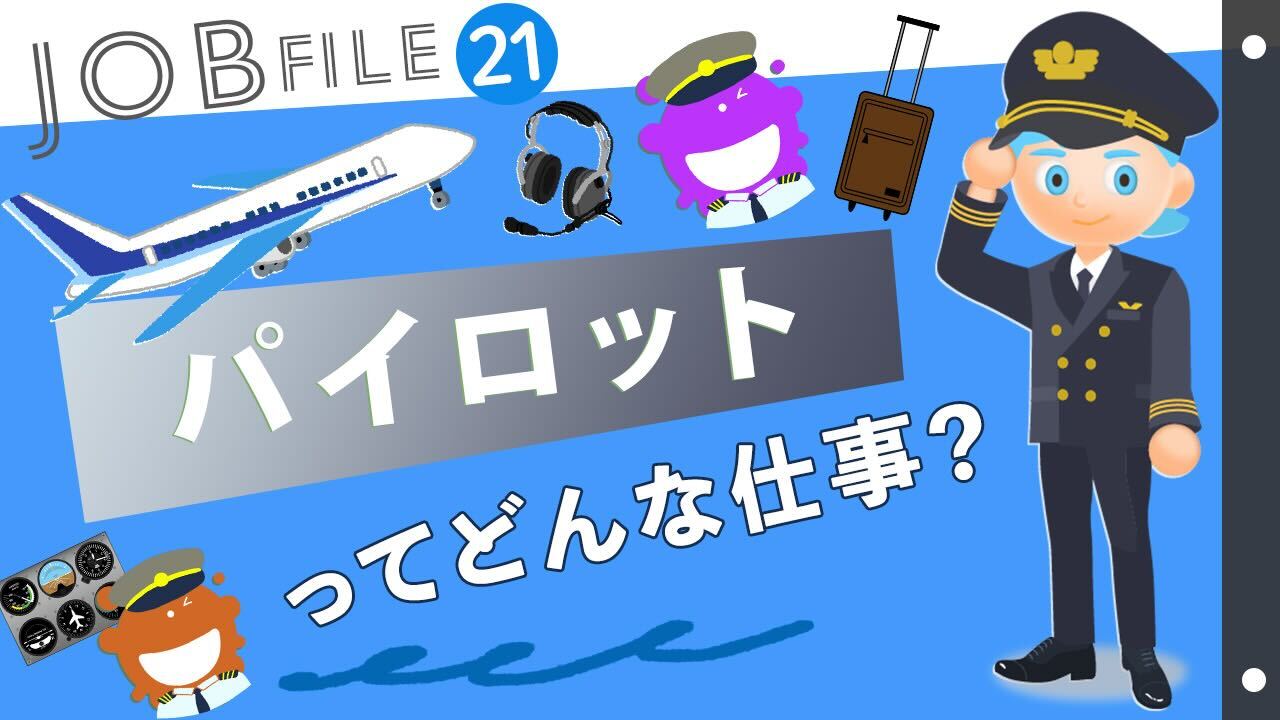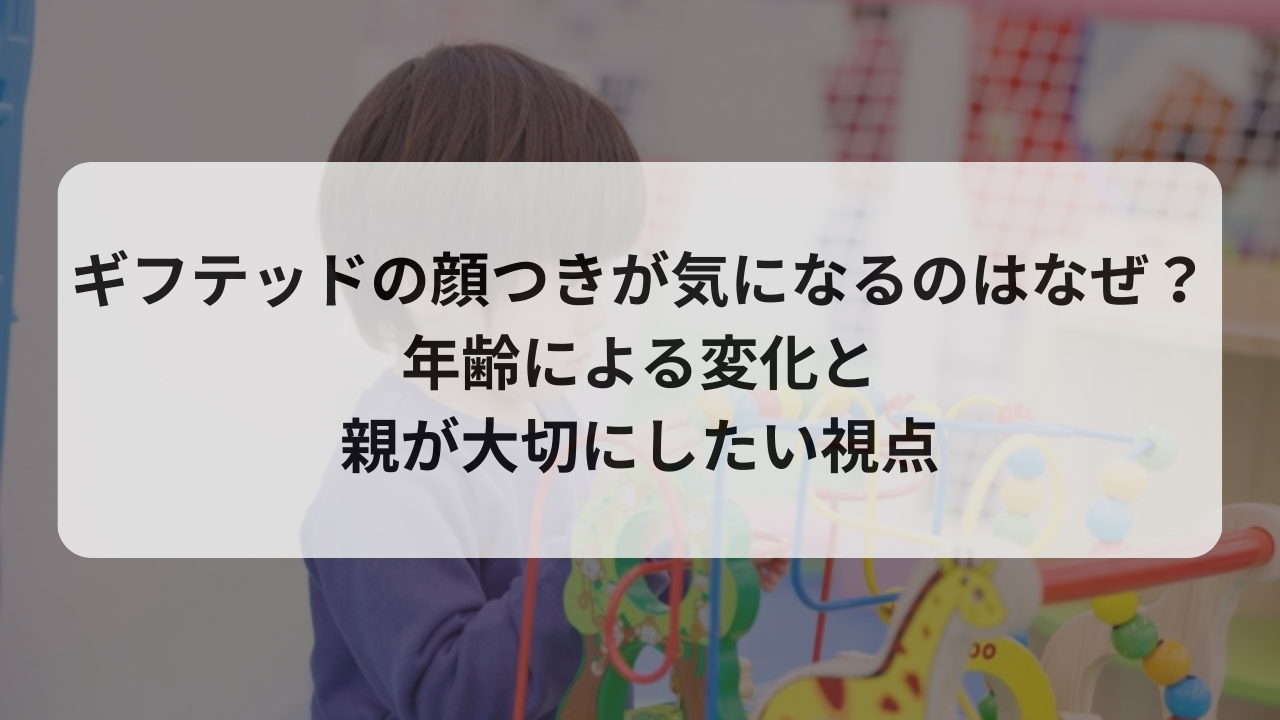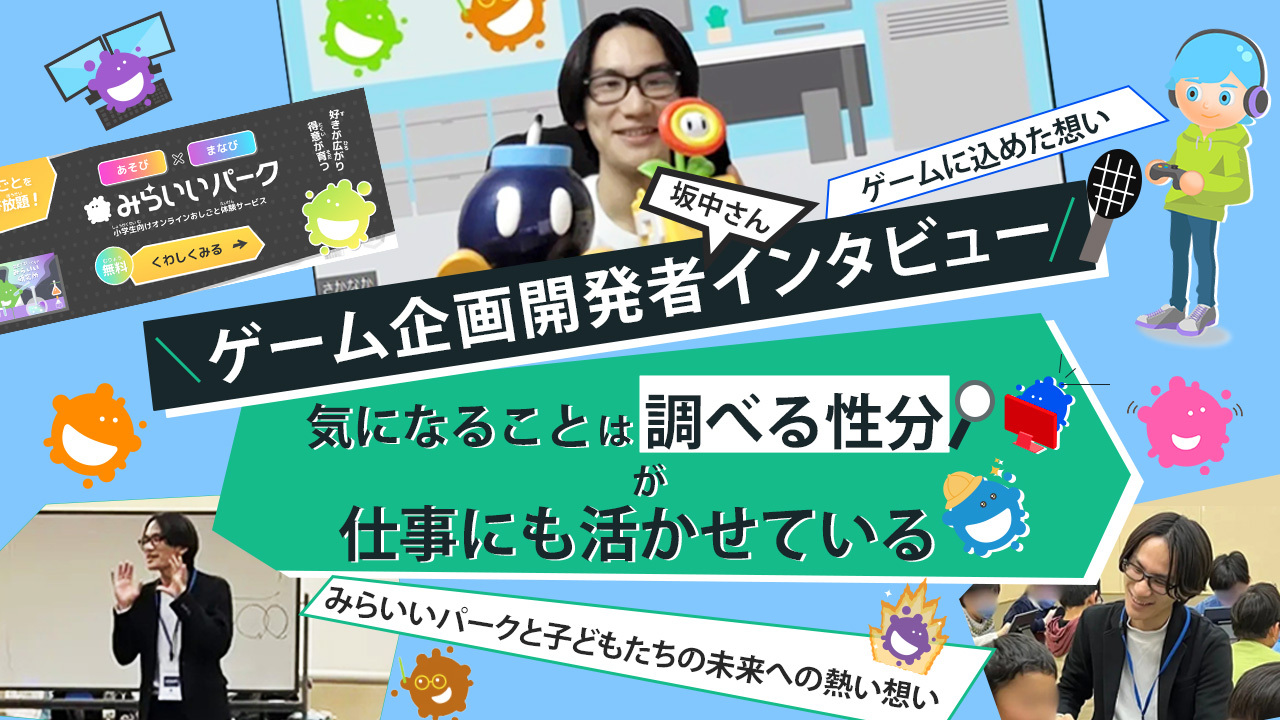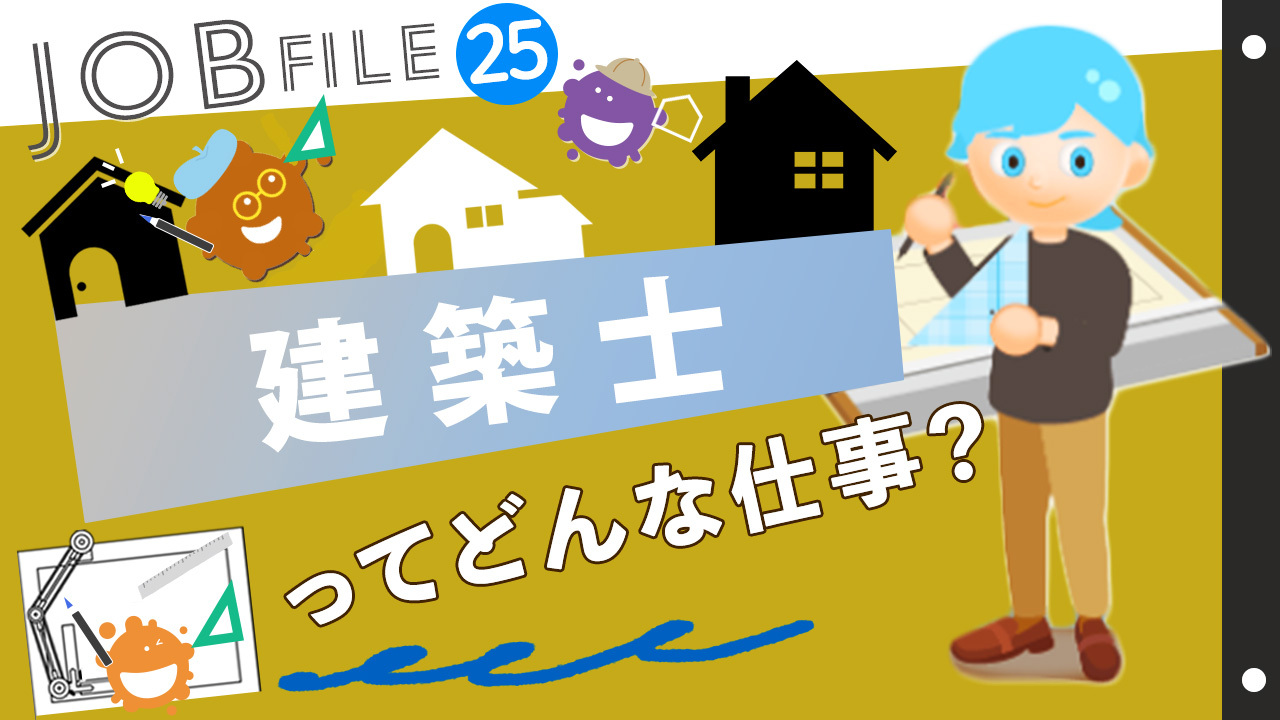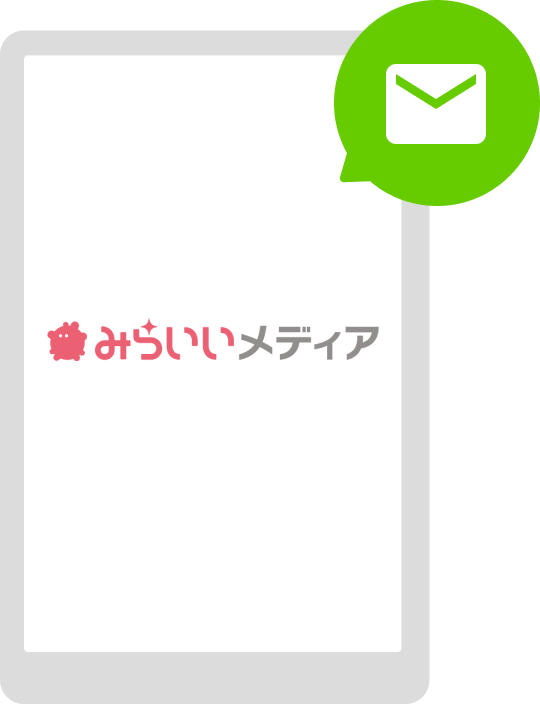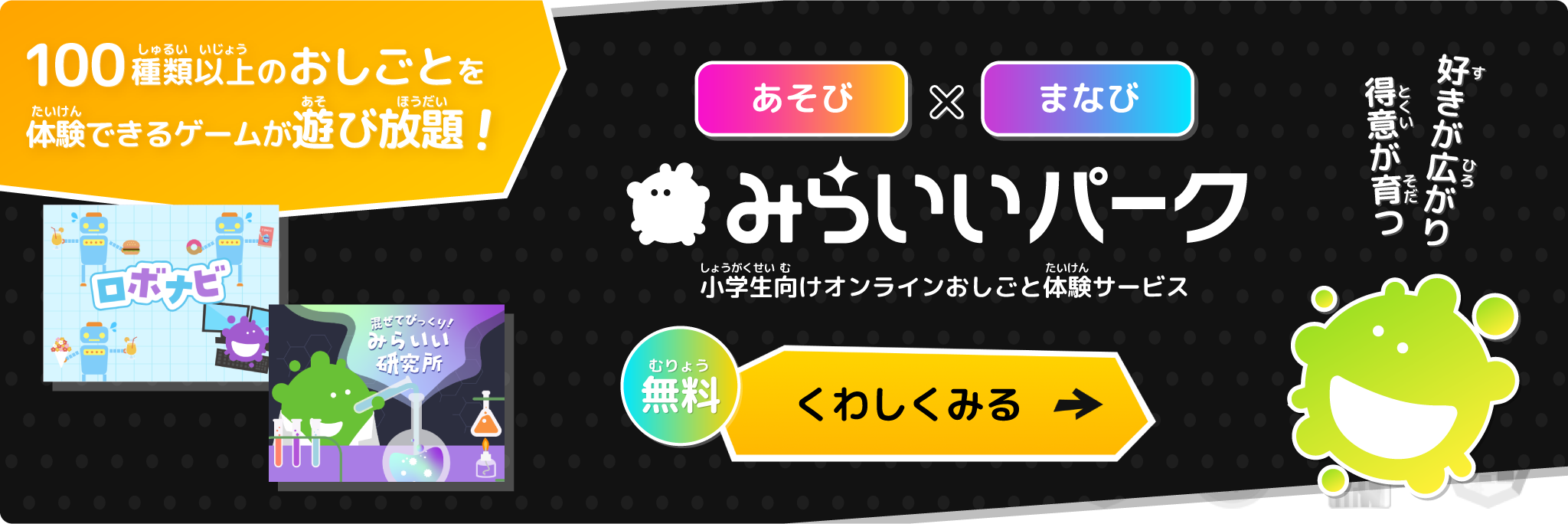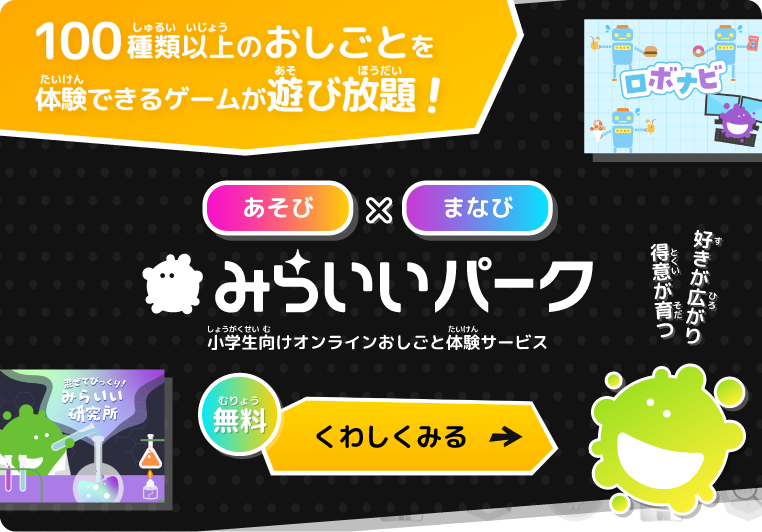オンライン診療のやり方ガイド|初診の流れと子どもの体調急変時の使い方
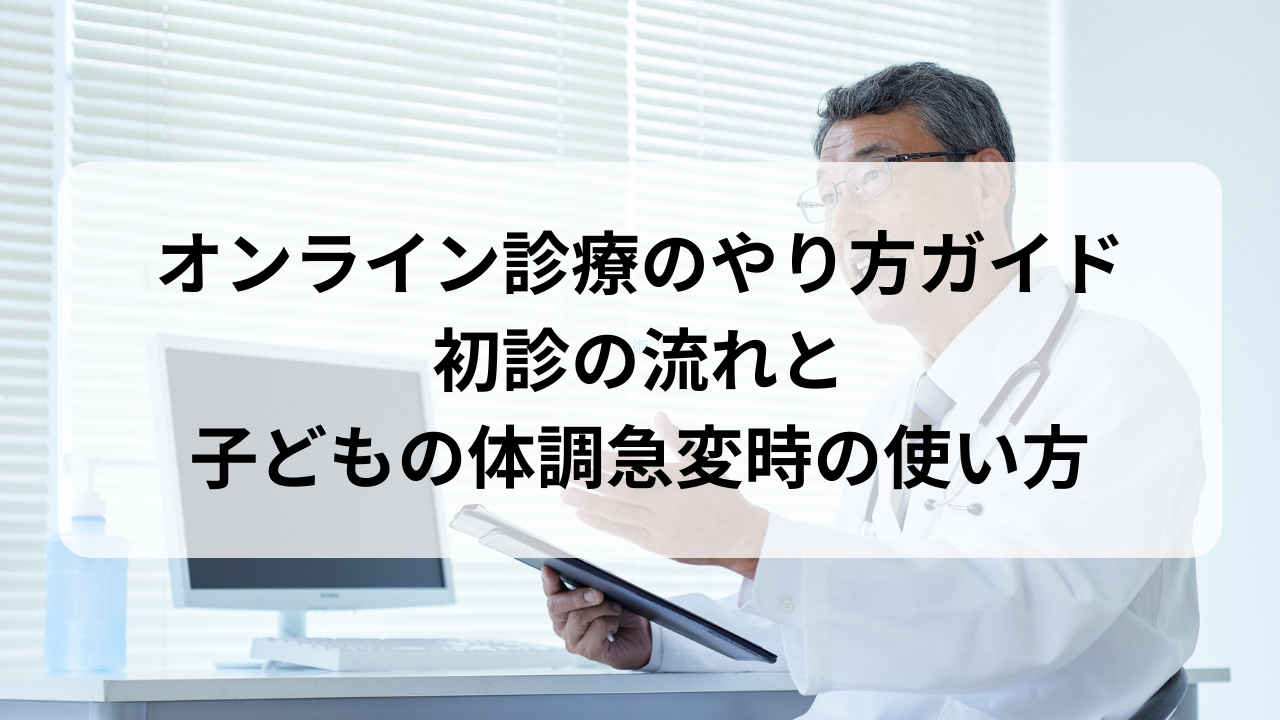
「夜中に子どもが急に熱を出した」「休日に体調を崩したけど、病院はお休み」そんな不安な経験をされた保護者の方は多いのではないでしょうか。
オンライン診療は、スマートフォンがあれば自宅にいながら医師の診察が受けられる仕組みです。
この記事では、オンライン診療のやり方を基本から丁寧に解説します。
オンライン診療はスマホがあればどこでも受診できる

オンライン診療とは、スマートフォンやタブレットなどを使って、自宅にいながら医師の診察を受けられる仕組みです。
病院に行かなくても、ビデオ通話を通じて医師と直接話ができ、必要に応じて薬の処方も受けられるのは心強いですよね。
まずはオンライン診療の基本について理解しましょう。
オンライン診療の基本ポイント
オンライン診療は、インターネット環境があればどこでも受診できるのが大きな特徴です。自宅だけでなく、旅行先や帰省先でも利用可能。
予約から診察、支払い、サービスによっては薬の受け取りまで、すべてオンラインで完結します。
診察はビデオ通話で行われ、医師が患者の顔色や様子を確認しながら診断します。
事前に予約した時間に医師から連絡が来るため、病院に行ったり、待合室で長時間待ったりする必要がありません。
他の患者との接触もなく、感染症をもらうリスクも減らせます。
通院・往診との違いとおすすめの使い方
通院は患者が病院に行って診察を受ける従来の方法です。
往診は医師が患者の自宅まで来て診察する仕組みで、直接の診察や処置が必要なときに利用されます。
オンライン診療は、軽い症状や経過観察が必要なときに便利です。
たとえば「子どもの熱が37度台で元気はある」「いつもの薬がなくなりそう」といった場合に適しています。
一方「高熱で意識がもうろう」「激しい痛みがある」といった緊急性の高い症状の場合、すぐに病院を受診するか、救急車を呼びましょう。
サービスによっては、オンライン診療で相談した後、必要に応じて往診に切り替えられるものもあります。
初診・再診・保険診療のしくみ
オンライン診療では、初診と再診で対応できる内容が異なります。
初診とは、その医療機関で初めて診察を受けることです。
再診は、一度受診したことがある医療機関で2回目以降に受ける診察を指します。
保険診療の対象となる病気や症状には制限があります。
たとえば、高血圧や糖尿病などの慢性的な病気で、すでに診断を受けていて症状が安定している場合は、オンライン診療で保険が適用されることが多いです。
また、軽い風邪の症状や花粉症などのアレルギー症状も対象になります。
一方で、予防医療や健康相談のみの場合は、基本的に保険適用外の扱いとなり、自費負担となります。
ただし、すべての病気がオンライン診療で対応できるわけではありません。
検査が必要な場合や、医師が直接診る必要があると判断した場合は、病院での受診をすすめられることもあるので注意が必要です。
オンライン診療のやり方【準備から受診までの4ステップ】

オンライン診療を受けるための具体的な手順を、
- 事前準備
- 予約と問診票の入力
- 診察を受ける
- 薬の受け取り
の4つのステップに分けて説明します。
初めての方でも安心して利用できるよう、準備から受診、薬の受け取りまでを順番に見ていきます。
①受診前に準備をする
オンライン診療を受けるには、いくつか準備が必要です。
準備として必要なものは、
- スマートフォン
- インターネット環境
- オンライン診療アプリ
- クレジットカード
- 保険証
- 医療証
の5つです。
詳しくみていきましょう。
まず、スマートフォンやタブレットなどの通信機器と、インターネット環境を用意します。Wi-Fiや4G、5Gなどの通信環境があれば問題ありません。
次に、オンライン診療アプリの準備です。
アプリをインストールしたら、アカウント登録に進みます。
氏名、生年月日、住所、電話番号などの基本情報と、クレジットカードの登録を行います。
病院などでは子どもの医療費がかからないため、支払いをしない場合がありますね。
しかし、子ども医療費助成の金額や対象年齢は地域によって異なります。
一時的に支払いをして、後から返金の手続きが必要な場合もあります。
多くのサービスでは、クレジットカードでの支払いとなるため、クレジットカードを手元に準備しておくとスムーズに登録可能です。
また、保険証の写真を撮影してアップロードを求められる場合もあります。保険証も準備しておきましょう。
②予約と問診票を入力する
準備ができたら、アプリから診察の予約を取ります。
希望する日時を選んで予約しましょう。
夜間や休日に対応している医療機関もあるため、都合の良い時間帯を探してみてください。
予約時には問診票の入力が求められます。
問診票には、現在の症状や気になっていること、いつから症状があるか、症状の程度などを記入します。
「昨夜から38度の熱がある」「食欲はあるが元気がない」「3回嘔吐した」など、具体的に書くと医師が状況を理解しやすいです。
また、現在飲んでいる薬やアレルギーの有無、過去にかかった病気なども記入します。
お薬手帳などを手元に置いて事前に情報を整理しておくと、診察をスムーズに進められます。
③ビデオ通話で診察を受ける
予約の時間になると、医師からビデオ通話がかかってきます。
アプリの通知が来たら「応答」ボタンを押して診察を開始します。
診察を受ける場所は、明るく静かな場所を選びましょう。
医師が患者の様子をしっかり確認できるよう、顔がはっきり見える明るさが大切です。
診察では、医師が問診票の内容を確認しながら、さらに詳しく症状を聞いてきます。
子どもの様子を画面に映して、顔色や発疹、喉の赤みなどを見てもらうことも。
聞かれたことには正直に答え、気になることがあれば遠慮せず質問しましょう。
診察時間は一般的に5分から15分程度です。
医師は症状を総合的に判断して、薬の処方が必要かどうかを決めます。
また「この症状なら自宅で様子を見て大丈夫」「念のため病院で検査を受けたほうがいい」といったアドバイスももらえます。
大丈夫と言われた場合でも、どうなったら受診するべきかなど、次の行動の指標を聞いておくと安心できますよ。
④処方箋と薬を受け取る
診察が終わると、必要に応じて処方箋が発行されます。
処方箋の受け取り方は、主に2つ。
1つ目は、薬局で受け取る方法です。
処方箋が自宅の近くの調剤薬局に自動で送信されるサービスもあります。
薬局から「薬の準備ができました」と連絡が来たら、都合の良いタイミングで受け取りに行きましょう。
処方箋が郵送される場合は、受け取った処方箋を薬局に持って行きます。
処方箋の有効期限は発行日を含めて4日間なので、期限内に受け取るようにしてください。
2つ目は、薬を自宅に配送してもらう方法です。院内処方を行っている医療機関では、薬が直接自宅に郵送されることもあります。
外出が難しい場合や、近くに薬局がない場合に便利です。
オンライン診療のやり方【料金と支払い】

オンライン診療を利用する際の料金について、具体的な目安や支払い方法を説明します。
費用面での不安を解消して、安心して利用できるようにしましょう。
診察料と薬代の目安
子どもがオンライン診療を受ける場合、ほとんどのご家庭では医療費助成制度が適用されるため、診察料は無料またはごくわずかで済むことが多いです。
これはオンライン診療でも同じで、対面診療と同じ扱いになります。
ただし、医療機関によっては、システム利用料、アプリ利用料・予約料として数百円〜1,000円程度が追加でかかる場合があります。
これは自治体の助成対象外となることが多いため、事前に医療機関のホームページやアプリで確認しておくと安心です。
また、薬代も、自治体の医療費助成制度により無料または一部負担(数百円程度)になる地域がほとんどです。
オンライン診療で処方箋が発行された場合は、サービスによって薬局で受け取るか自宅へ配送してもらうか選ぶことができます。
薬の配送料は助成の対象外で、通常数百円程度(目安:300〜500円)かかります。
自宅受け取りを選ぶ際は、配送料の有無と金額を確認しておくとよいでしょう。
医療費助成の内容は自治体によって異なります。
何歳まで助成対象か、一部負担金があるか、オンライン診療でも助成が適用されるかなど。これらは自治体の公式サイトで確認できます。
オンライン診療は費用の面でも利用しやすいので、急な体調不良のときの選択肢として覚えておくと安心です。
クレジットカード・オンライン決済の使い方
オンライン診療の支払いは、クレジットカード決済のみという場合が多いです。
アプリにクレジットカード情報を登録しておけば、診察後にアプリ内で自動的に決済が行われます。
決済が完了すると、領収書がアプリ内やメールで送られてくるので、確定申告などで医療費控除を受ける際に利用できます。
クレジットカードを持っていない場合は、デビットカードやプリペイドカードに対応しているサービスを利用しましょう。
ただし、対応しているカードの種類は医療機関によって異なるため、事前に確認が必要です。
保険適用になる場合/ならない場合
オンライン診療でも、条件を満たせば健康保険が適用されます。
保険適用になる主なケースは、慢性疾患の経過観察、軽い風邪の症状、花粉症などのアレルギー症状です。
すでに診断を受けていて、症状が安定している場合に保険診療が受けられることが多いです。
一方で、保険適用にならないケースも。
たとえば、健康相談のみの場合は自費診療となります。
また、医療機関によっては、オンライン診療自体を自費診療としている場合もあるため、事前に確認しましょう。
保険証を持っていない場合や、保険証の有効期限が切れている場合は、全額自己負担となります。
診察前に保険証の有効期限を確認しておくと安心です。
オンライン診療のやり方【どんなときに相談できる?】

オンライン診療で相談できる症状と、対応が難しい症状について具体的に説明します。
どんなときにオンライン診療を利用すればよいか、判断の目安を知っておきましょう。
相談できること
オンライン診療は、軽い体調の変化や、子どものちょっとした不調に対応できます。
たとえば、37度台の微熱、鼻水や軽い咳、のどの痛み、お腹の調子が悪い、軽い皮膚の発疹などが相談できる症状です。
慢性的な病気で定期的に薬をもらっている場合も、オンライン診療が便利です。
「次の受診日まで薬が足りない」「いつもと同じ薬がほしい」といった場合に、病院に行かなくても処方してもらえます。
相談が難しいこと
オンライン診療では対応できない症状もあります。
激しい痛みがある、意識がもうろうとしている、呼吸が苦しい、大量に出血しているといった緊急性の高い症状は、迷わずに救急車を呼ぶか、すぐに病院を受診してください。
また、詳しい検査が必要な場合も、オンライン診療では対応できません。
医師が「直接診察しないと判断できない」と考えた場合は、病院での受診をすすめられます。
骨折やねんざの疑いがある場合、激しい腹痛、けいれんが止まらない場合なども、オンライン診療では適切な対応ができません。
こうした症状があるときは、病院に行くか、救急外来を受診しましょう。
受診をするかどうか判断しにくい時には、子ども医療電話相談(#8000)などの相談窓口を利用するのもひとつの方法です。
#8000は、小児科の医師や看護師に無料で相談できるものです。
症状を伝えると、受診すべきか、自宅で様子を見てよいかのアドバイスをもらえます。
予約不要で、休日や夜間も対応しています。
オンライン診療のやり方【気をつけたいポイント】

オンライン診療は便利なサービスですが、いくつか気をつけるべきことがあります。
オンライン診療を利用する際に知っておきたい注意点をまとめました。
すべての病気には対応できない
オンライン診療は便利ですが、すべての病気や症状に対応できるわけではありません。
ビデオ通話だけで、医師が直接触って確認することができないため、診断の精度には限界があります。
たとえば、お腹を押して痛みの場所を確認する、リンパ節を触って腫れを調べる、聴診器で心臓や肺の音を聞くといった診察は、オンラインではできません。
そのため、医師が「実際に診察が必要」と判断した場合は、病院での受診を指示されることがあります。
また、初めて診察を受ける病気の場合、オンライン診療では対応できないケースもあります。
まずは病院で詳しく診てもらい、その後の経過観察でオンライン診療を利用するという流れが一般的です。
夜間・休日・年末年始は使える病院が限られる
夜間や休日、年末年始に対応しているサービスは限られているので注意が必要です。
そのタイミングでサービスを提供している医療機関もありますが、通常よりも料金が高くなったり、予約が取りにくくなったりすることが予想されます。
予約が取れても、時間通りに来てもらえず、夜中や朝方に対応することになったという場合もあるようです。
便利なサービスですが、タイミングによっては利用できない可能性があることも覚えておきたいですね。
迷ったときは、近くの医療機関にも相談を
「オンライン診療を受けるべきか、病院に行くべきか」と迷ったときは、前述した子ども医療電話相談(#8000)に頼ってみましょう。
また、近くのかかりつけ医に電話で相談してみるのもよいでしょう。
日頃から子どもを診てもらっている医師であれば、これまでの経過を知っているため、的確なアドバイスがもらえるかもしれません。
オンライン診療のやり方に関するよくある質問

オンライン診療について、多くの方が疑問に思うことをまとめました。
利用前の不安を解消して、スムーズに利用できるようにしましょう。
長期休みや夜間の体調不良が心配なときは?
子どもの体調不良は、ゴールデンウィークやお盆休み、年末年始などいつでも起こる可能性があります。
そういった時に備えて、あらかじめオンライン診療アプリに登録しておくと安心です。
オンライン診療アプリには、キッズドクター(iPhone版・Android版)、ファストドクター(iPhone版・Android版)などがあります。
オンライン子ども診療はDoor.というアプリを使用します(iPhone版・Android版)。
登録しておけば、必要なときにすぐに予約もできます。
アカウント登録や保険証の登録には少し時間がかかるため、元気なときに済ませておくとよいでしょう。
複数のオンライン診療サービスに登録しておくのもひとつの方法です。
ひとつのサービスが混雑していても、別のサービスで予約が取れることがあるかもしれません。
往診との違いと上手な使い分け方を知りたい
使い分けの目安としては、軽い相談や症状の確認はオンライン診療、直接の診察や処置が必要なときは往診が適しています。
たとえば「熱はあるけど元気がある」「薬をもらいたい」といった場合はオンライン診療。「高熱で動けない」「吐き気が強くて水分が取れない」といった場合は往診を検討するとよいでしょう。
オンライン診療は、スマートフォンやタブレットを使って、自宅から医師に相談できる仕組みです。
ビデオ通話で診察を受けるため手軽ですが、医師と直接会うことはありません。
往診は、医師が患者の自宅まで来て診察します。
医師が直接、聴診器で音を聞いたり、触れたりした診察が可能です。
また、往診の料金はオンライン診療よりも高くなります。
医師の交通費や夜間・休日の加算があるためです。症状に合わせて、適切な方法を選びましょう。
オンライン診療でも往診してもらえるの?
オンライン診療で相談した後、医師が「直接診察したほうがよい」と判断したときに、必要に応じて往診に切り替えられるサービスもあります。
ファストドクターがオンライン診療と往診どちらも対応しています。
往診の対応エリアは限られているため、お住まいの地域が対象かどうかを事前に確認しておきましょう。
往診に切り替える場合は、追加の料金がかかります。
オンライン診療で安心の子育てを
オンライン診療は、スマートフォンがあればいつでもどこでも医師に相談できる便利な仕組みです。
夜間や休日の対応は限られているため、事前の登録がおすすめです。
子どもの急な体調変化に備えて、オンライン診療という選択肢を知っておくことで、いざというときに落ち着いて対応できます。
かかりつけ医への通院と組み合わせながら、上手に活用していきましょう。
これからの時期に備えて、遊びや睡眠で風邪を予防していきましょう。風邪予防に参考になる記事はこちらから。
小学生の風邪予防はこれ!7つの習慣と具体策を紹介!
寒い冬でも外遊び!外遊びのメリットとおすすめの遊びを紹介!
子どもの睡眠時間が足りてない?!「良い眠りのコツ」とは?

%20(1).jpg)







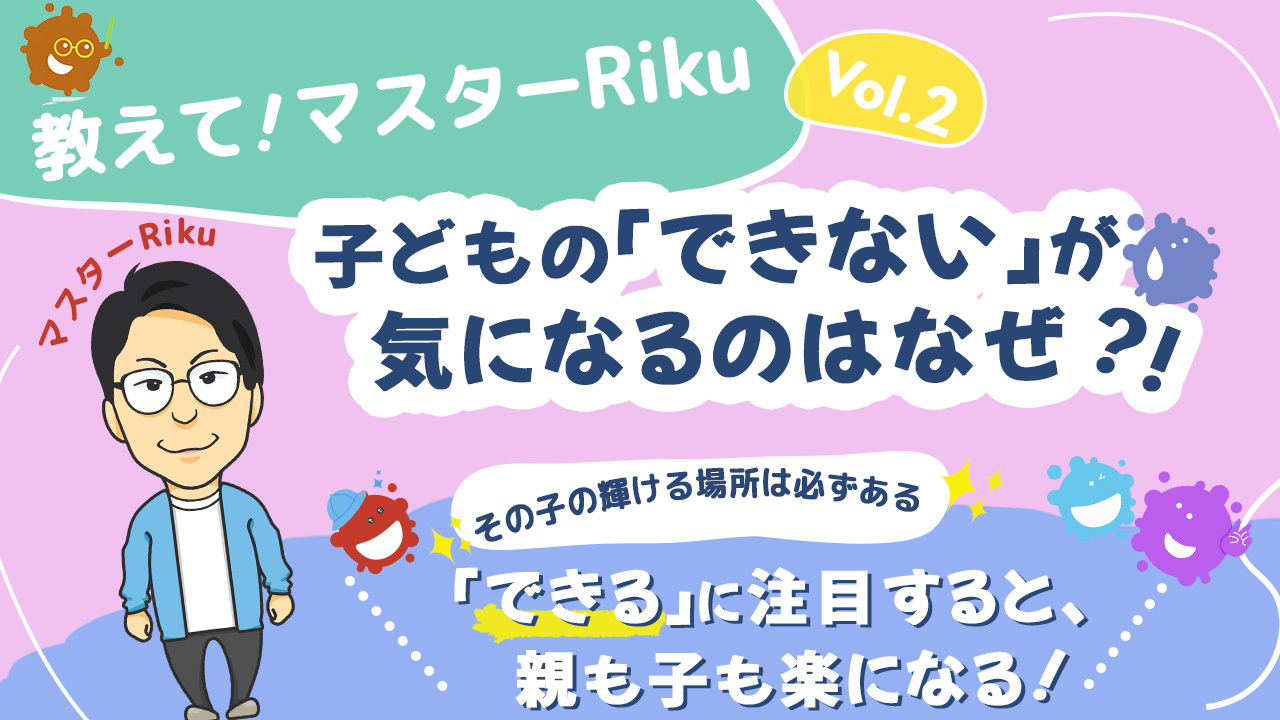
.jpg)

%20(1).jpg)