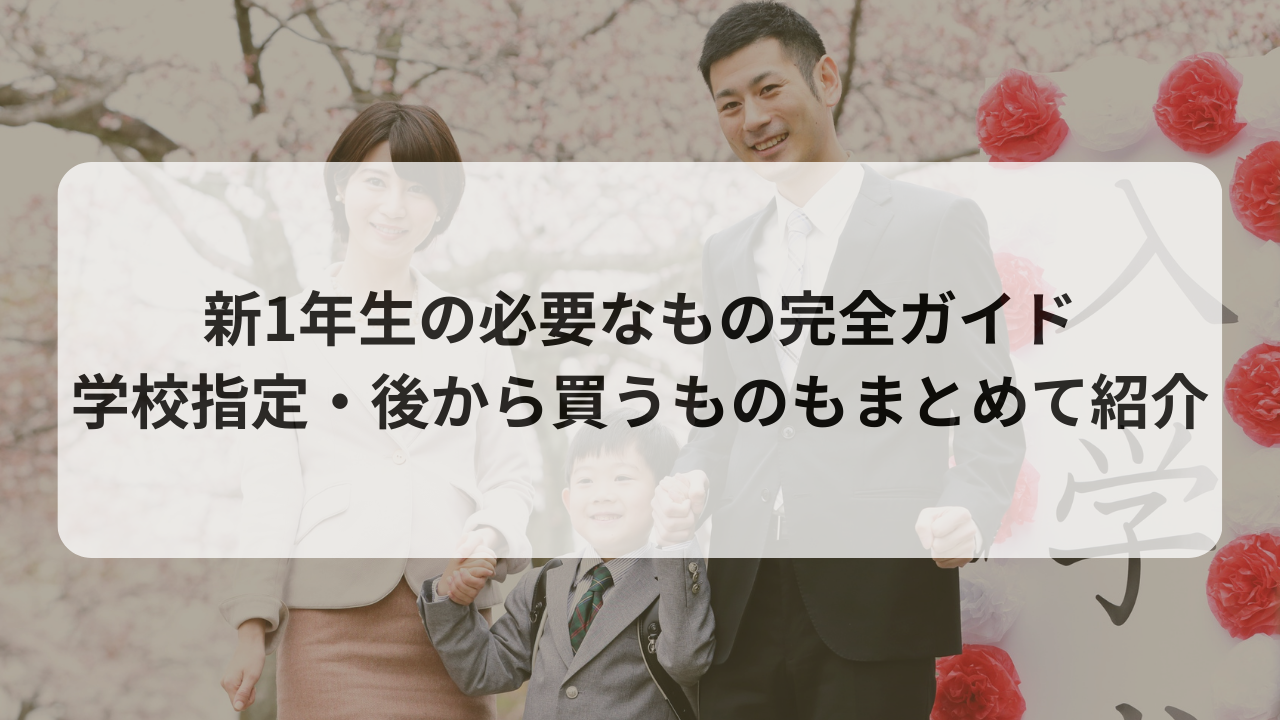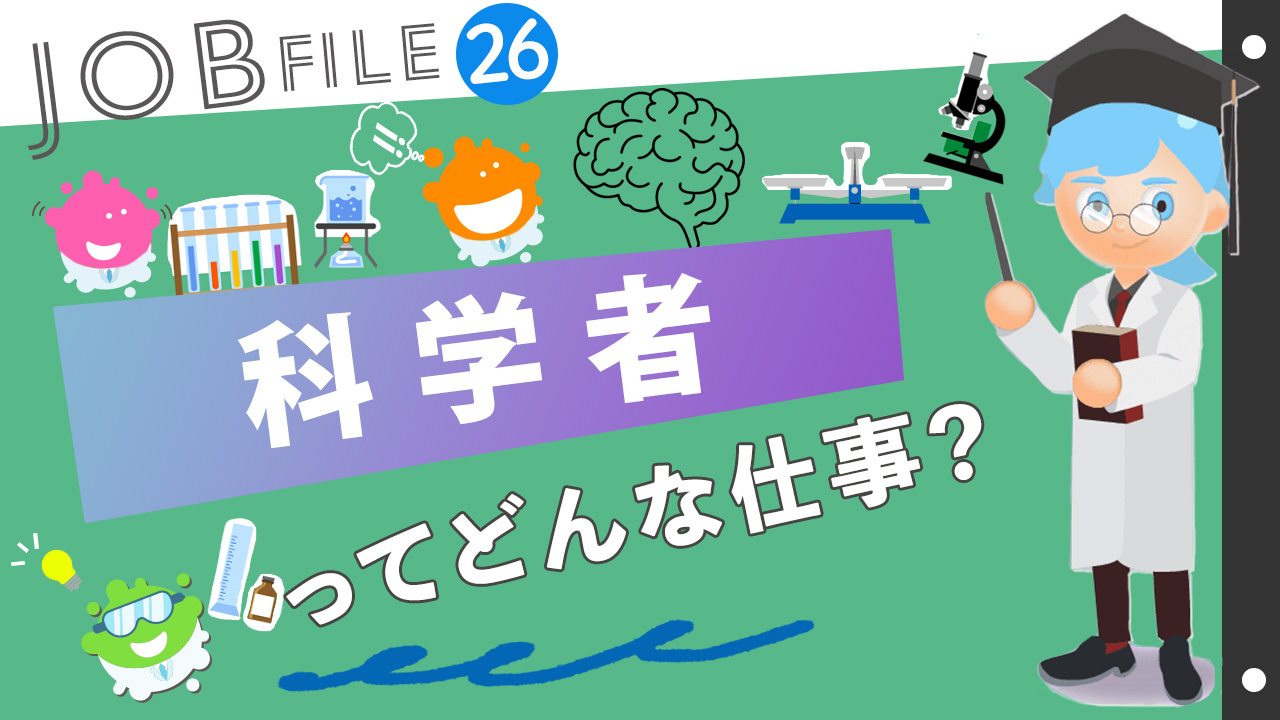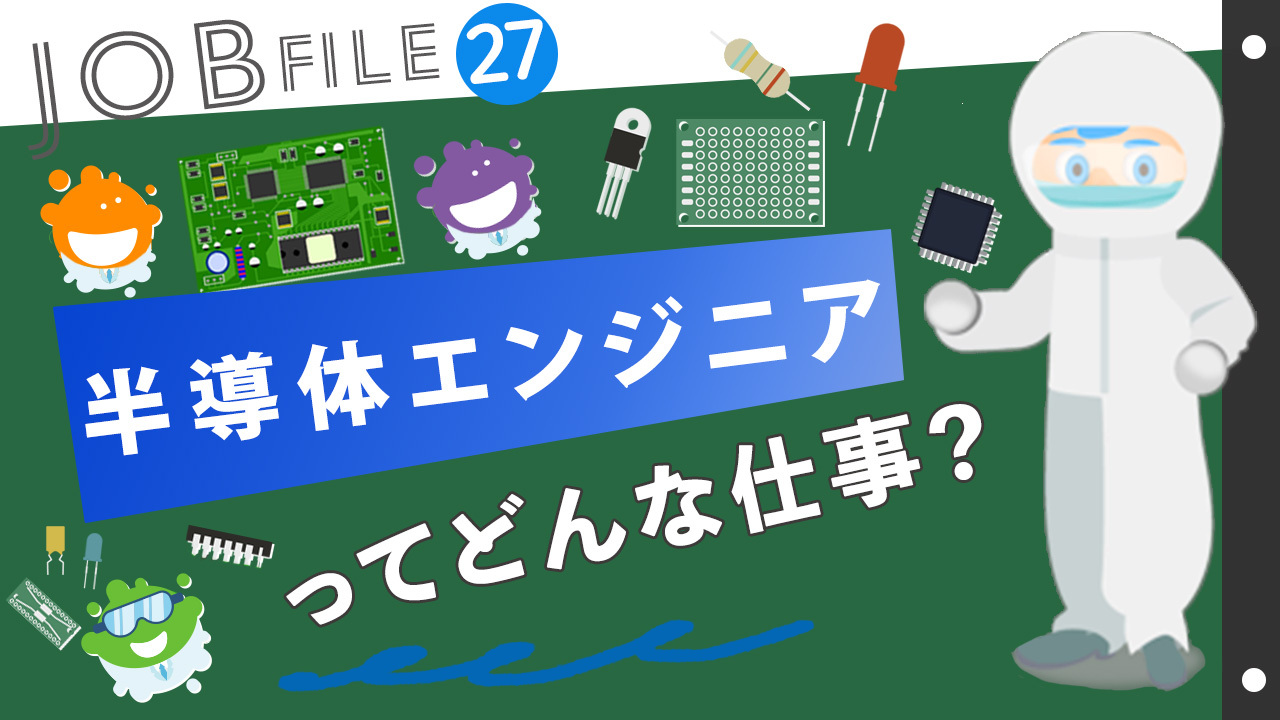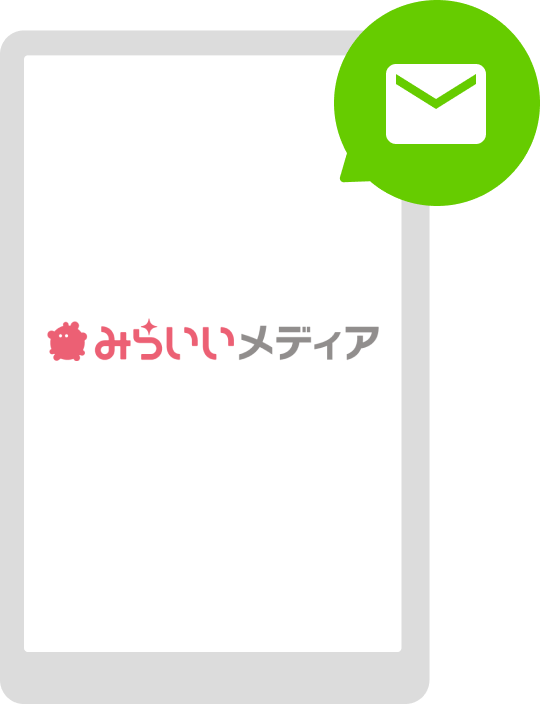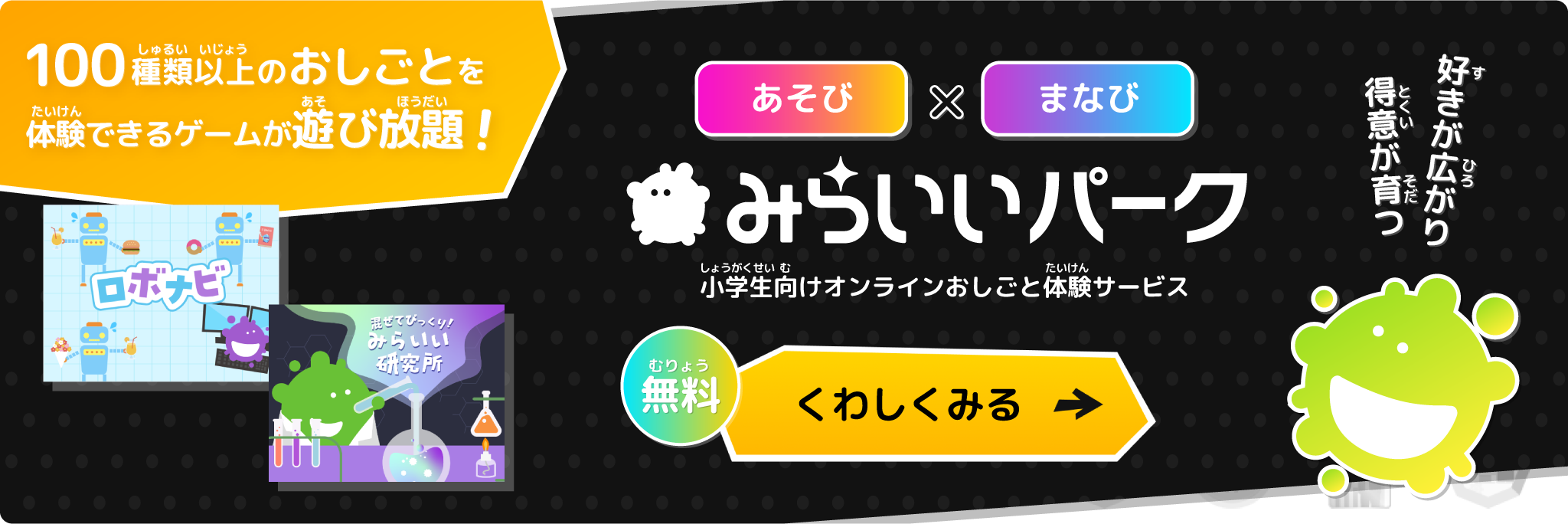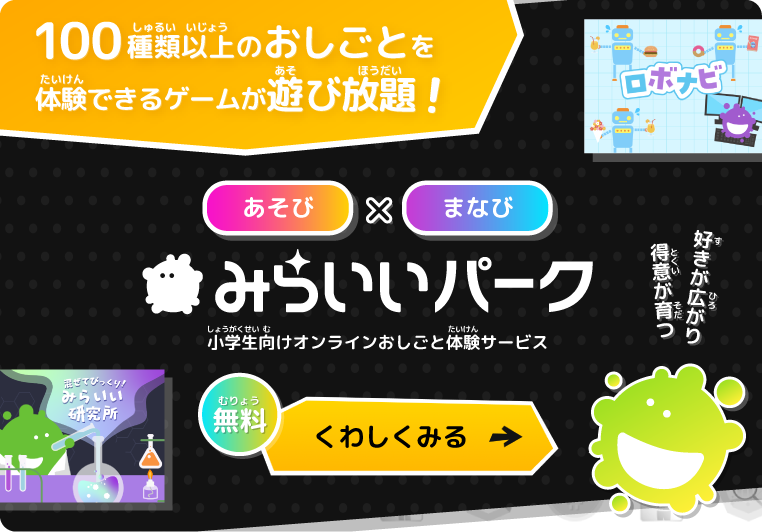アドラー心理学を子育てに活かそう!「ほめない」「しからない」子育てとは?

「ほめる子育て」に疲れていませんか?ほめるところを探すのも大変ですし、ほめないと行動しない子どもになっても困りますよね。
今回ご紹介するのはアドラー心理学を活用した「ほめない」「しからない」子育てです。実際にどんな声かけをしていくのかもご紹介します。子どもが自立し、自分で判断できるようになるために、きっと役立つでしょう。
「ほめる」「しかる」子育てのデメリット
「ほめる子育て」や「しかる子育て」は聞いたことがあるかもしれません。
90年代に、日本の子どもたちの自己肯定感が低いというアンケート結果を受け、自己肯定感の高かった欧米の教育方法が取り入れられたことが始まりのようです。
しかし、もともとの文化背景が違うにも関わらず、「ほめる子育て」を取り入れてしまったがために、弊害もあると言われるようになりました。
それは
- 一人ではやらなくなる
- ほめられないとやらない
- 自分のことだけ考えるようになる
の3つです。
「ほめてほしい」がためにその行動をするようになってしまったり、ほめてもらうのが当たり前になってきてしまったり。
年齢が上がってくると「ほめる」機会も少なくなっていきます。
その行動が「ほめられるかどうか」を気にするようになり、「自分がどうしたいか」ではなく「大人がどう思うか」を基準に自分の行動を決めてしまいかねません。
子どもを育てるためには「縦」の人間関係よりは、一人の人間として認め、接していく「横」の人間関係も必要です。
その「横」の人間関係から子育てに向き合っていくのがアドラー心理学の考え方です。
アドラー心理学は「勇気づけ」の子育て

アドラー心理学では親と子どもの関係は「横」です。
上の立場からする「ほめる」「しかる」はしません。
代わりに「勇気づけ」と呼ばれることをします。
「勇気づけ」とは一体何でしょうか?
「勇気づけ」とは
アドラー心理学における「勇気づけ」とは「自分や他者に困難を克服する活力を与えること」です。
アドラー心理学では人間は変化し成長していくものだと考えます。
そのために困難にぶつかることは避けられません。
困難にぶつかったときにされることが「勇気づけ」です。
ここでの「勇気」とは自ら行動しようとする力のことです。
「一歩前に踏み出そうとする気持ち」と言い換えることもできるかもしれません。
新しいことを始めようとするとき、失敗に正面から向き合うとき、失敗からの経験を踏まえて前に進もうとするとき、「勇気」は大切です。
アドラー心理学では、「勇気」を持てるのは「自分には価値があると感じられるとき」であり、「自分に価値がある」と感じられるのは「自分の行動は共同体に有益だと感じられるとき」であるとしています。
一方、「勇気」をもって行動に起こそうとするときに襲われるのが「勇気くじき」です。
それは誰かの言葉であったり、自分の心の声であったりします。
例えば、新しいことを始めようとするとき。
- どうせうまくいかない
- 私よりうまくできる人がいる
- やっても無駄だ
- 忙しくてできない
- 新しく始めなくてもこまらない
などが頭に浮かんでこないでしょうか。
私たちの脳は「生きていくこと」が最優先だと言われています。
そのため、新しいことを始めることは「現状ではなくなる」、つまり「安全ではない」と脳が判断し、その行動をストップさせるような考えが出てきてしまいます。
「失敗したくない」「嫌われたくない」という思いは「勇気くじき」の一種です。
しかし、子どもの成長のためには、自分で決め、挑戦していく勇気をもって欲しいですね。
そのために親ができる「勇気づけ」の声かけがあります。
「勇気づけ」の声かけの効果
「勇気づけ」の声かけは「ほめる」とは違って「横」の関係、つまり子どもをコントロールしようとしない関係です。
子どもを一人の人間として尊重し、信じることから始まります。
「勇気づけ」の声かけの効果としては、下記のものがあります。
- 親も子どもも自己肯定感があがる
- 信頼関係を築くことができる
- 次への行動を促すことができる
その行動をする要因が外的なものになる「ほめる」とは違って、「勇気づけ」は子どもの心に訴えかけ、内的要因としての行動の動機になりえるでしょう。
「勇気づけ」をする際のポイント
「勇気づけ」をする際のポイントは下記です。
- 子どもへの「共感」「信頼」「尊敬」を大事にする
- コントロールしようとしない
- 結果だけに着目しない
- 条件にかかわらず、存在そのものを尊重する
子どもと親の関係は、あくまでも「横」です。
そのため、相手に「共感」し「信頼」「尊敬」することが大切です。
たとえ努力をしたからといって、必ずしも成功するとは限りません。
「成功したからほめる」では子どもとの関係は「縦」になってしまい、「勇気づけ」にはならないため、「結果」だけではなく「過程」や「姿勢」にも着目することが必要です。
また、失敗した時にこそ「勇気づけ」はその力を発揮します。
そこには「親の言うことを良くきくから」「勉強するから」「良い子だから」という「条件付き」ではなく、「存在してくれるだけでありがたい」という子どもを尊重する精神が必要です。
「勇気づけ」の具体的な声かけ例

では、具体的な「勇気づけ」の声かけを見ていきましょう。
子どもが何かをしてくれた時
「ほめる」だと「えらいね」「すごいね」になりますが、「勇気づけ」の声かけは
- 「〇〇してくれてありがとう!」
- 「〇〇してくれて助かったわ!」
- 「〇〇してくれてうれしい!」
と気持ちを伝える言葉になります。
感謝の気持ちを伝えましょう。
子どもがテストで70点を取ったとき
「どうして70点だったの?」では取れなかった30点に意識を向けています。
「勇気づけ」では「できていること」に意識を向けて声かけをします。
たとえば
「7割は理解できているね。どうやって勉強したの?」
「頑張って解いたけど、難しかったんだね」
「勉強していたの、見てたよ!」
などです。
子どもが失敗したとき
子どもが何かに失敗した時こそ「勇気づけ」が重要です。
子ども自身も「失敗した」と思っているので、そこに追い打ちをかけるように「なんで失敗したの!」などとは言わないようにしましょう。
まずは「失敗は悪いことではない」と親も子どもも認識することが大切です。
「失敗」は「成功するための経験を積んでいる」と考えてみましょう。
「失敗」は誰にでもあることであり、悪いことでも怖いことでもありません。
むしろ、「何もしない」ことを選ばずに、「挑戦した」「やってみた」ことは素晴らしいと言えます。
子どもと一緒に「では次はどうしたらいいか」を一緒に考えていきましょう。
活用できるフレーズ10選
ここでは、活用できるフレーズをご紹介します。
「ありがとう!」
何かをしてくれた時だけではなく、「生まれてきてくれてありがとう」と伝えてみましょう。
「大好き!」
子どもの存在が「大好き」だけではなく、子どもが作った物などを「お母さんはこれ大好き」と伝えても良いですね。
「うれしい」
「ほめる」代わりにも使いやすいフレーズです。
たとえば、親が電話をしている間に、静かに待ってくれていたら「静かに待ててえらいね」ではなく、「静かにしてくれてうれしい。ありがとう」です。
「大丈夫」
こちらは分かりやすい「勇気づけ」のフレーズではないでしょうか。
「失敗しても大丈夫だよ」「一緒に方法を考えるから大丈夫だよ」などと伝えたら、子どもの心も軽く、暖かくなりそうですね。
「ここは良くなってるね」
「できていないところ」ではなく、「できているところ」に意識を向けるフレーズです。
人は注目された行動を繰り返す習性があるそうです。
つまり、「できていないところ」ばかりに注目してしまうと、それを繰り返してしまうということになります。
「できているところ」は、再現することは簡単だと言われているため、ぜひ「できているところ」に注目しましょう。
「応援してるよ」
「頑張れ」と言われるよりも「応援してるよ」と言われる方が、心の距離が近いように感じないでしょうか?
また、すでに頑張っている子どもに「頑張れ」というと追いつめてしまうかもしれません。
「あなたの頑張りは知っているよ、そのうえで応援しているよ」と伝えると、追いつめることなく寄り添える言葉になるでしょう。
「楽しみにしているよ」
「楽しみにしているよ」と伝えることで、子どもが自分の行動は人の楽しみにもなりえる、と認識できます。
それは、「自分は人の役に立てる」と意識し、自分の価値を感じられるものになるでしょう。
「信じてるよ」
人に信じてもらうことは、とても勇気が湧いてくるものです。
ぜひ積極的に伝えましょう。
「頼りにしているよ」
「縦」の関係ではなかなか口にできないフレーズです。
「横」の関係である、「あなたを一人の人間として頼りにしている」と伝えることは、子どもの自立にもつながるでしょう。
「見てるよ(見守っているよ)」
「見てくれている」ことは「自分のことを分かってくれている」ことにもつながります。
ひいては親と子どもの信頼関係にも良い影響があるでしょう。
子どもが社会の一員として生きていくためにアドラー心理学を活用しよう
アドラー心理学を活用した、子どもへの「勇気づけ」の声かけは、難しいものではありません。
子どもと「横」の関係であることを意識し、普段から信頼関係を築き、子ども自身が「自分は価値がある」と感じられるような声かけをしていくことです。
「ほめる」「しかる」こととは違って、子どもの行動を変えるのに即効性はありませんが、長い目で見て「勇気づけ」の声かけは、子どものためになるでしょう。
まずは「ありがとう」から始めてみませんか?
お子さまの個性に合わせた体験ができるオンラインのプログラミングワークショップはこちらから!
【オンライン開催】子どもの"やってみたい”からはじめる!小学生のプログラミング無料体験!
プログラミング教室受講生の子どもたちのインタビューはこちらから!
「楽しい」からこそ「自分でやりたい!」そしてスケジュール管理までできるように
【まるで別人】学校のテストの点数が100点に!?
プログラミングに熱中!「やりたいことをやる」ことで育まれるチャレンジ精神
「まあ、やってみましょう」が口癖に!自分を認めてくれるから失敗を恐れず試行錯誤できる!
モンテッソーリ教育や国際基準の「子育て」に関する記事はこちらから!
!モンテッソーリ教育とは?おすすめする理由
国際基準の「子育て」〜究極の目標、子供の自立。実は親の自律が鍵だった〜
国際基準の「子育て」〜好きなこと探し〜
国際基準の「子育て」〜好きなことを探して、見つかったら〜








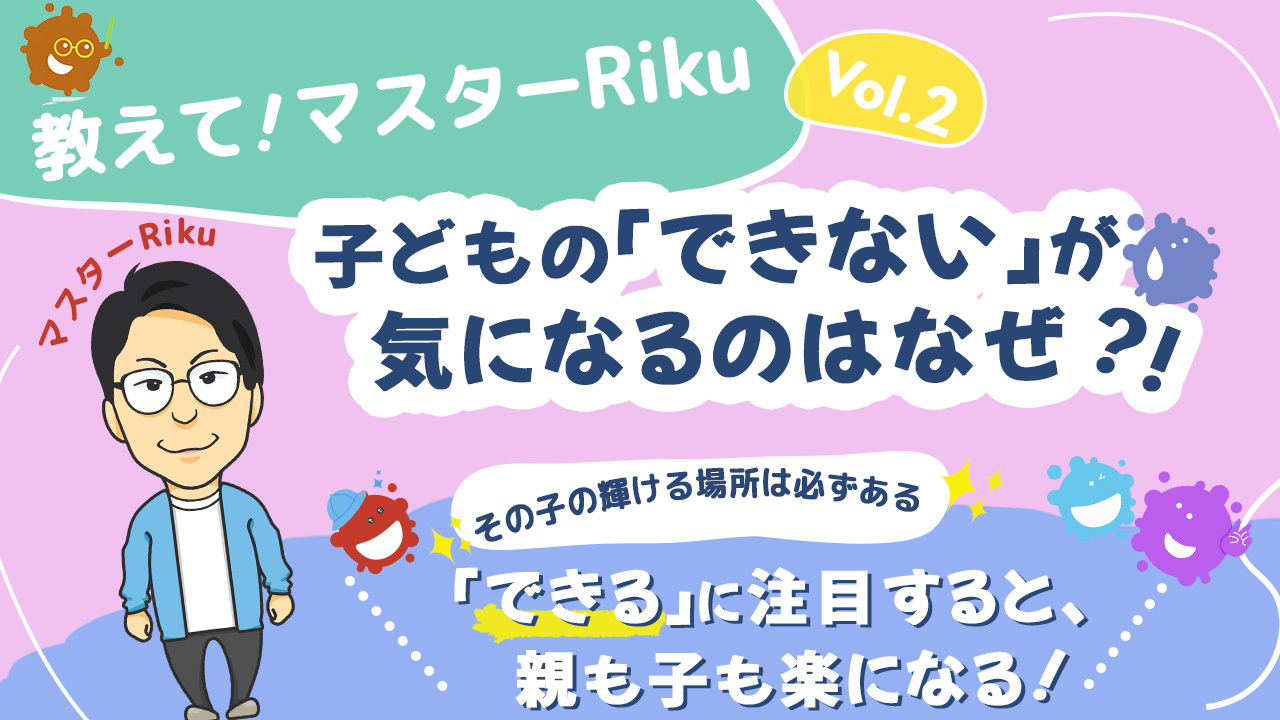
.jpg)

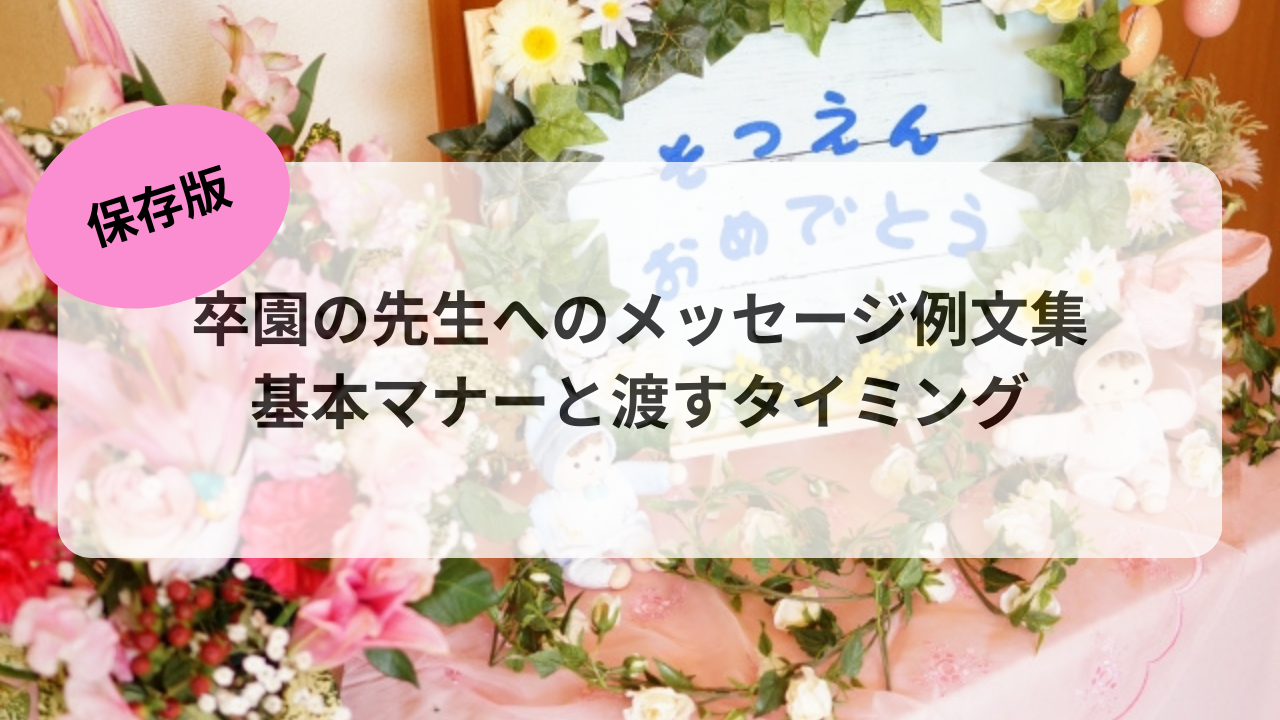
%20(1).jpg)
.png)