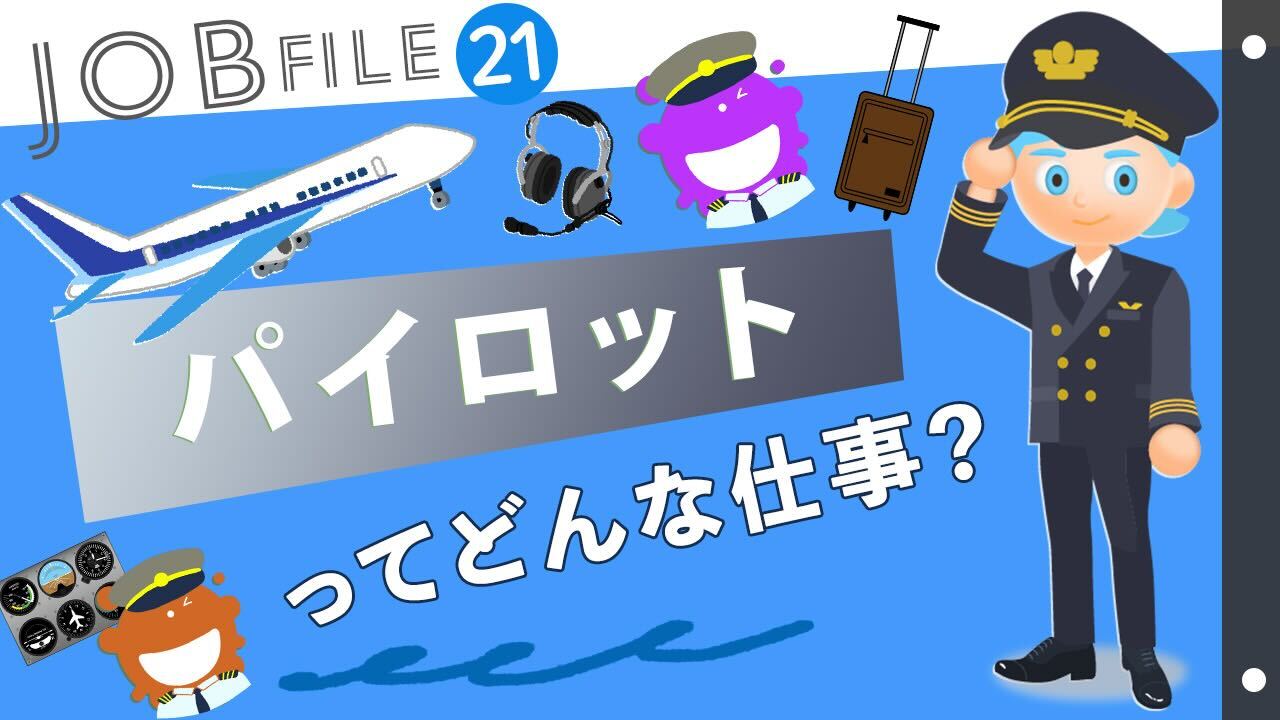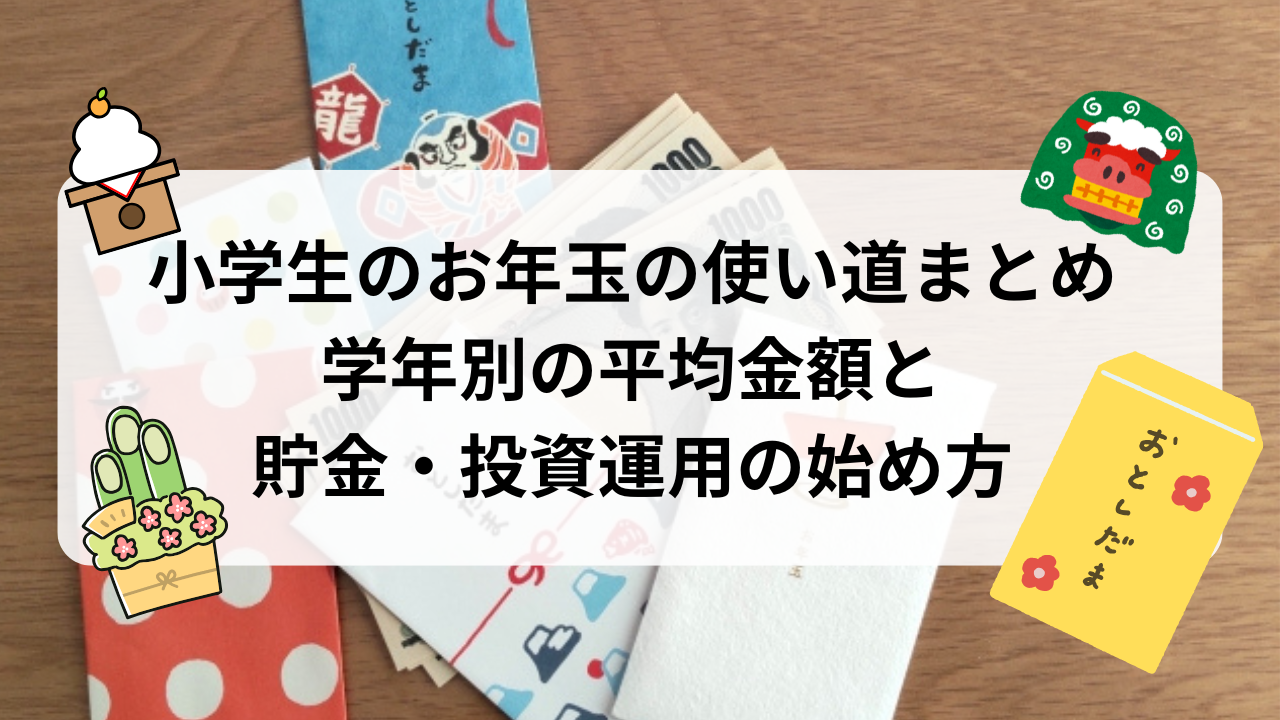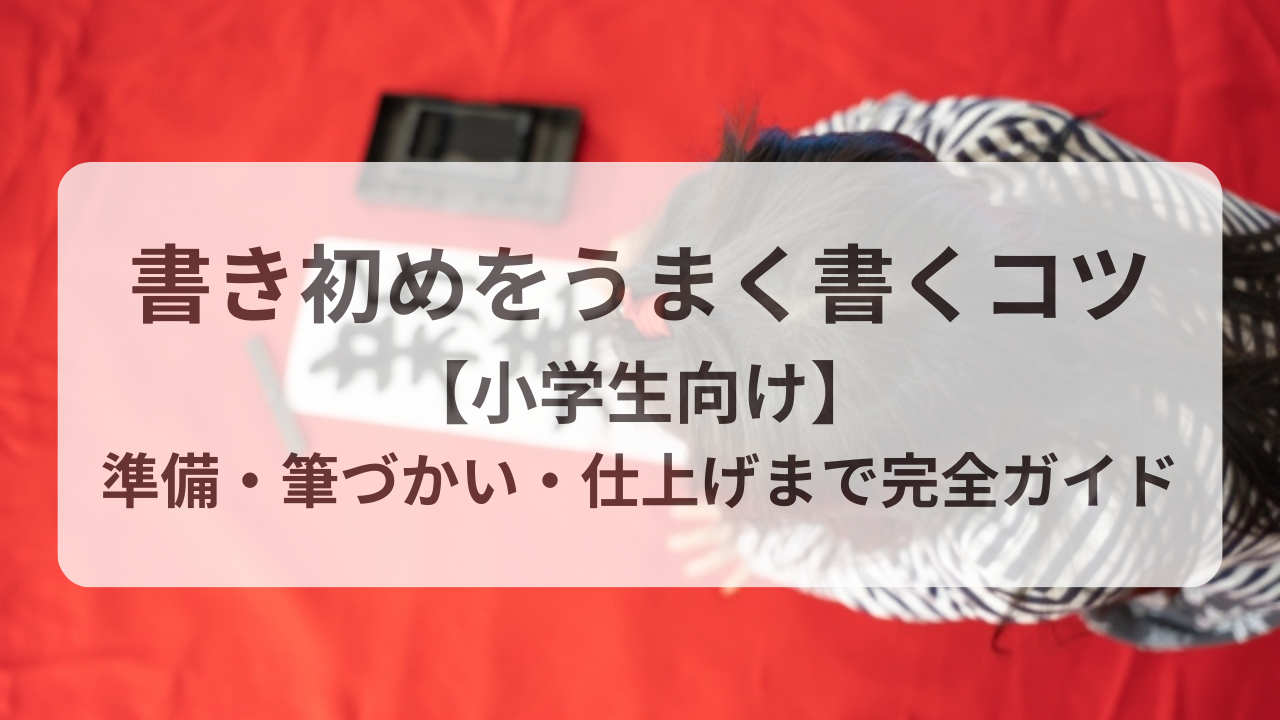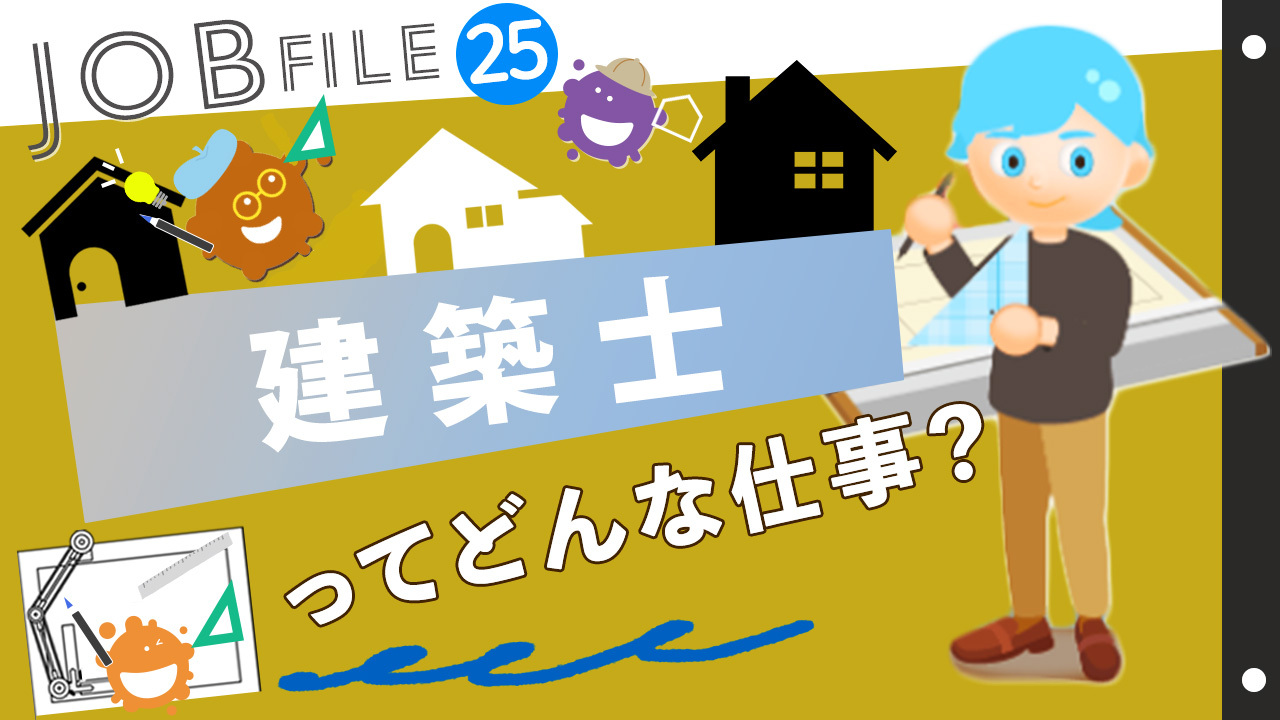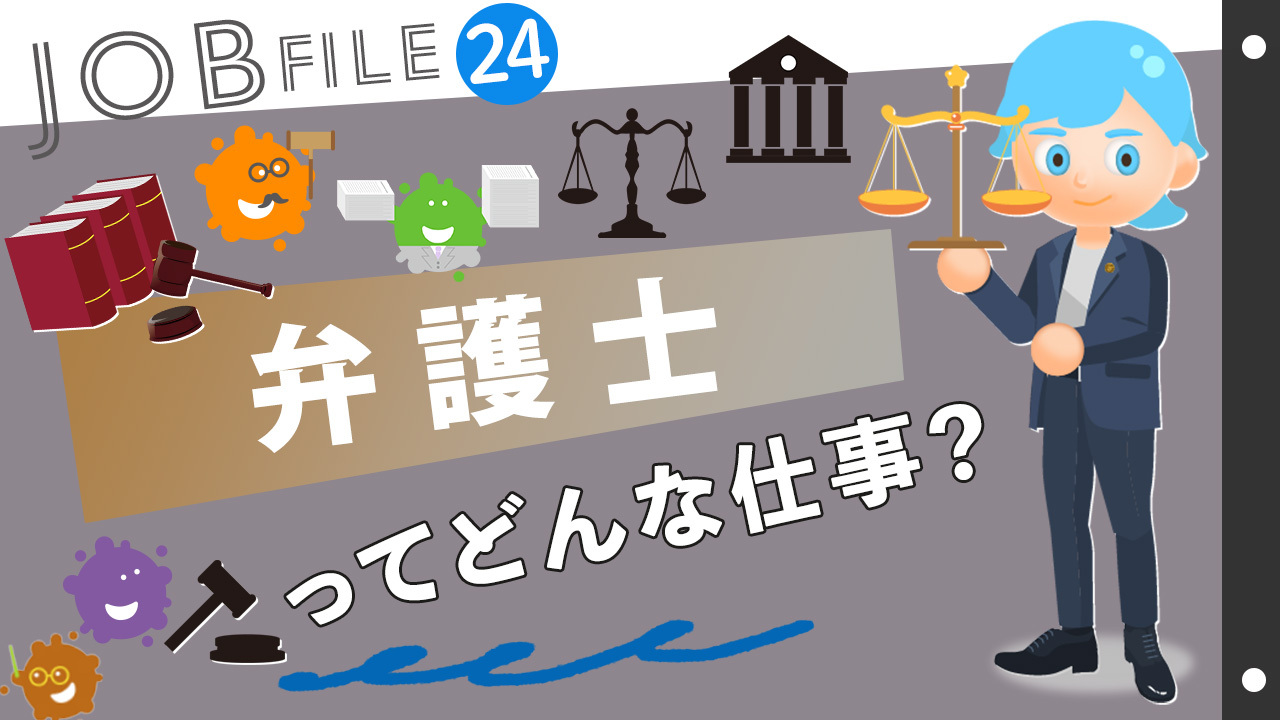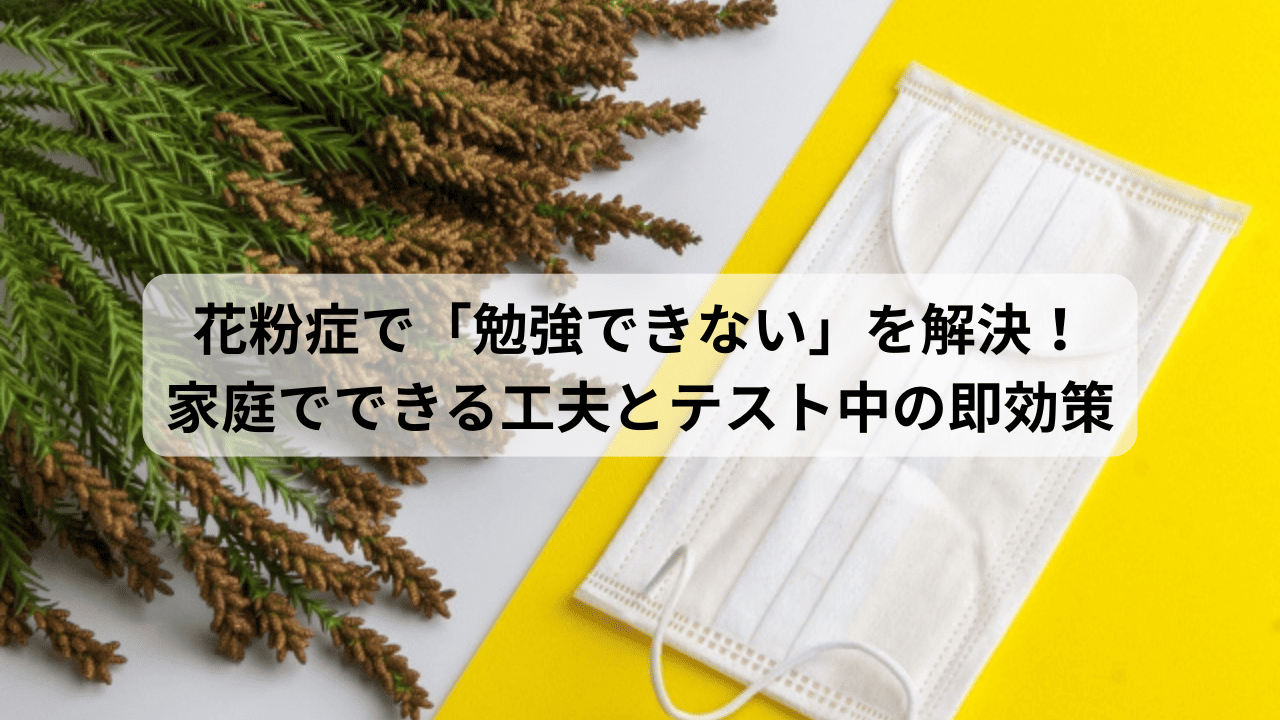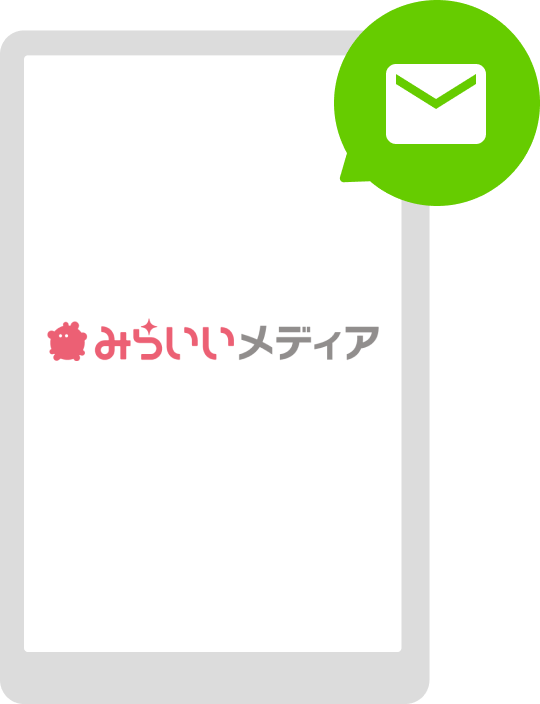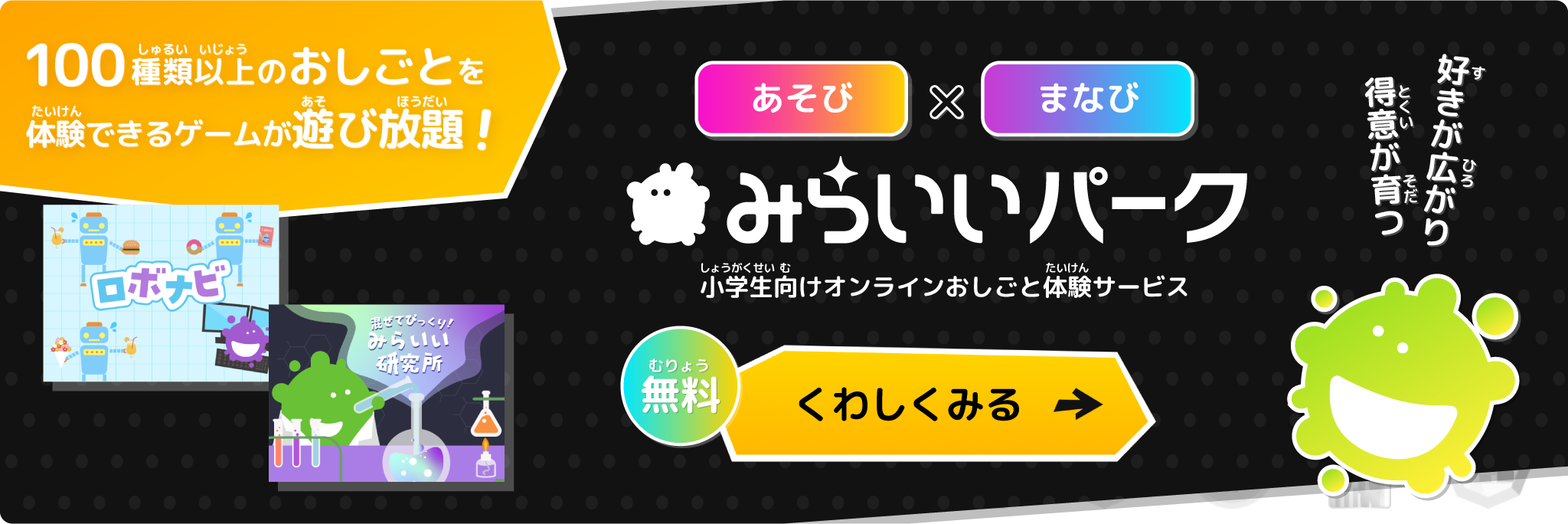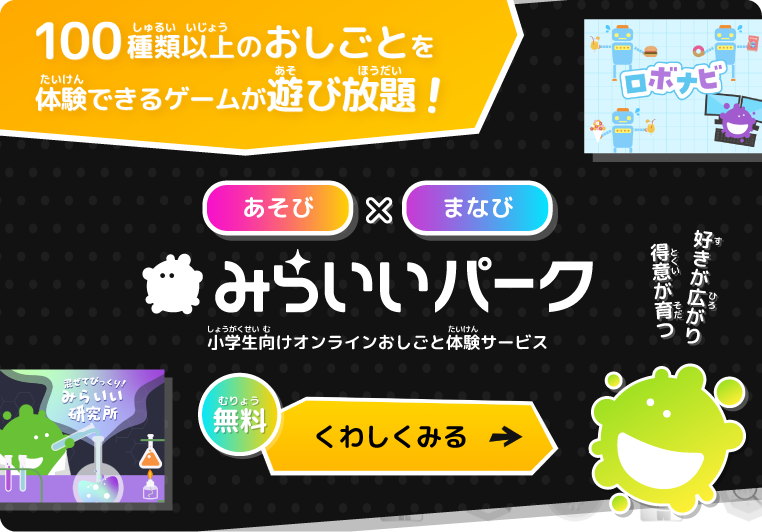SDGs2飢餓をゼロに|現状・課題と取り組み事例も解説

SDGs2は「世界から飢餓をゼロにする」という取り組み。全世界の人の食料事情に関する重要な課題です。
ここでは、この取り組みの現状や課題をご紹介します。どんなアクションが起こせるか、考える手立てにしてみてください。
SDGs2 飢餓をゼロにとは?

まずは、SDGs2の基礎知識について知っておきましょう。世界や日本の飢餓の現状についても説明しています。
SDGs目標2「飢餓をゼロに」の意味
「SDGs2.飢餓をゼロに」とは、世界中の人々が食べ物に困らない状況を目指すための目標です。しかし、世界には、常に食べ物に困っていたり、栄養バランスが偏っていたりと飢餓で苦しんでいる人が存在しています。
SDGs2は、そのような飢餓で苦しむ人たちを1人でも少なくするために掲げられた目標と言えるでしょう。
これですべてが分かる!【SDGs 2.飢餓をゼロに】とは?事例と家庭でできることを紹介
世界・日本における飢餓の現状
国連の5つの専門機関が報告したデータによると、2024年には世界の人口の約8.2%、およそ6億7,300万人が飢餓状態にあると示されています。数字だけを見ると、2023年の8.5%、2022年の8.7%から減少しています。
しかし、アフリカと西アジアの地域で飢餓の拡大が続いており、決して改善しているとは言えません。
一方、2020年の日本における相対的貧困率は15.7%で7人に1人、飢餓を経験した人は5.1%と、20人に1人が飢餓状態にあることが確認されています。具体的な数値で表すと、2020時点の日本人人口は1億2,713万人なので、飢餓を経験した人は約635万人と考えられます。
参照元: Spaceship Earth(スペースシップ・アース)、FAO駐日連絡事務所
飢餓が起こるのはどんな事が主な原因?

では、なぜ飢餓が起こるのか、主な原因はどのようなものでしょうか。
貧困と食料へのアクセス不足
飢餓の原因のひとつとして、慢性的な貧困が挙げられます。
特に、開発途上国では仕事に就ける可能性が低く、低賃金で働いている人が多く存在しています。そのため、食料を十分に入手できず、飢餓状態になってしまうのです。
また、農業で収入を得ている人は、土地や肥料などを確保することが難しく、十分な農作物を収穫できません。収入を得られない→食料が買えない→飢餓状態、という負の連鎖になってしまうのです。
気候変動や自然災害の影響
気候変動によって起こる洪水や干ばつなどの自然災害の影響も、飢餓の原因と言えるでしょう。
災害が起きれば、農業を生業としている地域に住む人は、安定した農作物の供給が困難になります。たとえば、干ばつが起きると使える水の量が減るため、当然農作物も育ちません。現金収入を得られず、飢餓状態に陥ってしまいます。
紛争や社会的不安定さ
国内外の紛争も、飢餓状態を引き起こす主な原因です。
紛争が起きると家や農地を失うだけでなく、難民キャンプでの生活を余儀なくされます。
たとえ紛争が終わったとしても、元の生活に戻れる可能性は限りなく低いでしょう。適切な支援を受けられない場合もあるため、食料を確保することが難しくなり、飢餓状態になってしまうのです。
食料ロス・フードロスの問題
食料ロス・フードロスも、SDGs2を達成するにあたって避けられない課題です。
飢餓が拡大しているにもかかわらず、飢餓問題は、実は食料が足りないという理由で起こっているのではありません。世界中の人々が十分に食べられる食料が生産されているのですが、そのうちの3分の1が食品ロスとなっていることが分かっています。
先進国では食べ残しや賞味期限切れなどで多くの食料が廃棄されており、それが飢餓の原因のひとつとなっているのです。
参考元: World Food Programme
私たちができることに関しては、以下の記事も参考にしてください。
いま話題!【SDGs2.飢餓をゼロに】とは?私たちができることも紹介
食品ロスについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
”食品ロス”の現状と”いまから始めるSDGs”4つのことを紹介!
「SDGs2.飢餓をゼロに」の世界の取り組み

SDGs2を実現するため、世界ではさまざまな取り組みがなされています。どのような活動を行っているのかチェックしてみましょう。
国連WFPの活動
WFP(国連世界食糧計画、World Food Programme)は、飢餓のない世界を目指して活動する国連の食料支援機関です。
具体的な活動内容として、
- 緊急事態の食料支援
- 栄養改善と社会的弱者の支援
- 小規模農家の支援
などが挙げられます。
紛争や自然災害が起きた際には、現場にいち早く駆け付けて食料支援を行うほか、場合によっては、被災者が食料を選べるように現金給付や食料引換券を配布しています。
また、5歳未満の子どもや妊婦、高齢者といった社会的弱者に対しては、栄養のある食品や補助食を提供。栄養を改善し、健康を支えています。
そのほか、小規模農家の農業研修や技術支援も実施。設備の整備や土壌改善、農作物の栽培技術の伝授を行い、農業の発展をサポートしています。
FAOの活動
FAO(国連食糧農業機関、Food and Agriculture Organization of the United)はWFPと並んで、飢餓をなくすための中心的な役割を果たしています。
具体的には、
- 食料の安全保障
- 栄養不足の解消
- 作物や家畜、漁業と水産養殖を含む農業や農村開発
などの活動が挙げられるでしょう。
人々が健康な生活を送れるよう、量・質ともに十分な食料が行きわたるよう活動しています。
WFPによる学校給食プログラムの拡大
途上国の子どもたちを栄養不足から守るため、学校給食プログラムによって栄養バランスのとれた学校給食を提供しています。
給食を提供することで子どもたちが学校に通うきっかけを作り、誰でも教育を受けられるように。さらに、栄養改善が図れるだけでなく、地域の経済と生産者のサポートにもつながっている点もポイントと言えるでしょう。
発展途上国の農業支援・強化
飢餓をなくすためには、食料生産量を増やすことも必要です。そのため、さまざまな団体が発展途上国の農業支援などを行っています。
例として、デンマークとスウェーデンの企業の取り組みを紹介しましょう。
デンマークのバイオサイエンス企業「クリスチャン・ハンセン」:ケニアへの農業支援
世界的なバイオサイエンス企業「クリスチャン・ハンセン」は、ケニアへの農業支援を行っています。
小規模農家の労働条件を向上させるため、植物の病気を防ぐ植物防疫製品「Nemix C」をケニアの農業市場へ導入。農作物の収穫量を増やすことを目指しています。
スウェーデン国際農業ネットワーク(SIANI):「ビジネス・プラン・コンテスト」の実施
スウェーデン国際農業ネットワーク(SIANI)は、就農を目指す学生向けに、「ビジネス・プラン・コンテスト」を行いました。
農業経営のための教育講座を開講し、農業のノウハウを提供。農業のノウハウを学んだ人が増えれば、農作物の生産量を増やせるほか、生計を立てる方法に困る人も減らせるでしょう。
世界各国の食品ロス削減法(フランス・イタリアの食品ロス対策)
飢餓をなくすため、食品ロス対策も世界各国で進められています。先進国では、食品ロスに関する法律も作られています。
フランス:食品廃棄を禁止する法律
2016年に、店舗面積が400平方メートルを超える大型スーパーに対し、食品廃棄を禁じる法律が公布されました。この法律では、賞味期限切れの商品は、慈善団体への寄付あるいは肥料や飼料への再利用が義務付けられています。
違反すると、罰金が科せられます。
ユーロスタット(EUの統計局)のデータによると、政策実施後、2016年から2020年まで食品廃棄物の10%削減を実現したとのことです。
参照元:セカンドハーベストブログ
イタリア:食品廃棄を規制する法律
イタリアでも、2016年に食品廃棄を規制する法律が施行されています。食品の寄付手続きを簡単にすることで、食品廃棄物の削減を図る法律です。
イタリアの農業生産者団体 Coldiretti50が公表したデータによると、食品廃棄規制法が成立した2016年から4年間、食料の寄付は21%増加。食品廃棄物の削減も実現でき、一人あたり95kgから65kgとなりました。
参考文献:岩波佑子『フランス・イタリアの食品ロス削減法』2019年10月
「SDGs2.飢餓をゼロに」の日本企業の取り組み

SDGs2の実現に向け、多くの日本企業もさまざまな取り組みを行っています。どのような取り組みがあるのかを紹介していきましょう。
味の素株式会社
味の素グループでは、子ども食堂を応援する「アジパンダ食堂」を立ち上げ、フードロス削減と地域共食に取り組んでいます。
味の素グループで発生するフードロスの対象となる商品を、子ども食堂や地域食堂を運営する提携先に無償で提供。子どもたちの栄養改善をサポートしています。
また、フードロス対象商品を地域住民に販売することで、地域のフードロスへの関心向上にも貢献しています。
出典:味の素グループ
株式会社日本フードエコロジーセンター
株式会社日本フードエコロジーセンターは、食品工場やスーパーなどで余った食料から養豚用の飼料を作っている会社です。
「食品ロスに新たな価値を」という企業理念に基づき、食品廃棄物を有効活用するリキッド発酵飼料を産学官と連携して開発。廃棄物処理業と飼料製造業、2つの側面を持つ新たなビジネスモデルを実現しました。
この取り組みは、「ジャパンSDGsアワード」最優秀賞を受賞。捨てられてしまう食品を活用した液体飼料の製造が、SDGsに貢献していると評価されました。
出典:株式会社日本フードエコロジーセンター
セブン&アイ・ホールディングス
セブン&アイグループは、サプライチェーン全体で食品廃棄物削減の取り組みを継続しており、さまざまな工夫を図っています。
たとえば、
- コンビニでは、手前に置いてある商品から選んで購入する「てまえどり」の推進、オリジナルデイリー商品の消費期限延長、加工食品のフードバンク団体への寄付
- レストランでは、食べ切れるサイズの小盛のメニューや食べ残しのお持ち帰りを推進する「mottECO(モッテコ)」の取り組み
など、会社全体で食品廃棄物削減に注力しています。
消費期限の延長については、工場の技術革新によって製造工程や温度、衛生管理を見直し、「安全・安心の確保」と「味・品質の向上」を実現しました。
また、フードバンク団体に寄付した商品は、高齢者や子どもの支援を行っている団体・施設に分配されています。
出典:セブン&アイ・ホールディングス
イオン株式会社
イオン株式会社は、総合スーパーや不動産会社、金融会社などを展開する総合小売会社です。
食育実践活動事業を全国のイオン店舗で行っています。たとえば、食育イベントや食事相談ブースの併設、食育スタンプラリー、管理栄養士によるセミナーなどを開催。食育に関する意識を高められるでしょう。
食品ロスに関する取り組みとしては、「トップバリュ」の加工食品の賞味期限を緩和する対策が見られます。賞味期限が1年以上の商品を順次、年月日表示から年月表示に切り替えることで、食品の廃棄量を減らしています。
そのほか、廃食油や売れない魚のアラのリサイクルも実施。それらを飼料や油脂などにリサイクルして、食品ロスの削減につなげています。
参考文献:イオン環境財団 SDGsハンドブック
農林水産省との連携事例
政府は、2019年に「食品ロス削減推進法」を施行しました。農林水産省や厚生労働省・文部科学省・経済産業省などが連携し、食品ロスの削減を目指して、基本方針を定めています。
具体的には、
- 国や自治体に対して、食品ロスを削減するために、計画や啓発活動を行うこと
- 企業に対して、賞味期限の見直しや食べきりキャンペーンなどを行うこと
- 消費者に対して、買いすぎや食べ残しを減らすこと
といった行動を促す法律です。
自治体に対する取り組みの例として、ステッカーやPOPの掲示、食品ロス削減レシピの配布、食品ロス削減全国大会の実施などが挙げられます。
参考文献:環境庁『自治体職員向け食品ロス削減のための取組事例集』(令和6年10月更新版)
TABETEによる取り組み
飲食店や小売店の売れ残り食品を、消費者とマッチングするフードシェアリングサービスも、食品ロスを減らすのに有効です。
たとえば、TABETE。
ホテルや飲食店、スーパーなどのお店で、廃棄される可能性のある安全な食べ物と、それを購入したい消費者とをマッチングするアプリです。お店は無駄を減らして売上を伸ばせ、消費者もおいしく食べながら社会貢献ができます。
TABETE
SDGs2「飢餓をゼロに」の課題と今後の展望

SDGs2を実現するうえでどのような課題があるのでしょうか?
今後の展望についても解説していきます。
あらゆる方面から取り組む必要性(社会保障・流通網・栄養改善)
SDGs2を達成するためには、以下のようにあらゆる方面から取り組む必要があります。
- 貧しい人を優先して社会保障制度を充実させる
- 農家と市場がスムーズに繋がる流通網を整備する
- 子どもの最初の1000日間(胎児~2歳の誕生日まで)の栄養状態を改善させる
具体的には、小規模農家にドローンによる農薬散布や水分センサーを使ったスマート農業の導入、有機肥料の利用による土壌改善などを行い、安定した食料供給を可能にする。農道や灌がい施設の整備支援など、農村インフラを整えるなど、食資源を世界中の人々が手に入れられるよう、多角的な面からの対策が求められます。
飢餓と気候変動・貧困とのつながり
先述したように、飢餓のおもな原因となっているのが、気候変動による貧困です。
気候変動によって干ばつや洪水などが引き起こされ、農業ができずに貧困状態に陥ってしまう。貧困状態になれば、飢餓のリスクも高まります。
そのため、飢餓をなくすには、農業支援など食料の供給に関わる取り組みだけではなく、気候変動問題に対する対策にも取り組まなければいけません。気候安定化の具体的な対策としては、森林保全や植林活動、クリーンエネルギーの使用などによる温室効果ガスの削減などがあります。
SDGs2の達成期限と現状の遅れ
FAOやIFADなどを含む国連5機関が共同で発行している報告書「世界の食料安全保障と栄養の現状(2024年版)」によると、2023年、世界では11人に1人、アフリカでは5人に1人に相当する、約7億3,300万人が飢餓に直面したと言われています。
国連は2030年までにSDGs2の達成を目指していますが、FAOやWFPといった専門機関は世界が大きく遅れをとっていると警告。目標を実現するため、農業・食料システムの変革と強化、不平等に対する取り組み、全ての人に健康的な食事を手ごろな価格で入手可能とすることなど、多様な取り組みが必要だと述べています。
参考文献:IFAD『世界の食料安全保障と栄養の現状(SOFI):2024年版報告書』
わたしたちにできること|家庭・個人での取り組み

ここでは、SDGs2を達成するために、わたしたちができることを詳しく解説。
できることから少しずつ取り組むことが大切です。ぜひ参考にしてください。
食べ残しをゼロにする工夫(買い物・調理・保存のポイント)
すぐにできることとして、まずは食べ残しをゼロにすることから始めてみましょう。
たとえば、
- 食べきれる量を考えて買い物する・作る
- 賞味期限・消費期限をこまめにチェックして、食材を使い切る
- 嫌いなものでも食べられるように工夫する
- 給食は自分が食べられる分だけ取る
などが挙げられます。
野菜嫌いなお子さまがいるなら、ミキサーで細かくする、小さく切り刻んでわからないように料理に入れる、など工夫してロスが出ないようにするのもひとつの方法です。
また、それぞれの野菜や果物に合った保存方法があるので、少しでも鮮度が長く保たれるよう、適切な保存方法を調べて実行するとよいでしょう。(※参考:デリッシュキッチン)
日頃から食べ残しを減らすことは、食料を作るための土地や水、エネルギーを無駄にしないということ。資源が守られることで、世界中の人に食べ物が行き渡りやすくなるため、世界の飢餓の削減につながるのです。
子どもと一緒に取り組むSDGs(教育・食育・ゲーム教材など)
お子さまと一緒に献立を考え、必要な食材の買い物に一緒に行き、お子さまの食への関心を高めることが大切です。
お子さまと買い物をする際には、消費期限の短い物を選ぶ、原産国をチェック、季節の野菜や果物を探す、ということを心がけると、お子さまの食に対する意識がめばえるかもしれません。こういった体験を通して、食べ物を大切にする気持ちや、食料を作る人・環境への関心を育むことができます。
お子さまと一緒に冷蔵庫や家にある物だけで献立を考えると、ゲーム感覚で楽しく取り組めますし、食材を余らせることも少なくなるでしょう。
また、SDGsを学べるゲームを取り入れてみるのもおすすめ。
SDGsを効果的に学べるボードゲーム「ゲット・ザ・ポイント」は、小学生でも直感的にプレイできる、ポイントを取り合うゲームです。親子で楽しみながらSDGsを学べるため、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
【公式】子どもと大人のSDGs学習ゲームGet The Point
「ゲット・ザ・ポイント」は、公式オンラインショップで購入できます。
すなばコーポレーション
フードバンクや寄付活動に参加する
フードバンクや寄付活動に参加することも、SDGs2を実現するためのひとつの方法です。
たとえば、レッドカップキャンペーンと呼ばれる活動があります。
WFPが給食を入れる容器として使っている、赤いカップのマークが目印。

引用元:国連WFP協会
このマークが付いた商品を購入するだけで、売上の一部が学校給食支援に役立てられます。
マークがついた商品はスーパーや小売店、ECサイトで購入可能。
キューピーや日清食品など多くの企業が賛同し、マーク付きの商品を販売しているので、買い物をする際には意識して探してみるのもよいでしょう。
レッドカップキャンペーン
困窮家庭や施設などで活用するために、家で余っている食材を寄付できるフードバンクを活用するのもおすすめです。地域によって回収場所や回収方法、寄付できる物が異なりますので、インターネットで調べたり、自治体に問い合わせたりしてください。
SDGsについては、お子さまと一緒に本を読むのもおすすめです!
【SDGs本】子どもと一緒に読むならこれ!おすすめ9選
みらいいおすすめ!「こどもSDGs なぜSDGsが必要なのかがわかる本」をご紹介!
SDGsを学ぶにあたって、以下の記事では、小学生向けの教材を紹介しています。
【SDGsについて知ろう!】小学生向けの教材をご紹介
私たちの行動が世界に与える影響
先述したように、世界の飢餓の原因は、食料生産が追いついていないからではありません。世界中の一人ひとりが十分に食べられるだけの食料が生産されています。
しかし、3分の1が廃棄されているため、食品ロスを減らす工夫をすることは、確実にSDGs2の実現につながることを覚えておきましょう。
食べ物を大切にすることは、食料を作るための資源も大切にするということ。限られた資源が守られることで、世界中の人に食べ物が行き渡りやすくなるため、世界の飢餓の削減につながるのです。
まとめ|SDGs2「飢餓をゼロに」は私たち一人ひとりの行動から

飢餓問題は遠い国の話ではなく、身近な食生活とつながっていることをまず理解することが大切です。
自分ひとりが実行したところで、そんなに影響はないのでは?と思うかもしれませんが、一人ひとりの力が集まれば大きな力となります。たとえば、世界中の人々が食べ残しを減らすことを心がけるだけで、それは多くの資源や食料を守る力につながるでしょう。
改めて、世界・企業・個人の三位一体で取り組むことの重要性を再確認し、「食品ロスを減らす」「子どもが嫌いなものを食べられるように工夫する」など、SDGsを自分事ととらえて、親子でできることから始めてみましょう。
みらいいではSDGsに関するさまざまな取り組みをご紹介しています。ぜひこちらもご覧ください!
【身近なSDGs特集】未来のために子どもたちと「いま」からできること
【みんな知ってる?】SDGsとは?17の目標の解説をまとめました!
【SDGsについて知ろう!】小学生向けの教材をご紹介












%20(1).jpg)